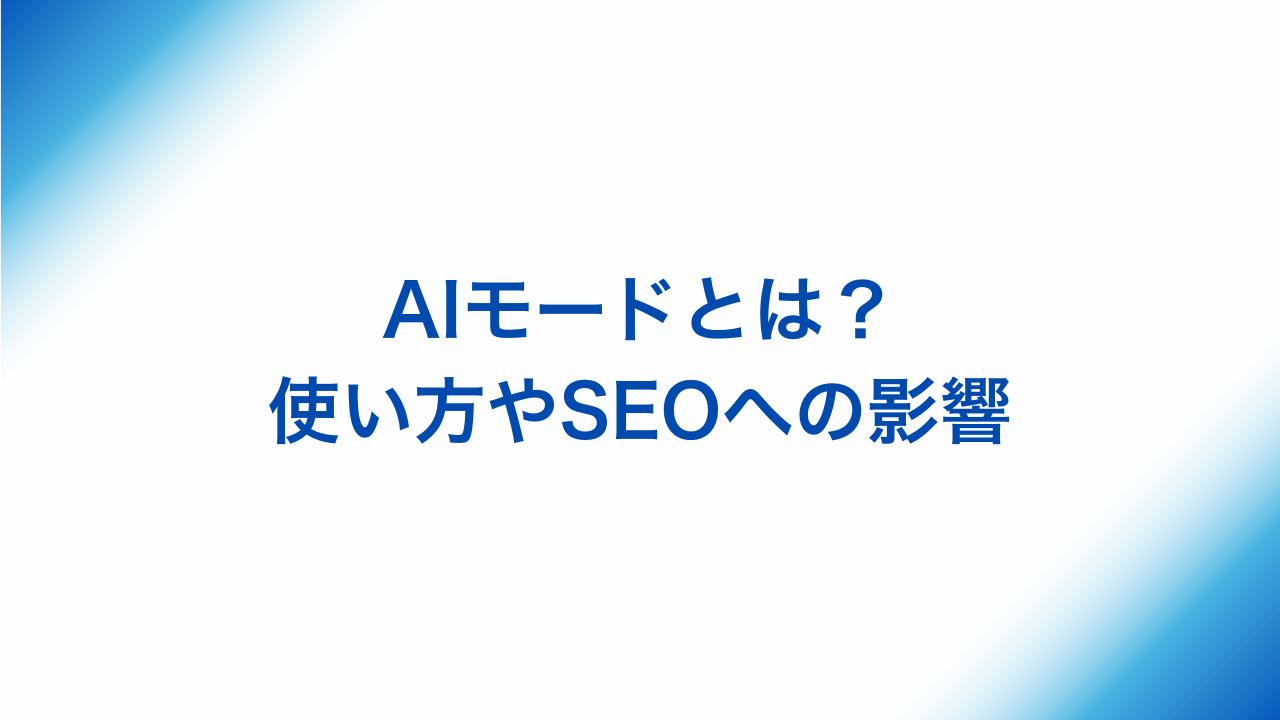Google検索の新たなAI機能「AIモード」が、2025年9月より日本でも提供開始されました。
- AIモードとは何か知りたい
- AIモードの特徴や仕組み、機能、従来の検索結果との違いを知りたい
- AIモード実装への対策のポイントや注意点を把握したい
この記事を読んでいる方の中には、上記のように考えている方もいることでしょう。
この記事では、「AIモードの特徴や、メリット・デメリット、具体的な機能、コンテンツ制作者が対策を実施するうえでのポイント」などについて解説します。
AIモードを使いこなしたい方はもちろん、AIモード対策を検討している事業者の方もぜひご覧ください。
AIモードとは
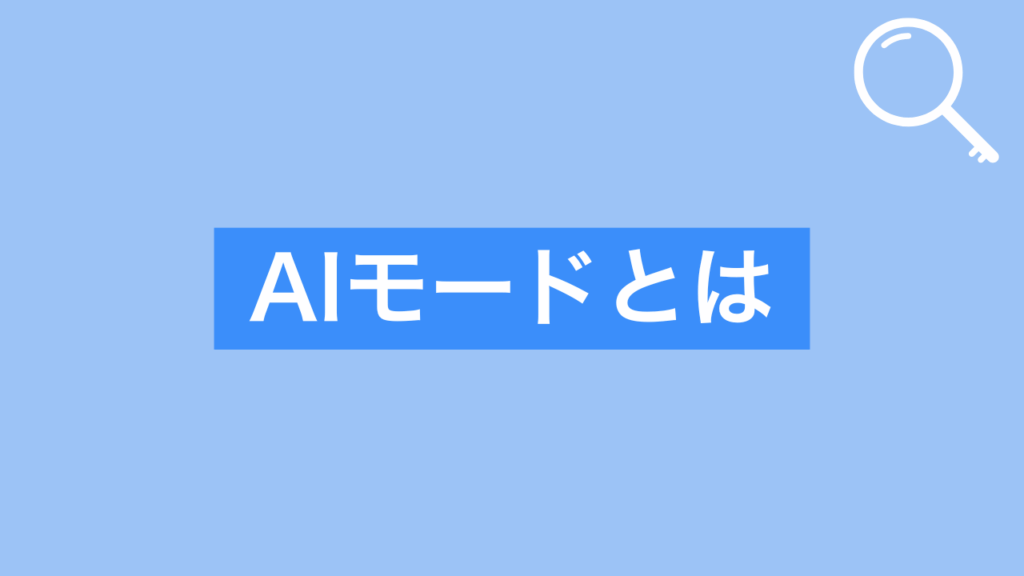
AIモードとは、検索の内容に合わせてAIが回答を作成・提示する機能のことです。
AIモードの導入により、従来のように検索結果の中でリンクを比較・選択する方法から、AIが提示した要点の要約チェックへの変化が予想されます。
検索結果の画面上部に生成された回答が並んで出典も合わせて示され、さらに質問を重ねると回答が深まります。
業務の下調べや比較検討の初動を短時間で行える、魅力的な機能だといえるでしょう。
AIモードとはGoogle検索に合わせて生成AIが回答を表示する機能
AIモードとは、Google検索に合わせて生成AIが回答を表示する機能です。
検索クエリに合わせて、生成AIが要点をまとめて表示します。
従来の検索結果画面と完全に置き換わってしまうのではなく、画面の上部に回答カードが表示されるイメージです。
要約と根拠となる出典が並び、ユーザーの理解を助けます。
質問の言い回しが多少あいまいでも、意図に沿う回答へと導ける仕組みです。
AIモードでは追加での質問が可能であり、同じ画面で深掘りまでが完結します。
買い物や予約など、次の行動につながるリンクも表示されるので、検索から意思決定までの距離が短くなるでしょう。
AIモードではAIが文脈を理解して回答を行う
AIモードでは、AIが文脈を理解して回答を行います。
単なるキーワードの検索ではなく、質問の意図と背景を読み取った応答が可能です。
追加で質問をしていく場合でも、前のやり取りを踏まえて条件や好みを保ったまま答えを更新してくれます。
否定や例外の指定など複雑な制約にもある程度柔軟に対応可能であり、長文も整理して生成AIが結論から提示します。
また、出典のような形式で根拠を示してくれるので、内容の確認や再検索がしやすくなる点も大きな魅力です。
表や手順の形式でまとめ直してくれるため、読みやすさも高まります。
結果として、文脈の誤解によるミスが起きにくくなるでしょう。
Gemini統合とマルチモーダル対応を行う
AIモードの中核には、Googleの生成AI「Gemini」が組み込まれています。
画像や音声、動画など複数の情報を同時に解釈可能であるため、文字以外での質問が可能です。
たとえば、型番やラベルが映っている写真から、該当製品の情報を引き出します。
音声の指示で条件を指定し、手を離したまま操作することも可能です。
また、提出した資料を要約し、要点と抜けを短時間で洗い出してもらうような利用方法も考えられるでしょう。
図や表の自動生成も可能であり、比較や集計も同じ画面内で完結できます。
マルチモーダル機能を活用すれば、説明の手間を省けるはずです。
【表で整理】AIモードと従来検索の違い
従来検索は表示されているリンクをクリックする方法が主で、ユーザーが主体的に検索行動を行います。
対してAIモードは要約が中心で、次の行動までを瞬時に導いてくれます。
違いを一覧で確認し、導入判断の材料にしてください。
| 項目 | AIモード | 従来検索 |
|---|---|---|
| 表示の主役 | 回答カード | 青いリンク |
| 根拠の提示 | 出典を併記 | 各ページで確認 |
| 操作性 | 追質問で深掘り | 再検索で絞り込み |
| 作業の進行 | 比較や要約を内製 | ユーザーが整理 |
| 入力手段 | テキスト以外も可 | テキスト中心 |
| 到達スピード | 結論が速い | 情報収集に時間 |
AIモードの方がより効率的で統合的なアプローチを取っており、情報探索の初動コストを削減できます。
【表で整理】AIモードとAI Overviewsの関係と違い
AI OverviewsはAIが検索結果を要約してくれる機能の名称であり、表示の形全体を指します。
一方のAIモードは検索機能名称であり、機能の束を示します。
両者の位置づけを整理すると、戦略設計が明確になります。なお、AI Overviewsは「AIO」とも呼ばれます。
| 観点 | AIモード | AI Overviews |
|---|---|---|
| 範囲 | AIアシスタント機能 | 検索結果の要約機能 |
| 操作 | 質問による双方向の会話 | 回答の閲覧が中心(簡易的な追加質問も可能) |
| 入力 | テキスト以外も対応 | テキスト起点が主 |
| 継続性 | 質問により継続 | 検索ごとに完結 |
| 拡張 | 表やグラフ生成などカスタマイズが可能 | 要点要約が中心 |
AIモードの方が、より包括的で多機能なアプローチを取っていることが分かるでしょう。
AIモードの日本での提供状況と対応環境(2026年2月時点)
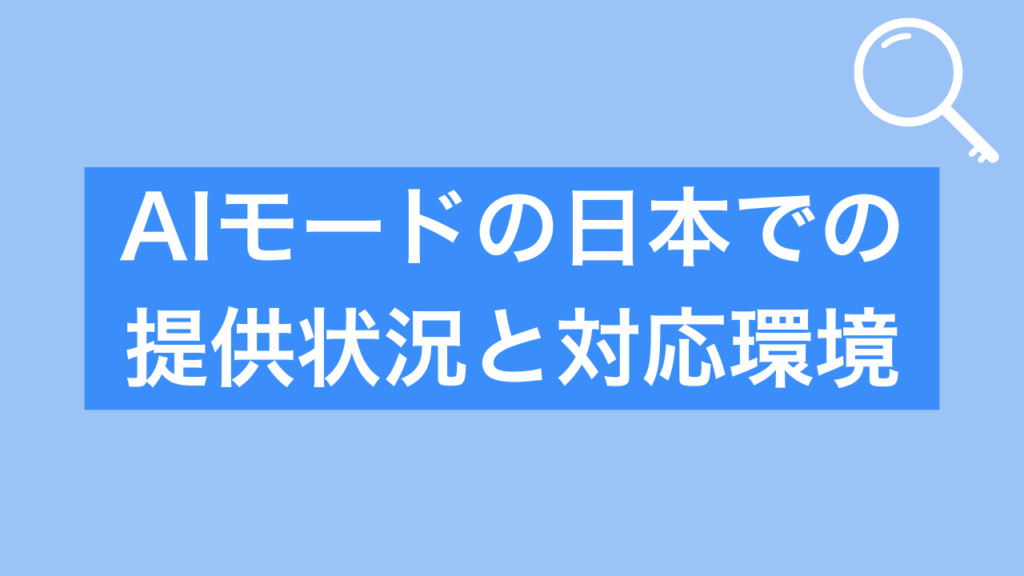
日本語でのAIモードは、2025年9月9日に提供が始まりました。
AIモードは、PCのブラウザとスマホのGoogleアプリの双方で利用可能です。
国や言語の設定、アプリの更新状況により表示有無が異なると予想されます。
日本では2025年9月9日より提供開始
AIモードの日本語提供は、2025年9月9日よりスタートしました。
機能の提供は一斉ではなく、順次拡大していくと思われます。
検索結果ページにAIモードのタブが現れたら、AIモードが利用できます。
まだ表示されていない場合は、言語を日本語に設定し直してみましょう。
ブラウザのキャッシュ削除やログインのやり直しも有効です。
パソコン・スマートフォンのどちらでも利用可能
AIモードは、パソコン・スマートフォンのどちらでも利用可能です。
パソコンでは、主要ブラウザからAIモードのタブに切り替えて使います。
スマホでは、GoogleアプリでAIの回答カードが表示されます。
音声やカメラ入力であればスマホが手早く、現場で便利です。
ただし、パソコンでもマイクやカメラを許可すれば、同様の入力が十分に可能です。
AIモードの主な機能
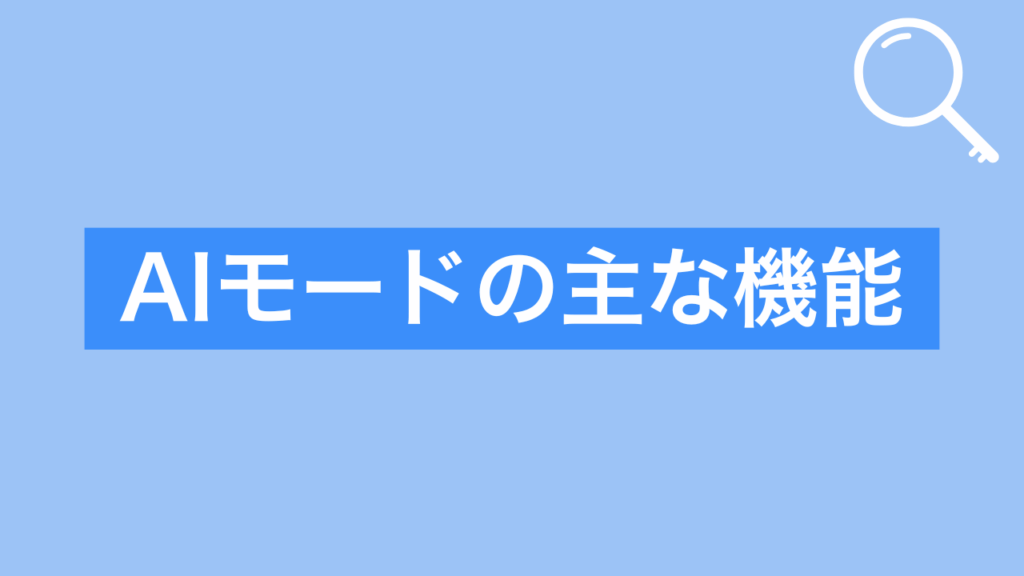
AIモードは、調査から意思決定までの流れを包括的にサポートしてくれる機能です。
長文の要約や比較の整形を自動でこなし、ユーザーの作業にかかる時間を短縮します。
また、画像や音声も使えるため、入力の手間が少ない点も魅力的です。
出典確認や追加質問で、回答に対する迷いを減らしながら前に進めます。
Deep Searchによる調査のサポート
Deep Searchは、複雑な質問を分解して調査してくれる機能です。
関連する観点や抜けやすい条件も補い、視野を広げて回答してくれます。
長い記事や複数の出典を横断し、結論と根拠を並べて示します。
重複情報はまとめ直して比較しやすい形に整える、専門用語には短い説明を添えて理解しやすくするなど、ユーザーをサポートしてくれる革新的な機能です。
Search Liveによるリアルタイムのカメラでの質問
Search Liveは、カメラを使ってリアルタイムに映像を見せながら質問できる機能です。
配線や部品の名称など言葉にしづらい分野において、Search Liveは効果を発揮します。
カメラによって映った文字やラベルを読み取り、AIが関連情報へ案内可能です。
音声による条件・指示の追加も可能であり、手がふさがっていても操作できます。
Search Liveを活用すれば、専門的ジャンルで説明・理解しづらい内容でもすぐに問題を解決できるでしょう。
エージェント機能による検索から購入までのサポート
エージェント機能は、さまざまなタスクにおいてユーザーを代理し、自動的に実行してくれる機能です。
計画立案や商品・サービスの比較、予約手配などさまざまなタスクを代行してくれます。
エージェント機能が優れているのは、関連する作業や情報を加味したうえでタスクを実行してくれるところです。
たとえば、「来週の沖縄旅行の計画を立案して」と指示すれば、交通手段や宿泊施設の比較、おすすめの観光地の確認などを包括的に実施してくれます。
要件変更にも追従し、再提案を即座に実行可能です。
また、学習機能によってこれまでの選択履歴に合わせてパーソナライズされたサポートを実施してくれます。
AIショッピングパートナーで商品の検索時間を短縮
AIショッピングパートナーは、商品・サービスの比較から購入までを包括的にサポートしてくれる機能です。
用途と予算から、候補を即座に絞ります。
比較表で主要スペックを並べてくれるので、各商品・サービスの違いをひと目で把握可能です。
レビュー傾向を要約し、長所と注意点を端的に示してくれます。
在庫や価格の変動なども反映してくれるので、買い時の判断の助けにもなるでしょう。
パーソナルコンテキスト機能で自分仕様の検索結果を表示
パーソナルコンテキストは、検索履歴に合わせてパーソナライズされた提案をしてくれる機能です。
ユーザーの好みや既知情報を検索履歴から分析し、回答内容を調整します。
また、GoogleマップやGmailなどと連携させれば、現在地やこれまでの連絡内容なども参考にした回答・提案が可能です。
パーソナルコンテキストの設定は後から変更でき、無効化や履歴からの個別削除もできます。
AIがデータからチャートとグラフを作成・分析
AIモードでは、貼り付けた表や数値から、適切なグラフを自動生成してくれます。
棒グラフや線グラフ、円グラフなど、さまざまな形式のグラフ・チャートを生成可能です。
外れ値の指摘や傾向の要約・考察も同時に返してくれるので、洞察を得やすくなるでしょう。
比較対象を追加すれば、差分の根拠も短く説明可能です。
AIモードの使い方
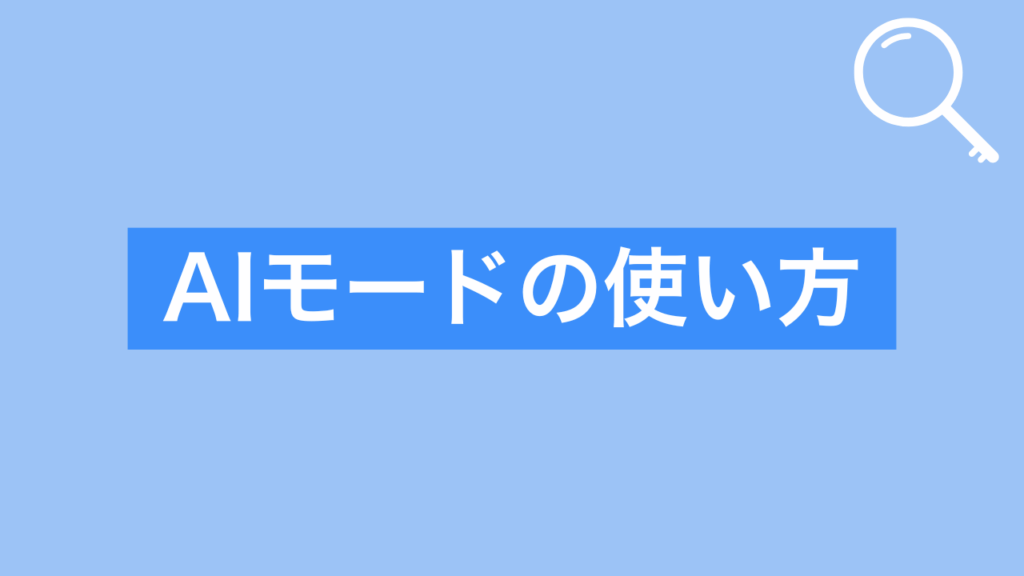
AIモードは検索バーから起動でき、そのままチャット形式で質問できます。
回答を基点とした追加質問や出典確認もできて、設定からオンオフ切り替えも簡単に実施可能です。
ここではAIモードの基本的な使い方を紹介します。
ただし、画面要素の位置や名称は随時変わる点にはご留意ください。
検索バーのAIモードから質問できる
AIモードは、検索ページのバーにある「AIモード」のボタンを選び、質問を入力するだけで簡単に回答を得られます。
質問事項を記載したうえでEnterで送信すると、要点をまとめた回答カードが表示されます。
条件が多い場合は、箇条書きで並べるとAIの理解が速いのでおすすめです。
画像や音声も入力できる環境なら、その場で添付して情報として追加できます。
できるだけ不要な言葉は記載しないようにすると、回答に含まれる不要な情報を減らせるでしょう。
また、地名や日時などの前提を先に示すと、回答の精度が高まります。
たとえば、「雨でも楽しめる場所」とだけ質問するのではなく、「10月の東京で雨でも楽しめる場所」と書くのがおすすめです。
検索意図がまだ固まっていない場合は、会話形式で徐々に情報を追加していってください。
チャット形式でフォローアップ質問と出典リンクを利用できる
AIモードでは、AIの回答の下に続けて質問を入れることで、文脈を読み取ってさらに深掘りした回答を返してくれます。
「追加したい・除外したい条件」を追加していけば、回答の精度を高めていくことが可能です。
また、AIの回答に掲載されている出典リンクを開けば、根拠となっているサイトへすぐに移動できます。
AIの回答と原文を往復して情報収集すれば、誤解を避けやすいでしょう。
さらに、比較が必要な時は「表で比較したい」などと指示すると整形されます。
途中で聞きたい内容が変化したら、「前提をリセット」と明示してください。
オフにする際には「Search Labs」アイコンから
AIモードをオフにする際には、画面上部のフラスコアイコンを開き、「AIモード」をオフに切り替えます。
反映は原則として即時ですが、念のため再読み込みをすると確実でしょう。
端末を共有する場合は、オフにしておけば意図しない情報の保存を避けられます。
子どもが触れる端末では、履歴設定も合わせて点検しておくのがおすすめです。
AIモードのUI構成イメージ
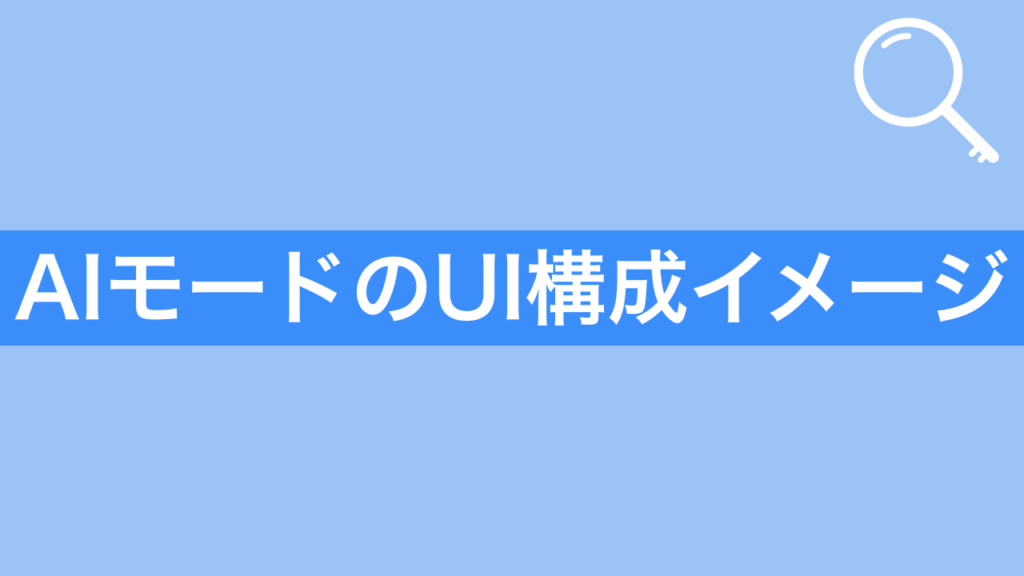
AIモードの画面ではAIの回答が中心に据えられており、ユーザーを次の行動へ誘導します。
上部に回答カードが並び、根拠と操作が一目で把握可能です。
追加質問欄は常に表示されており、それまでのやり取りの文脈を保ったまま情報を深掘りできます。
音声や画像の入力に切り替えても、回答枠は同じ配置です。
回答カード・出典リンク・関連アクションで構成されている
AIモードの画面は、回答カード・出典リンク・関連アクションで構成されています。
回答カードは、要点の段落と小さな見出しで構成されているシンプルなものです。
回答カード右上や下部に出典が並び、クリックで要約の根拠となったサイトへ移動できます。
出典は複数サイトが均等に表示されており、偏らないように配慮されている構成です。
長文回答は折りたたまれ、展開ボタンで続きを確認できます。
また、共有のアイコンからメモやチャットへの転送も可能です。
画面下のテキスト欄に続けて質問を入れると、文脈を維持したまま追加質問が可能です。
音声・画像入力時でも、画面のイメージは大きく変わらない
音声・画像入力時でも、AIモードの画面のイメージは大きく変わりません。
音声入力ではマイクボタンが強調され、録音中は波形が動きます。
一時停止とやり直しが並び、誤認識の修正も即座に可能です。
画像入力ではプラスボタンで写真を添付でき、範囲指定も可能です。
AIモードにより想定されるクエリへの影響
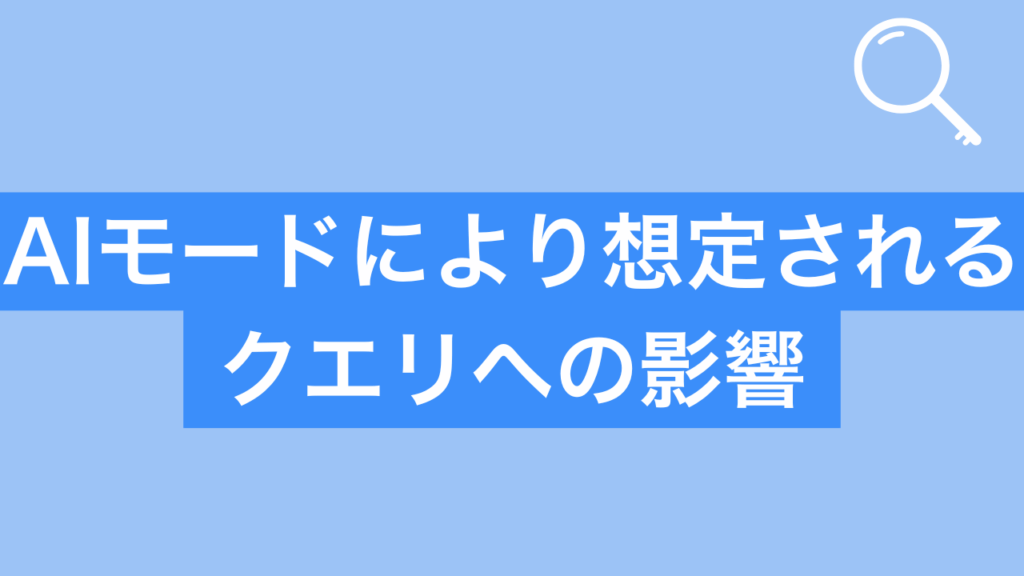
AIモードは、検索の冒頭で答えをまとめて示します。
従来とは全く異なる検索体験であり、一部のクエリにおいては検索結果に大きな影響が出ると想定されています。
コンテンツ作成においては表示されやすい情報を意識し、AIから引用されるように設計することが重要です。
比較系クエリではランキングや比較の概要を自動生成
AIモードでは主要な比較候補を自動で抽出し、それぞれの違いを簡潔に整理して表示します。
価格やサイズなどの比較項目を明確に並べることで、要点を一目で把握できるようになります。
ユーザーが指定した条件に合わない候補は除外され、関連性の高い選択肢のみが整理されて提示されます。
AIモードでは情報は表形式や箇条書きなどの見やすい形に変換されるため、長文を読み進める負担が軽減されます。
気になる項目については追加質問により深掘りでき、不要な条件は除外することも可能です。
各項目の出典リンクから元の詳細情報へ直接アクセスし、より詳しい内容を確認できます。
また、比較記事では冒頭に要約を配置することで、AIモードに取り込まれる可能性が高まるでしょう。
ローカル系クエリでは検索条件に合う店舗を提案
ローカル系クエリでは、場所や時間などの条件を追加すると、該当する店舗候補が素早く絞り込まれて表示されます。
営業時間や混雑状況の目安など、実際に訪問する際に必要な情報が整理して提示されます。
店舗の写真やメニューの要点も要約表示されるため、事前に雰囲気を把握できます。
徒歩や電車での移動時間も併せて表示されるため、具体的な訪問計画が立てやすいです。
予約サイトや問い合わせ先への導線が近くに配置され、スムーズに次の行動へ移れるでしょう。
また、利用者レビューの傾向も簡潔にまとめられ、評価を事前に把握できます。
店舗側では最新情報を適切に整備すれば、AIモードの提案候補に選ばれる可能性が高まるでしょう。
B2Bサービス系クエリでは各ツールのスペック一覧表を生成
業務用サービスやツールの選定時には、各サービスの機能と料金を比較した表が自動的に生成される傾向があります。
対応範囲や導入形態などの重要な比較項目が、統一された形式で整理されて表示されるでしょう。
ユーザーが検討要件の優先度を伝えれば、ツールの並び順が要件に応じて最適化されます。
導入事例やサポート体制の概要も簡潔に付加されるので、総合的な判断が可能です。
生成された表には必要に応じて列を追加でき、検討漏れを防ぐことに役立ちます。
各項目の出典となる企業ページへ直接移動し、より正確で詳細な情報を確認できます。
コンテンツの作成者側としては、表形式での情報整理を行うことで、AIモードでの参照頻度を高められるでしょう。
AIモードによる検索行動への影響
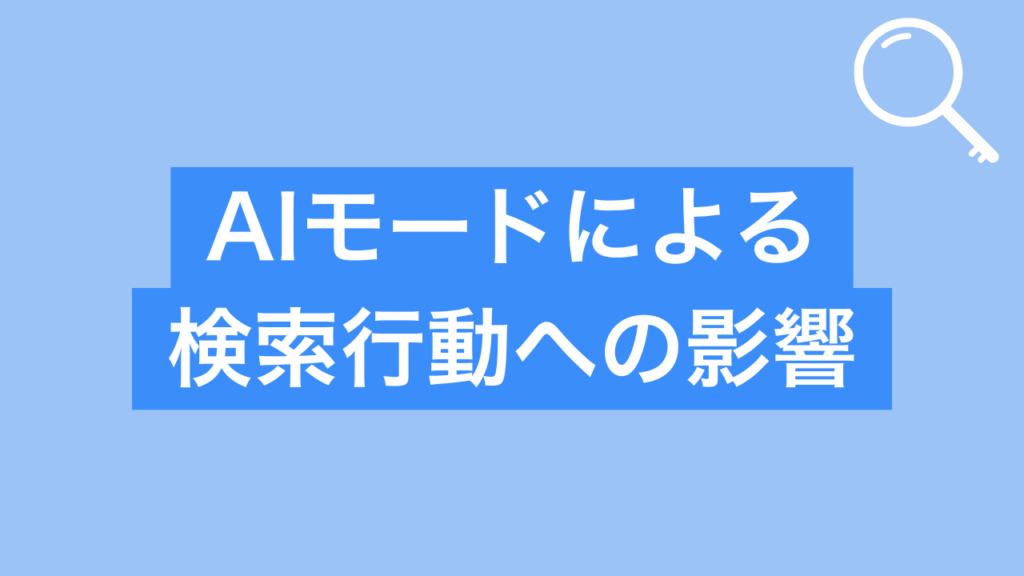
AIモードの普及により、検索行動は「入力→一覧」の型から離れていくと予想されます。
画像や音声の活用が進めば、検索から意思決定に至るまでの時間が短縮されるでしょう。
個々のユーザーにパーソナライズされた提示が増え、検索体験は個人ごとに変化していくはずです。
従来型のSEO対策から変化し、指名検索の重要度が増す可能性もあるでしょう。
テキスト以外での検索が増える
AIモードの普及により、テキスト以外の検索方法が増えていくと予想されます。
写真を撮って質問したり、音声で条件を伝えたりする検索方法が確実に増加していくでしょう。
型番や配線図など、文字で表現しにくい質問については、画像による検索が特に効果を発揮します。
結果として仕事現場や移動中での検索機会が拡大し、検索行動は「その場での即座対応」へと変化していくと想定できます。
検索結果もカード形式で素早く理解できるので、繰り返し検索の必要性が減少します。
企業側では、画像の代替テキストや分かりやすいファイル名の設定が重要な要素となるでしょう。
また、音声入力を前提とした簡潔な質問に対する回答設計も、コンテンツ作りにおいて不可欠な対応となるはずです。
図解や手順を示す画像を組み込む際には要点を冒頭で説明し、音声読み上げでも内容が伝わる構成にすることも求められます。
検索行動が対話型へと変化する
AIモードが検索の基本になれば、ユーザーは一度の検索で完璧な答えを求めるのではなく、追加質問を重ねながら段階的に答えを絞り込むようになります。
条件の追加・除外を会話形式で伝えていくことで、検索結果を段階的により精度の高いものへと洗練していくことが可能です。
重要な情報は表や箇条書きなどの形式に自動整理されるため、内容確認の負担が大幅に軽減されるでしょう。
また、AIモードの回答カードから出典リンクへ即座にアクセスできるため、情報の検証と意思決定を同一画面上で効率的に進められます。
また、FAQ形式での情報整理や結論を先頭に配置する構成は、対話のステップ数短縮に直接的な効果をもたらします。
誤解を防ぐための否定条件や除外事項の明記も、AIによる情報選別において重要な要素だといえるでしょう。
コンテンツを作成する側としては、最初の検索結果に選ばれるよう、要旨と根拠を簡潔な文章で明確に提示する姿勢の徹底が重要です。
検索体験がパーソナライズされていく
AIモードが検索の基本になれば、ユーザーの検索履歴や設定条件を基に、個人ごとに最適化された回答が提供される場面が増加していきます。
たとえば、予算範囲やサイズの希望などといった個人ごとの条件・設定が保持され、条件に合わない候補が自動的に除外されるようになるでしょう。
ユーザーの地域や時間帯なども考慮され、実際の行動に直結する情報が優先的に表示されるようになります。
一方で、ユーザーに公平な比較検討の材料を提供するためには、情報の出典確認が従来以上に重要です。
コンテンツの作成・運用においては、「どのような人にとって最適な情報か」を冒頭で明確に示す設計が効果的だといえます。
同一ページ内に初心者向けと上級者向けの異なる要約を併記すれば、幅広いユーザーに対応可能です。
また、構造化データを活用してAIに対してユーザー属性を明示し、適切な文脈での情報提供に繋げることも重要です。
自社・ブランド名の認知度拡大が重要になる
AIモード実装後は回答カードの内容に取り上げられる重要性が高まり、従来のリンク表示によるコンテンツの露出機会の減少が想定されます。
そしてAIモードの検索では、「〇〇(ブランド名) バッグ」のように、知っている企業・ブランド名で指名検索する人が増えると予測可能です。
そのため、企業名やブランド名で指名検索される、あるいは部分的なキーワードでも想起されることが、安定的な流入確保には欠かせません。
社名表記と商品名の統一的な使用は、AI回答内での正確な識別を促進する要素となります。
独自の調査データの公開や分かりやすい図表を提供できれば、AIに選択される確率を大幅に上げられます。
また、記事の著者や監修者の情報を明記すれば専門性の高さを証明でき、AIからの信頼性向上が期待できます。
さらに、AIの要約に採用されやすい冒頭要旨と表形式データの整備をおこない、コンテンツの参照価値を高めていってください。
AIモードのメリット
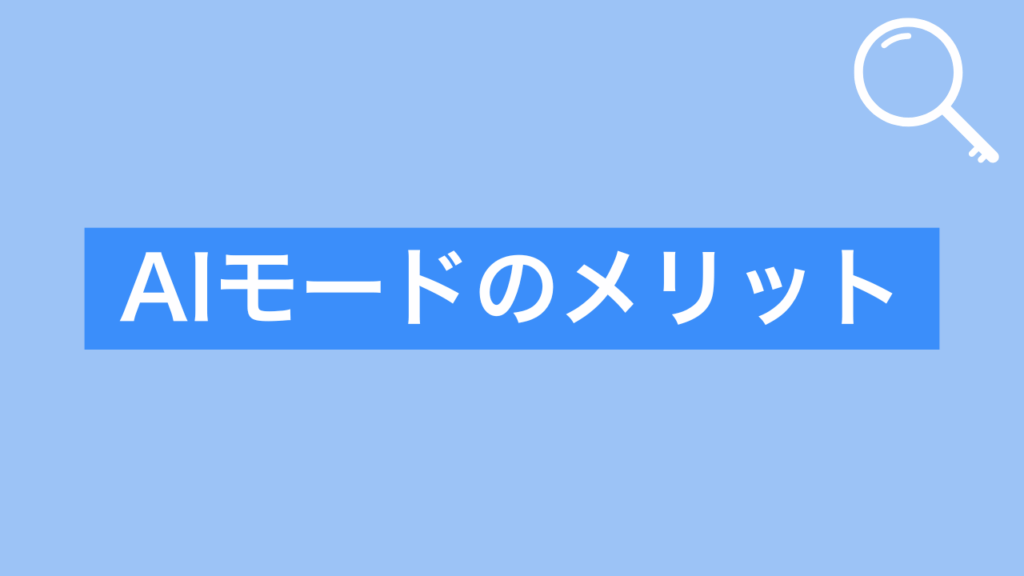
AIモードは要点を先に示してユーザーの迷いを減らし、次の行動へと前進させます。
出典リンクも近くに並んでいるため、要点の確認から次の行動までがスムーズになるでしょう。
また、音声や画像の活用で、入力の負担も同時に下がります。
結果として意思決定の初動が速まり、検索行動に対するハードルが下がるでしょう。
複雑な質問でも意図を汲み取って解答してくれる
AIモードでは、複数の条件を含む複雑な質問でもユーザーの意図を正確に読み取り、要点をまとめた回答を提供可能です。
重要な結論が最初に提示されるため、意思決定に必要な時間を大幅に短縮できるでしょう。
「〇〇は除外したい」といった否定条件や例外事項の指定にも適切に対応し、不要な選択肢を排除できます。
過去のやり取りの内容を記憶して文脈として活かしてくれるため、前提条件を維持したまま情報をアップデート可能です。
また、回答内容を表形式や手順リストなどの見やすい形に自動整理してくれるため、ユーザーは内容確認の負担を大幅に軽減できます。
情報が不足している部分については追加質問で補完でき、段階的により深い検討が可能になります。
理解が困難な専門用語については、簡潔な説明が自動で付加されるので、知識レベルを問わず情報の理解が可能です。
リンク付き回答で探索と回遊を促進する
AIモードの回答カードには情報の出典が明確に記載されているため、根拠となったWebサイトの情報読み取りにかかる時間を大幅に短縮可能です。
複数の異なる視点からの情報が整理して表示されるので、情報に偏る心配が低いといえます。
また、商品やサービスの比較が必要な場合は自動的に表形式に変換され、違いや特徴が一目で分かります。
関連する次のアクションへの導線が近くに配置されているため、スムーズな情報収集と意思決定につながります。
これらの機能により、より深いリサーチが自然に促進され、ユーザーの学習効率が向上します。
コンテンツ提供者側としては、要約に適した冒頭文の作成により、AIによる情報収集の対象に選ばれやすくなります。
信頼性の高い情報源としての評価確立は、長期的なブランド価値の向上に直結します。
マルチモーダル入力で検索のハードルを低減する
音声や画像での質問が可能になれば、複雑な内容の検索にかかる負担が大幅に軽減されます。
たとえば、写真に写った型番やラベルをAIが自動で読み取り、該当する製品情報や関連情報へ直接案内してくれます。
現場の状況を写真でそのまま示せるため、長い文章での説明が不要です。
また、画面のスクリーンショットに簡単な注釈を付けて質問すれば、問題解決までの時間を大幅に短縮できるでしょう。
移動中は音声入力、デスク作業時はテキスト入力というように、状況に応じて最適な方法を選択できます。
AIが内容を誤認識した場合でも、その場で再撮影や再入力ができるため、簡単に修正可能です。
入力方法の選択肢が増えることで、より直感的な検索が可能になり、試行錯誤の回数が減少するでしょう。
年齢や技術レベルを問わず誰でも検索がしやすくなれば、デジタル情報へのアクセス格差(デジタルデバイド)の解消にも貢献が期待できます。
AIモードのデメリットやリスク
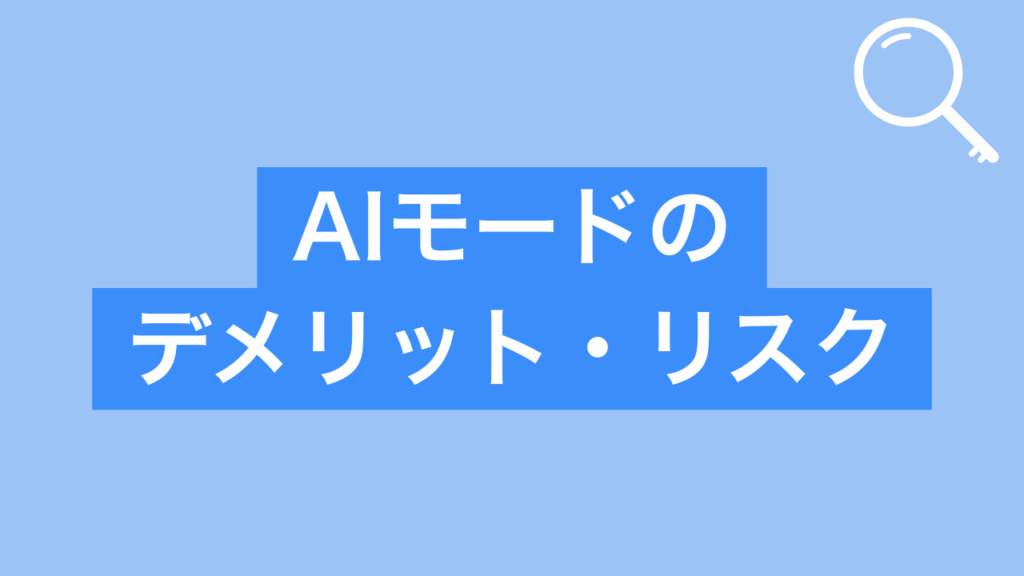
AIモードは便利な反面、検索に関わるさまざまな前提に変化をもたらします。
従来型のクリックが減る恐れや、出典品質のばらつきにも注意が必要です。
一時保存や履歴連携の扱いも、ここでチェックしておくことをおすすめします。
AIモードの影響を把握し早期に対策をとっておきましょう。
ゼロクリックが増加する
AIの回答カードでユーザーの疑問が解決する機会が増えれば、元のサイトへのクリックが発生しない場面の増加が予想されます。
特に用語の定義や価格相場など、簡潔な回答で十分な質問については、この影響が顕著に現れる可能性が高いでしょう。
検索結果での露出は維持されていても、実際のサイト流入数との間に大きな乖離が生じることが深刻な課題となります。
ゼロクリックへの対策としては、コンテンツ冒頭への要約掲載やFAQ形式での情報整理を行い、AIによる出典採用の確率を高める取り組みが重要です。
ユーザー導線では「詳細情報はこちら」「比較表を見る」など、次のアクションを明確に示すことで誘導を図ります。
ブランド認知度の強化を並行して進めて、指名検索による直接訪問の増加を目指すことも有効です。
一般的なキーワードでの流入減少については、サイト内での滞在時間延長や回遊率向上によって補う戦略設計が重要でしょう。
情報元が確かではない可能性がある
AIによる要約は複数の出典を統合して作成されますが、情報の誤りや不正確さを完全に排除することはできません。
そのため、更新が遅れている情報や地域によって差異がある内容については、古い記述や間違った情報が表示されるリスクがあります。
情報を利用する側には、必ず出典リンクを確認し、一次情報で数値や日付の正確性を検証する姿勢が重要です。
情報を提供する側としては、記事の作成日時と根拠となるデータを明確に記載し、表やグラフには注釈をつけて誤解を防ぐ必要があります。
AIによる引用を意識した文章作成を心がけ、断定的な表現と適用条件を併記することで、誤読のリスクを軽減できるでしょう。
他の情報源との相違が発覚した場合は、速やかに訂正版を公開し、変更履歴を明確に記録として残すことが必要です。
また、記事の監修者や作成プロセスを明示すれば、読者が情報の信頼性を判断するための重要な材料となります。
やり取りの内容が一時的にサーバーに保存される可能性がある
AIモードでは、サービス品質の改善や不正利用の防止を目的として、ユーザーとのやり取り内容が一時的にサーバーに保存される可能性があります。
社内の機密情報や重要な業務情報を含む質問については、情報漏洩のリスクを考慮して細心の注意を払わなくてはいけません。
使用端末やユーザープロファイルを明確に分離し、業務利用と個人利用の境界を厳格に管理するようにしてください。
検索履歴やパーソナライズ設定を定期的に確認し、意図しない情報共有が発生しないよう注意深く管理すべきです。
データの保管期間や第三者への提供可能性については、サービスの公式利用規約やプライバシーポリシーで必ず確認しましょう。
組織内では情報の匿名化処理やマスキング処理を標準的な手順として確立し、機密情報の保護を徹底します。
質問内容を送信する前のチェックリストを作成・活用すれば、人的ミスによる情報漏洩リスクを最小限に抑えられるでしょう。
AIモードへの対応策
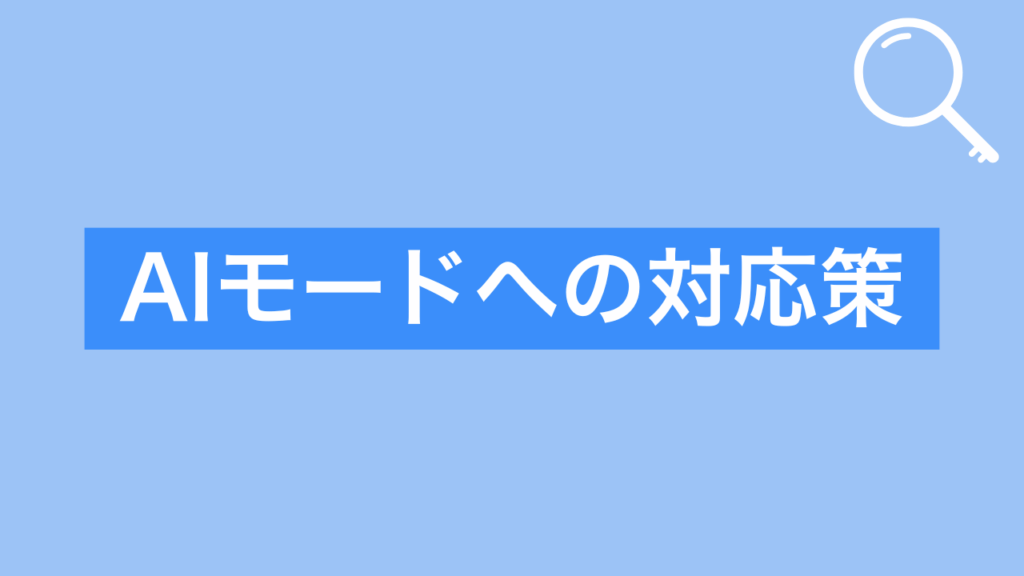
AIモードの要約に引用されるためには、論理的な文章構成や引用されやすい見出しの挿入など、さまざまな対策が考えられます。
ここで紹介する対策方法を理解し、実践しやすいものから取り入れてみてください。
表や箇条書きで要点を分かりやすく整理する
AIは情報を要約して簡潔に伝えようとするため、選ばれるには記事冒頭に簡潔な結論と箇条書きによる要点整理を配置することが効果的です。
比較表では違いが明確に分かる列幅の設定や分かりやすい表現を心がけ、不要な冗長表現は削除します。
表の項目名は簡潔に設定し、数値の単位や適用条件については各セル内で明確に記載してください。
企業名や商品名などの固有名詞は正式な表記を基本とし、一般的な略称がある場合は括弧内で併記します。
箇条書きは簡潔さを基本とし、各項目の表記形式を統一して読みやすさを向上させましょう。
図表の近くに内容の要旨を配置し、音声読み上げ機能を使用した場合でも内容が理解できるよう配慮するのがポイントです。
コンテンツには「結論→理由→根拠→次に取るべき行動」の順序で情報を構成すれば、ユーザーの迷いを最小限に抑えられるでしょう。
FAQ形式の見出しを積極的に採用する
ユーザーが実際に質問する表現に近い見出しを作成すれば、AIの回答に取り込まれる確率を高められるでしょう。
1つの質問に対して1つの明確な回答を用意し、適用される前提条件や除外される条件を簡潔に併記します。
似通った質問は統合して整理し、重複する回答を避けることで情報の密度と価値を維持可能です。
また、回答の冒頭では結論を明確に示し、その後に根拠となるデータや参照すべき詳細情報を続けて記載してください。
季節変動や年度更新がある情報については、最終更新日を明記することで古い情報による誤解を防止可能です。
顧客からの問い合わせ履歴が蓄積されていれば、分析してまだ対応できていない質問領域を積極的に補完します。
質問の重要度や頻度に基づいて表示順序を決定し、特に重要な項目については目次から直接アクセスできるよう設計するのもポイントです。
コンテンツ冒頭への要約ブロックと結論の記述を標準化する
すべての記事において冒頭に要約ブロックを設置し、読者が最初に結論を把握できるよう標準化しましょう。
要約は3行以内に収め、判断に必要な要素と情報の対象範囲を明確にします。
想定する読者像を明確に設定し、対象外の読者に対する適切な誘導先も併せて示せると理想的です。
本文の各見出しには、その章で何を説明するかの目的を記載し、読了後に得られる知識を明文化します。
結論部分では適用条件を明記した表現を使用し、どの読者でも同様の結果を再現できるように整理します。
記事更新の際は、要約部分だけを読んでも変更内容が分かるよう適切に書き換えを行ってください。
問い合わせや申し込みなどのコンバージョン導線は要約の直下に配置し、読者の行動を妨げない設計にしましょう。
構造化データマークアップを実装する
AIが理解しやすくするとの観点から、構造化データマークアップの実装も重要です。
FAQ、HowTo、製品情報などのトピックに対し、検索エンジンやAIが内容を正確に理解できるよう、専用のタグ(構造化データ)を追加します。
各タグに必要な情報はすべて入力し、日付や数値には単位も忘れずに記載してください。
AIが記事を参考にしやすくするため、記事を書いた人や監修した専門家の名前も適切にタグ付けします。
FAQページでは質問と回答の内容がきちんと対応するようにし、余計な装飾文字や表現は極力使わないようにします。
HowToトピックでは各ステップに番号を振って順番を明確にし、必要な道具や時間の目安も一緒に明示しましょう。
設定後の効果を測るために、どのページにタグが付いているかの確認とエラーの修正を定期的に行う姿勢も大切です。
本番のWebサイトに公開する前に、テスト環境で専用ツールを使って正しく設定されているかを必ず確認しましょう。
図表には代替テキストやキャプションの追加を徹底する
図表には代替テキストやキャプション(図表の説明文)を追加し、音声検索にも対応できるようにすべきです。
代替テキストでは、図表の重要なポイントと結論を簡潔な文章で説明します。
キャプションにはデータの出典や集計方法などを明確に記載し、他の人でも同じ結果を再現できるようにします。
画像ファイルの名前は内容が分かる単語で構成し、記号や数字だけの名前は避けたほうがよいでしょう。
比較を示すグラフでは、縦軸・横軸の意味と単位を明記して、読み間違いを防いでください。
画面のスクリーンショットでは個人情報や機密情報をマスキングし、撮影日を記録して管理すべきです。
色で情報を区別する場合は濃淡をはっきりさせ、凡例(色の説明)も文字で併記します。
図表を更新する際は版数を付けて管理したうえで、古いバージョンが埋め込まれたページを新しいものに更新しましょう。
AIモードに関してよくある質問(FAQ)
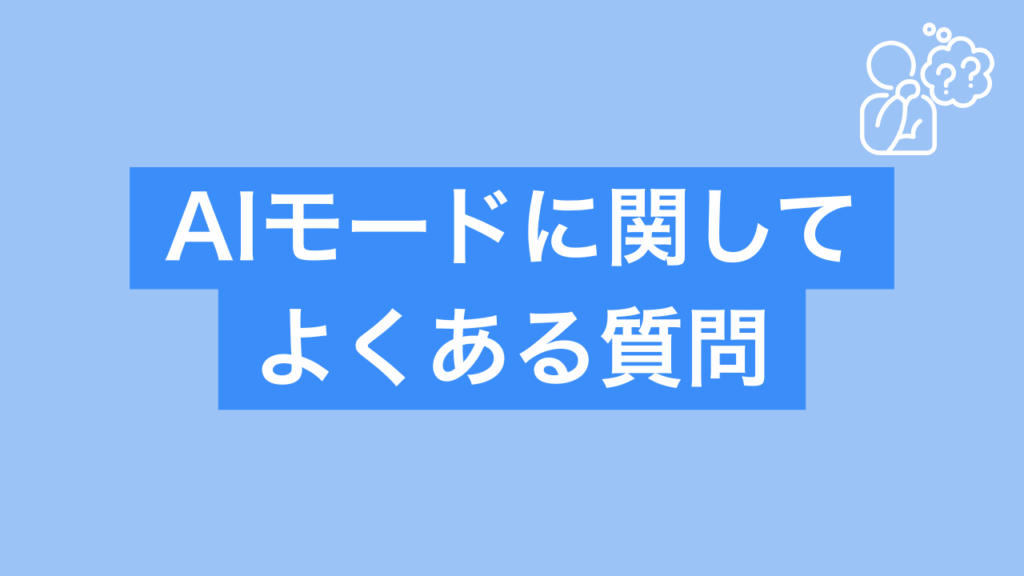
ここでは、AIモードについて多く寄せられる疑問をまとめました。
提供時期や費用、設定方法、従来検索の扱いを順に解説するので、今後の利用に役立てましょう。
ただし、名称や表示は随時更新されるため、詳細はGoogleの公式ページを確認するようにしてください。
AIモードはいつから日本で使える?
日本では2025年9月以降に順次導入が開始され、利用できるユーザーが段階的に拡大されました。
すべてのユーザーに一斉に提供されるのではなく、アカウントや使用端末ごとに段階的に利用可能になると思われます。
Googleの検索画面にAIモードのタブや回答カードが表示されるようになれば、その時点で利用可能です。
まだ表示されない場合は、ブラウザの言語設定を日本語にして、一度ログアウト後に再ログインしてみてください。
ブラウザの更新やキャッシュ(一時保存データ)の削除により、表示されるようになる可能性もあります。
企業で利用可否の検証を行う場合は、異なるOS(Windows、Mac等)や回線(社内、モバイル等)での表示差異を記録すると効率的です。
同じ検索キーワードを試してみて、情報源の表示順序や回答の詳しさをスクリーンショットで保存しておきましょう。
月に1回程度、検索結果での自社コンテンツの露出状況を確認し、影響の変化を把握することをおすすめします。
料金や利用条件は?無料で使える?
検索時に表示されるAIモードは基本機能の一部として提供されており、追加料金は原則として発生しません。
ただし、一部の高度な機能や外部サービスとの連携については、別途利用規約への同意や設定が必要になる可能性があります。
また、アカウントの年齢制限や居住地域の設定によって、AIモードが表示されない可能性も考えられるでしょう。
会社の端末を使用している場合は、管理者の設定によってAI機能が制限されていないか確認してみてください。
音声入力やカメラ撮影機能を使用する際は、事前に端末のマイクやカメラの使用許可を確認しましょう。
AIモードの使用により通信量が増加する可能性も否定できないため、携帯回線では使い過ぎに注意が必要です。
企業で利用する場合は、社内規定に従ってデータの取り扱い方法と記録保管の条件を明確にしておくことをおすすめします。
新しい機能が追加された際は、どこまで無料で使えるかと利用規約の変更内容をその都度確認しましょう。
AIをオンにする/オフにする具体的な手順は?
検索画面の「Search Labs」アイコンをクリックし、「AIを使った機能」の該当するスイッチでオン・オフを切り替えます。
設定変更後はページを再読み込みして、表示が正しく切り替わったかを確認してみてください。
検証目的で使う場合は、複数のユーザープロファイルを使い分けることで、設定の影響の混在を防げます。
スマートフォンでは、Googleアプリ内の設定メニューから同様の操作が可能です。
音声入力や画像撮影の機能については、端末側でも個別にオン・オフの設定を行いましょう。
複数人で使用する共有端末では、初期設定をオフにしておき、意図しない情報保存を防止することをおすすめします。
設定変更の記録を残しておくことで、後から同じ条件で検証できるようになります。
動作が不安定な場合は、ブラウザの更新、キャッシュ削除、ログアウト後の再ログインなどを試してください。
従来の検索結果は完全になくなるの?
従来の青いリンクがある検索結果は引き続き表示され、AI回答が画面上部に追加される形で併用されます。
AIの要約だけで疑問が解決する質問では、元のサイトへのクリック数が減る可能性がある点に留意が必要です。
一方で、AI回答に含まれる出典リンクから元サイトを訪問するユーザーが増えるケースも考えられます。
また、検索キーワードの種類によって、AI回答が表示される頻度や影響の大きさは大きく異なります。
コンテンツ制作において、要約に適した冒頭文や比較表を整備することで、AIの参考情報として選ばれることを目指しましょう。
一般的なキーワードからの流入減少は、サイト内での滞在時間延長や関連ページ閲覧の促進で補うことも検討してください。
月に1回程度、検索結果画面のスクリーンショットを保存し、表示内容の変化を記録しておくと、AIモード対策の効果を検証できます。
広告とブランド認知向上の取り組みを連携させ、幅広い接点でユーザーとの関係を強化しましょう。
まとめ
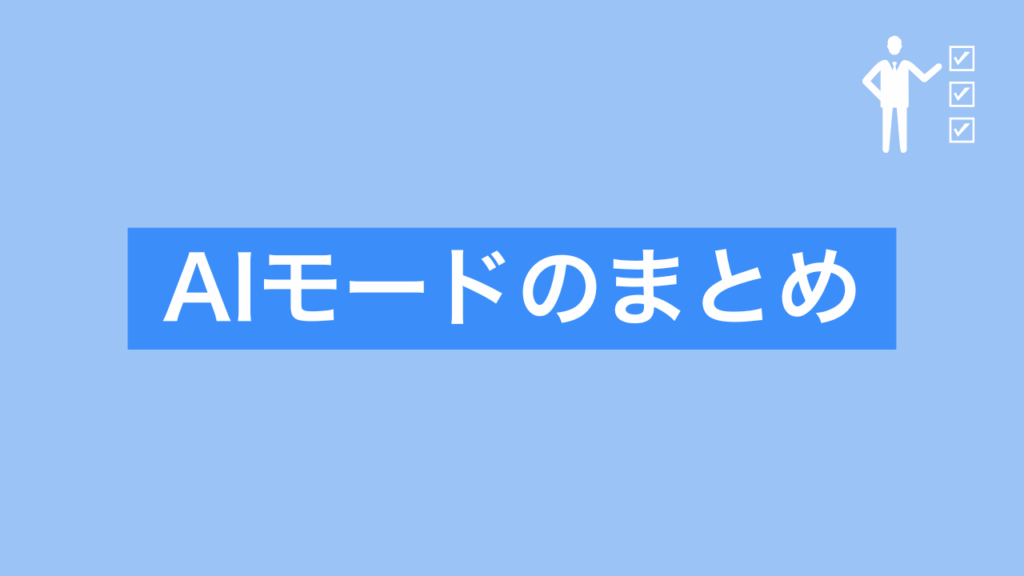
AIモードとはGoogle検索にAIが統合された新機能であり、従来のリンク一覧形式ではなく要約された回答カードを表示してユーザーの疑問を解消します。
2025年9月から日本でも段階的に提供開始され、音声や画像での検索、対話形式での深掘り質問が可能になりました。
ユーザーにとっては検索効率が向上する一方、サイト運営者にとってはゼロクリック増加や情報の正確性確保などの課題があります。
対策として、FAQ形式の見出し採用、冒頭要約の標準化、構造化データの実装などが重要です。
AIモードを導入しても従来の検索結果は並行表示されますが、今後はブランド認知度向上がより重要になるでしょう。AIモードへの対応を含め、生成AI時代の検索対策全般について詳しく知りたい方は「LLMOとは?生成AI時代の検索対策やSEOとの違い、具体的な導入方法について解説」もあわせてご覧ください。
「LLMOに取り組みたいが、何から始めればいいかわからない」
「自社サイトがAI検索でどう扱われているか知りたい」
TRILIA株式会社では、SEO・LLMO領域の専門知見と独自のAI分析基盤を活かし、完全成果報酬型のマーケティング支援を提供しています。初期費用0円で、まずは現状の課題整理からお手伝いいたします。