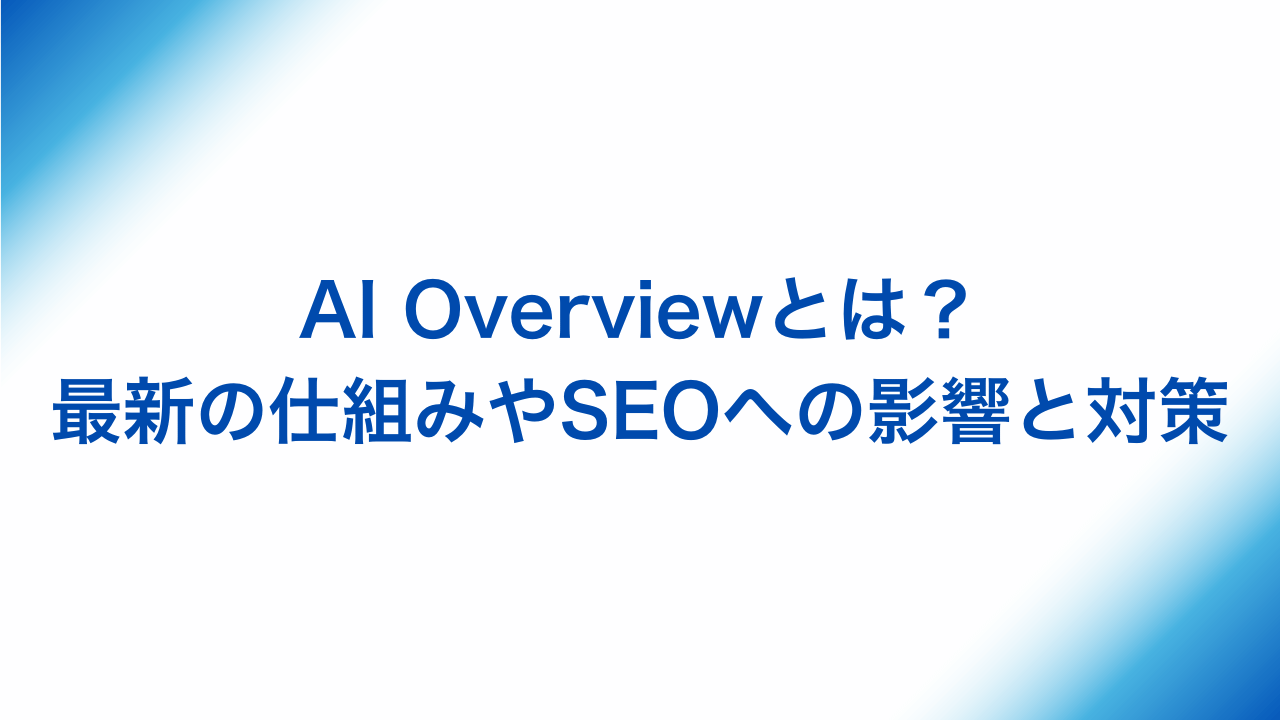検索結果の冒頭に生成AIが要点をまとめて提示するAI Overview。
質問の意図をくみ取り、複数ソースを横断して要約し、次に取る行動のヒントまで示すため、従来の検索体験から大きく変わりつつあります。
- AI Overviewとは何か知りたい
- AI Overviewの特徴や仕組み、従来の検索結果との違いを知りたい
- AI Overview対策のポイントや注意点を把握したい
この記事では、そんなあなたに「AI Overviewの概要やコンテンツ制作者がAI Overview対策をするうえでのポイント」などについて解説します。
AI Overviewとは検索クエリに対してAIが関連情報を表示する機能
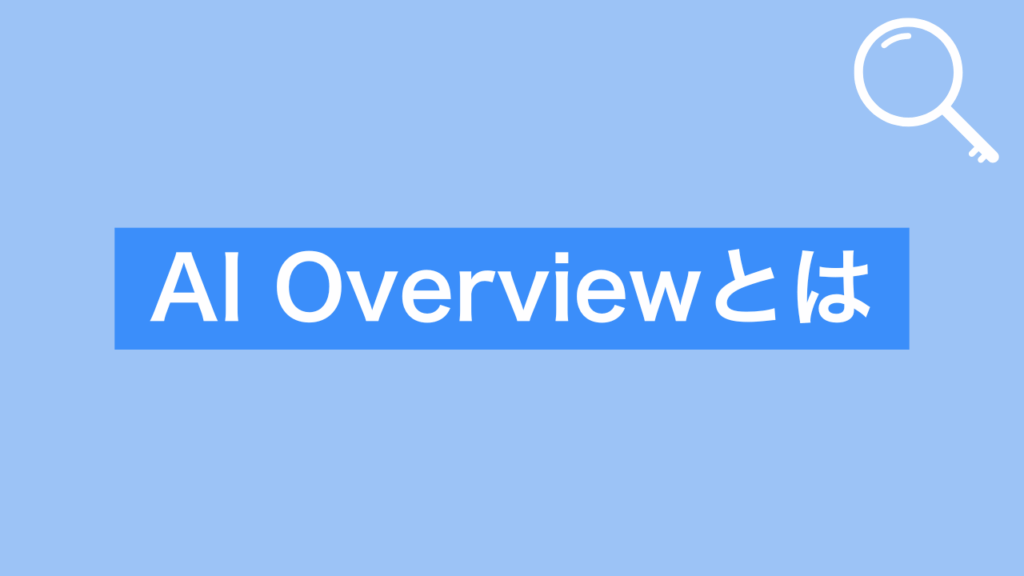
AI Overviewとは、検索語句に対する要約をAIによって自動生成し、検索欄の上部に表示するGoogle検索の新機能です。
これまでは「SGE(Search Generative Experience)」として試験提供されていましたが、今回正式に提供されるにあたって「AI Overview」と名付けられました。
AI Overviewは、Googleの生成AI「Gemini」を使用し、ユーザーの質問や課題に対して関連情報を掘り下げて回答を出力します。
出典へのリンクも併記されるので、関心ごとに対する追加調査をしやすい点が魅力です。
質問形式や問題解決型のクエリが表示されやすい傾向
AI Overviewは、すべての検索結果に対して表示されるわけではありません。
質問形式のクエリや「〇〇のやり方」「〇〇と△△の違い」などの問題解決型のクエリに対して、表示されやすくなっています。
また、複数の情報源から情報収集しなくてはならないようなクエリに対しても、AI Overviewが表示される可能性が高いでしょう。
一方で、単語の意味確認や特定の固有名詞だけの検索など目的が明確で要約の必要がない場合は、AI Overviewは出にくい傾向があります。
検索意図があいまいな場合は、追加入力で検索意図をAIが把握できた場合に表示されます。
Google検索の結果から、チャット形式のインターフェース「AI Mode」も利用可
Googleの検索結果表示画面からは、チャット形式のインターフェース「AI Mode」も利用可能です。
AI Modeはチャット形式のAIサポートサービス(詳しくは「AIモードとは?」を参照)であり、従来の検索型とは異なり対話形式で続けて質問を投げかけられます。
会話の文脈を理解して回答を生成するため、会話の流れからの深掘りが可能です。
AI Modeは、日本国内では2025年9月9日より、一部ユーザーに対して提供が開始されています。
AI Overviewの仕組み
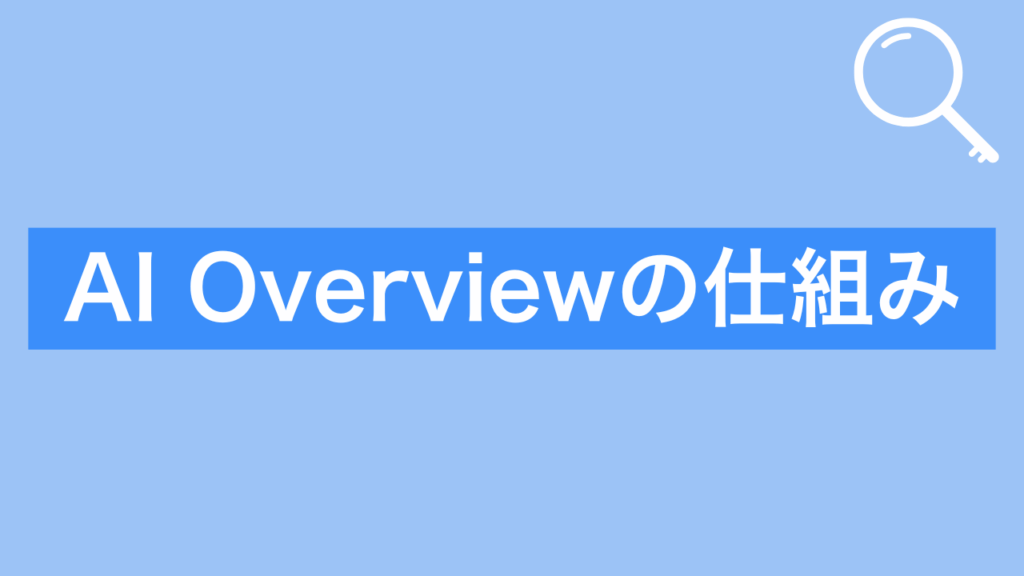
AI Overviewは検索意図に合った関連情報を収集し、要約してユーザーに提供します。
Web上の信頼できるページから要点を収集し、生成AIを使って文章を作成します。
また、人物や組織などの固有情報は、ナレッジグラフで補強可能です。
最後に根拠として出典リンクを提示し、ユーザーがさらに調査しやすくしてくれる点も特徴的だと言えます。
検索クエリに対するWebサイトでの情報収集
AI Overviewはユーザーが入力したクエリの意図を推定し、関連度と網羅性の軸で情報収集を行います。
信頼性や権威性が高い情報を優先するため、ニュースや公式ドキュメント、専門サイトなどが選ばれやすいでしょう。
情報収集する中で重複している内容はまとめて、矛盾する情報は信頼度を再評価します。
Webサイトの日付や更新履歴も確認し、新しい情報を選択する点も特徴的です。
また、地域や言語の条件があれば従って情報収集を行います。
収集した情報による生成AIでの文章作成
AI Overviewが抽出した情報は項目ごとに整理され、生成AI「Gemini」を使用して文章に起こします。
生成AIは質問の型に合わせて、結論から先に書き出すことが一般的です。
手順や比較は箇条書きも活用して簡潔化し、過度な推測を抑えるようにします。
数値や固有名詞は原文と照合し、表記ゆれを整えることも可能です。
また、不確実な点は断定を避け、確認を促す表現を用います。
Googleの「ナレッジグラフ」との連携
特に信頼性が求められる分野の返答においては、Googleが蓄積してきたデータベースである「ナレッジグラフ」と連携します。
ナレッジグラフとは、Googleが持つ人物や場所、製品などの情報をまとめたデータベースのことです。
企業名や人物名などの情報については、ナレッジグラフと連携して情報提供を行います。
ナレッジグラフとの連携により、別名や表記違いも同一の実体にひもづけて処理可能です。
コンテンツをAI Overviewに表示させるためには、ナレッジグラフに掲載されるように自社名やブランド名に関する情報発信を行うことも大切でしょう。
出典リンクの表示
AI Overviewは生成結果に対して根拠ページのリンクを並べ、ユーザーの検証を可能にします。
重要な主張には複数の出典を添えることで、情報の偏りを抑えます。
リンクは見出しや要点の近くに配置されているため、遷移が容易に可能です。
掲載順は、関連度や新しさが基準になりやすいとされています。
ユーザーは出典を比較し、自分の判断で深掘り可能です。
誤りがあれば出典を差し替えることで、AI Overviewの精度の改善につなげます。
AI OverviewとSGE・従来SERPの違い
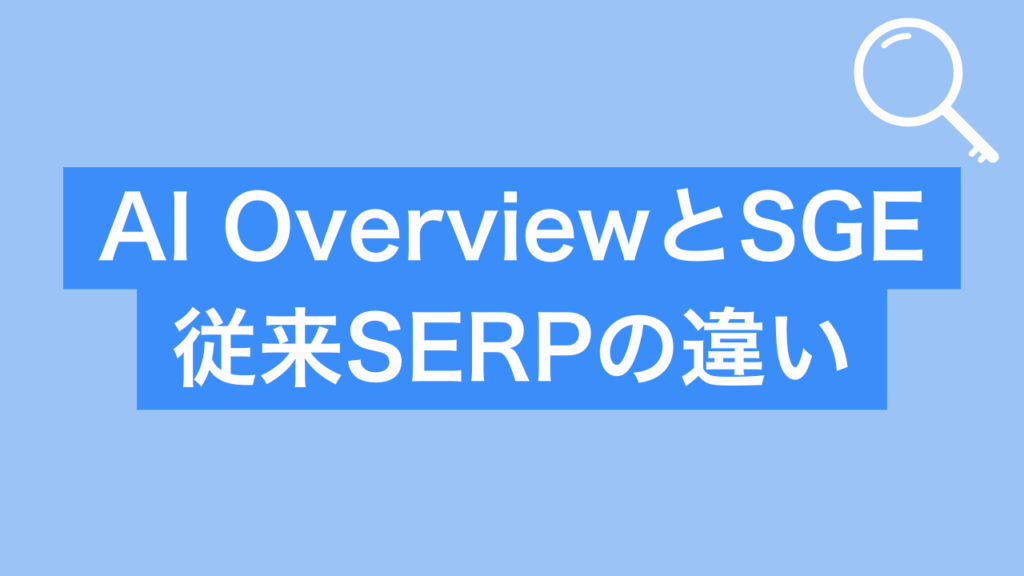
AI OverviewとSGE・従来SERPは見え方や役割が異なり、結果としてクリック動線にも差が出ます。
AI Overviewは要約を前面に出し、その後のさらなる情報収集へ誘導します。
SGEは実験色が強く、提示形式や条件の影響を受けやすい点が特徴的でした。
従来SERPとは、AI Overviewが登場する前の検索結果ページのことです。
各サイトのタイトルが青いリンクになって並んでおり、個別ページの比較がしやすいといえます。
表示位置と画面占有率の違い
AI Overviewは検索結果の上部に現れますが、最初の段階では折りたたみ表示されています。
展開すると縦方向の占有が増え、内容を詳細にチェック可能です。
要約が短い場合は省スペースで、下に表示される通常結果も同時に見られます。
AI Overviewのテスト版として提供されていたSGEは生成領域が大きく、初回表示でスクロール量が増えやすい印象でした。
また、従来SERPは各結果が均等に並び、検索結果の個別比較に向いた配列です。
出典表示・リンク導線・追従QAの挙動
AI Overviewは要約の直下に出典リンクが並び、クリックすれば根拠サイトへすぐ遷移できます。
リンクボタンが分かりやすく、クリック導線は明確です。
また、検索結果には提案質問も表示され、選ぶと前文脈を引き継いでさらにQAが増えていきます。
SGEも出典を示しますが、表現や並び順が時期によって変化する仕様です。
従来SERPはスニペット単位での出所が明確で、サイトによる違いは一目で簡単に確認できます。
AI Overviewの提供状況(2026年時点)

2026年現在、AI Overviewは広範囲に展開され、世界中の多くの地域で標準表示が進んでいます。
日本でも対応が進み、現在では質問や手順などの一部クエリで要約が自動表示されます。
ただし、表示有無はテーマや意図で変化し、常に同条件で出るわけではありません。
日本ではAI Overviewsがデフォルト設定になっている
2025年に入り、日本国内でも通常の検索でAI Overviewが自動表示されるようになりました。
特に質問型や手順型のクエリで、AI Overviewによる要約と出典が先頭に現れやすい傾向があります。
サインイン有無に関わらず表示される例が増えており、ユーザーの検索負荷軽減に役立っています。
一方で、ニュースや地震速報など速報性が求められる領域の場合、AI Overviewsは出にくい傾向があります。
また、同じ語句でも地域や端末条件で出方が変わる点に注意が必要です。
世界でもAI Overviewは続々と展開されている
AI Overviewは対象国と言語を段階的に拡大し、現在でも対応範囲が増え続けています。
英語圏に限らず多言語で提供が進み、利用者の裾野が広がっている状況です。
ただし、依然として地域によって提供有無が異なるので、海外向けサイトを運営する場合は、主要市場ごとに確認する必要があります。
国別に端末と言語を固定し、同一クエリで出方を比較してみるとよいでしょう。
AI Overviewを設定する手順
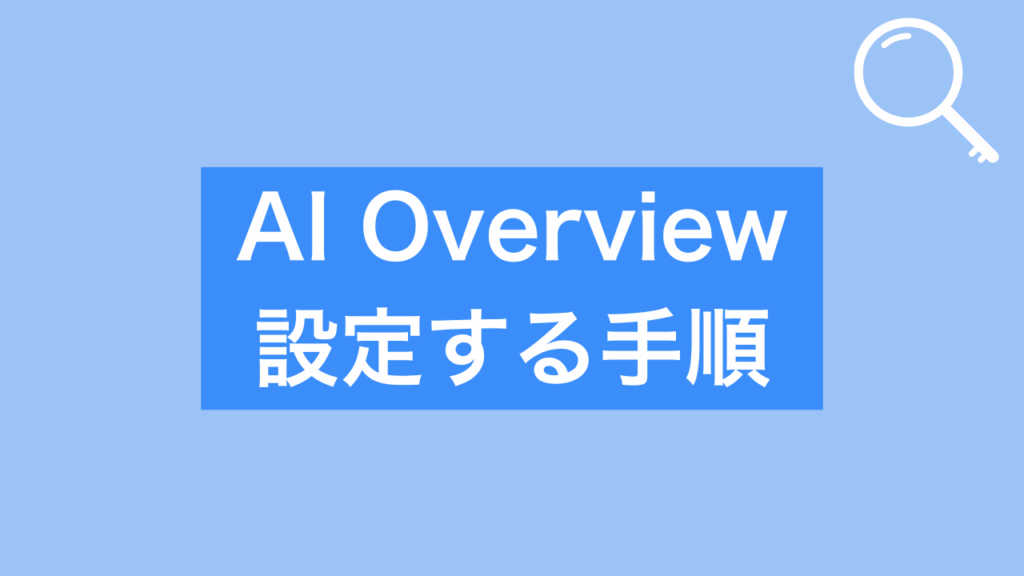
2026年現在、日本ではAI Overviewsがデフォルトで有効になっているため、通常は特別な設定は不要です。表示されない場合や、手動で設定を確認したい場合は以下の手順を参照してください。
基本的には、Search Labsの有効化可否を確認して設定するのみで簡単に利用可能です。
ただし、同じ操作でも端末やアプリの違いで方法に若干の違いが出る可能性はあります。
検証はサインイン状態や言語設定を固定して行います。
設定してもAI Overviewが出ない場合は、時間帯やネットワークを変えて確認してみるとよいでしょう。
パソコンの場合はSearch Labsにアクセスして有効化
パソコンの場合、まずGoogle Chromeにサインインし、検索ページを開きましょう。
画面右上のフラスコアイコンまたはメニューから、「Search Labs」へ進めます。
Search Labsを開いたら、「AIによる概要など」の「オンにする」を選択して有効化してください。
スマートフォンの場合もパソコンと基本的な流れは同様
スマートフォンの場合も、基本的な流れはパソコンのときと同様です。
GoogleアプリまたはChromeを起動してサインインします。
「ホーム」タブからフラスコのアイコンをタップし、「Search Labs」のページへアクセスしてください。
以降の流れは、パソコンのときと同様です。
「AIによる概要など」の「オンにする」を選択して、AI Overviewsを有効化します。
AI OverviewのSEOへの影響

AI Overviewが常時表示されるようになり、検索結果の見え方が変化しました。
要約が解決策を先に提示するため、ユーザーの検索体験がこれまでと変化します。
従来型のSEO施策による検索結果の上位表示だけではアクセス流入数の確保が難しくなり、いかにしてAI Overviewに取り上げられるかが重要になります。
また、AI Overviewが要約に採用しやすい、対話継続型のコンテンツが評価されやすくなる点も重要でしょう。
ゼロクリック検索が増える
AI Overviewの要約内で検索意図を満たせるようになれば、検索結果をクリックせずに離脱するユーザーの増加が見込まれます。
特に、「How to(〇〇の使い方)」や手順の説明などは、AI Overviewが表示されやすい領域です。
一方で、AI Overviewの要約のみでは根拠や比較が不十分になりやすく、深掘りに対する需要は残ると考えられます。
AI Overview時代に必要とされるコンテンツになるには、クオリティを高めて要約では拾いきれない内容を掲載する必要があるでしょう。
リスティング広告のクリック数が減る可能性がある
AI Overviewによる要約がファーストビューを広く占有すれば、リスティング広告のクリック数が減る可能性があります。
広告枠の視認率が下がり、クリック率が低下しやすくなる可能性があるでしょう。
リスティング広告を利用している場合、クリック単価の高騰に注意が必要です。
特に、いわゆる「Knowクエリ」と呼ばれる情報収集の検索意図に関しては、要約で疑問が解消される場面が増えると予想されます。
広告主は、「Buyクエリ」や「Doクエリ」に対する広告出稿を重視し、出稿費用が無駄になりにくいようにしなくてはいけません。
ユーザーファーストの対話型コンテンツが評価されやすくなる
AI Overviewの登場により、ユーザーファーストの対話型コンテンツが評価されやすくなるとも考えられます。
対話型のコンテンツはユーザーの悩みや質問に対して自然な形式で解答でき、AIの要約に採用されやすいためです。
コンテンツには「HowTo」系の見出しや「FAQ」見出しを積極的に取り入れ、比較表をひと目で理解できる並びに整えておくとよいでしょう。
また、根拠となる出典のリンクも忘れずに掲載することで、信頼性が高まります。
対話の続きを想定し、代替案や例外パターンにも備えておくとなお良いでしょう。
AI Overviewsに参照されるためのポイント
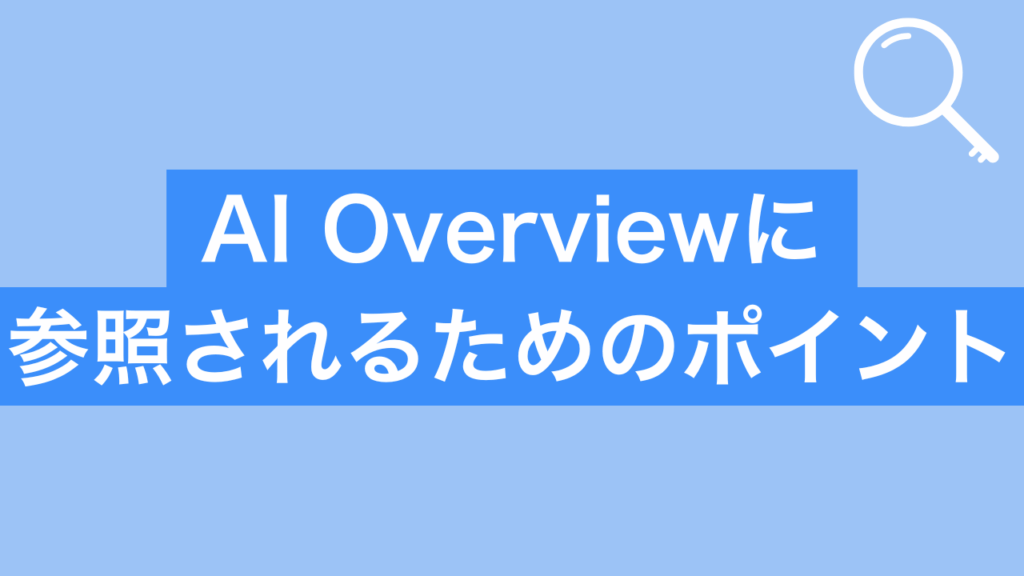
AI Overviewsの要約に採用されるためには、要点の明確さと根拠の提示が重要です。
冒頭で結論と数行の箇条書きを示し、裏づけへ誘導する設計が求められます。
また、手順や質問に強い見出しを積極的に盛り込み、読み手の迷いを減らす工夫も重要です。
さらに、著者や一次データの開示、比較表や深掘り解説の導入、構造化データの設定なども重要なポイントだといえます。
「要点+根拠リンク」を冒頭標準ブロック化する
AI Overviews対策として、コンテンツの最上部に全体の要点と根拠リンクのセットを固定で置きましょう。
要点は各30〜60字ずつの箇条書きで、結論と条件を短く示します。
根拠には一次情報や公式資料をできる限り採用し、権威性や信頼性を高める意識も大切です。
文章は「結論→理由→詳細」の順にすると、論理的でAIから高評価を得やすいでしょう。
コンテンツ冒頭に設置するブロックとして一定の型を作ってフォーマットにしておくと、全記事に展開しやすいです。
「HowTo」「FAQ」「強み・弱み」を積極的に盛り込む
コンテンツには、「HowTo(やり方や手順)」「FAQ(よくある質問)」「強み・弱み」の内容を積極的に盛り込みましょう。
これらのトピックは、AIの要約に採用されやすい傾向があります。
手順は番号付きの箇条書きにし、各手順の目的を簡潔に示してください。
手順の要所には画像や図解を入れ、一目でわかりやすくする工夫も効果的です。
FAQは質問文を自然文で書き、回答は結論から始めます。
強み・弱みは同じ評価軸で並べ、比較における注意があれば添えましょう。
著者情報・一次データ・実際の写真でE-E-A-Tを重視する
コンテンツには、著者の情報や一次データなどを掲載することで、E-E-A-Tを重視した高品質な内容に仕上がります。
著者情報には、専門領域や実務経験などを短く示し、専門性の高さをアピールしてください。
外部監修がある場合は、役割と確認範囲をできる限り記載します。
一次データは、公的機関や業界団体など、信頼性の高い参考元から入手するようにしましょう。
一次データとして、体験談やレビューを取り入れることで独自性が高まりますが、体験談は主観と事実を分けて記載してください。
また、手順の説明やレビューなどのトピックには、実際の写真を撮影日や場所と一緒に添えることで、独自性や信頼性を高められるでしょう。
比較表・深掘り解説で「クリックする理由」を設計する
比較表を入れると、情報が整理されて見やすいためにAIからの評価が高まります。
比較表は評価軸を3〜7項目に絞り、単位と条件をそろえて記載してください。
表下に根拠リンクをまとめ、裏取りがしやすい導線にします。
そして、要約だけでは伝わらない裏づけ情報は、本文で深掘り説明を加えましょう。
「要約だけでなくリンク先も確認しておきたい」と思えるコンテンツを作ることが、AI Overviews対策においては重要です。
構造化データを設定する
「AIが理解しやすいコンテンツにする」との観点では、構造化データの設定も重要です。
構造化データとは、コンピューターがページ内の情報を理解しやすくなるデータ形式のことです。
コンテンツごとに構造化データを設定しておくことで、AIによる情報理解の精度が高まります。
構造化データは、JSON-LD形式でHTMLのhead内やbody内に記述するのが一般的です。FAQPage、HowTo、Article、Productなどのスキーマタイプがあり、Google公式の構造化データテストツール(リッチリザルトテスト)やSearch Consoleのリッチリザルトレポートで正常に認識されているか確認できます。
AI Overviews対策のサンプル原稿作成
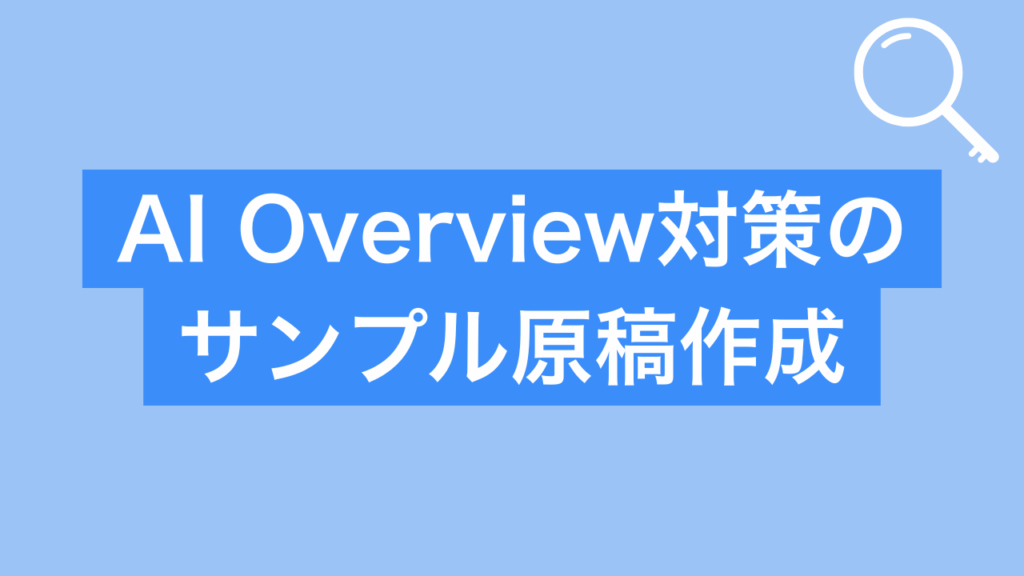
本章では、AI Overviewsの要約に採用されやすい原稿の具体例を紹介します。
NG例も併記して避けるべき書き方を紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
冒頭ブロックの型は「要点→根拠→詳細」
AI Overviewsに採用されやすい記事の冒頭は、要点→根拠→詳細の順序で情報を整理することが重要です。
以下に具体例をご紹介します。
【要点】DX推進における最大の課題は技術導入ではなく、従業員の意識変革とデジタルスキル不足です。
【根拠】経済産業省の調査では、DX推進の阻害要因として「人材不足」を挙げる企業が〇〇%、「従業員の理解不足」が〇〇%となっており、技術的課題(〇〇%)を大きく上回っています。
【詳細】成功するDX推進には、まず経営層のコミットメントと全社的なビジョン共有が必要です。ここでは、DXの具体的なステップとしてデジタルリテラシー研修の実施、段階的なツール導入、成功事例の社内共有などを紹介します。
上記の例文の前にコンテンツ全体の要点を3つ程度箇条書きで並べ、書き出し文を記載します。
要点は結論を簡潔に1文で記述し、根拠には一次情報や公式資料を盛り込むと信頼性が増します。
文体は基本的に断定で統一し、曖昧な推測は注意書きを添えて解説しましょう。
同じ型を全記事で統一すれば、AIによる引用を受けやすくなります。
How to記事の再構成例とNGパターン
How to記事の構成は、「目的→準備→手順→確認→補足」の順になるよう既存記事を再構成しましょう。
たとえば、「WordPressサイトのSSL化」についてHow to記事を作成する場合、以下の流れをおすすめします。
- 目的:何を達成するのか明確化(「WordPressサイトのSSL化で安全性向上」)
- 準備:必要な環境の整理(レンタルサーバー管理画面へのアクセス権限など)
- 手順:具体的なステップを番号付きで記載
- 確認:完了の判断基準提示(「ブラウザのアドレスバーに鍵マーク表示」)
- 補足:注意点やトラブル対処法を追記
各手順の先頭に目的を書くと、読み手が迷いません。
手順は番号付きの箇条書きで示し、この場合は完了条件や所要時間などを添えられると親切です。
必要に応じて、工程ごとに画像を添付するとユーザーが理解する際の助けになります。
注意点としてよくある失敗のパターンを盛り込むと、手順の再現性が高まるでしょう。
補足には、例外パターンの処理方法や失敗時のリカバー方法などを盛り込みます。
NGパターンとしては、上記の5要素のうちで特に目的や手順が欠けているケースが考えられます。
比較記事の表設計と出典明示のコツ
比較記事に掲載する表の評価項目は3〜7つ程度に絞り、内容を把握しやすくしましょう。
たとえば、以下のように記載します。
| 項目 | サービスA | サービスB | サービスC |
|---|---|---|---|
| 月額料金 | 1,000円 | 1,500円 | 800円 |
| 機能数 | 15個 | 25個 | 10個 |
| サポート体制 | 24時間対応 | 平日のみ | メールのみ |
| おすすめ度 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
表の下には、出典のリンクを記載してください。
差が出る項目がある場合は、色で目立たせるのではなく注釈をつけて、理由を説明します。
AI Overviewに関してよくある質問
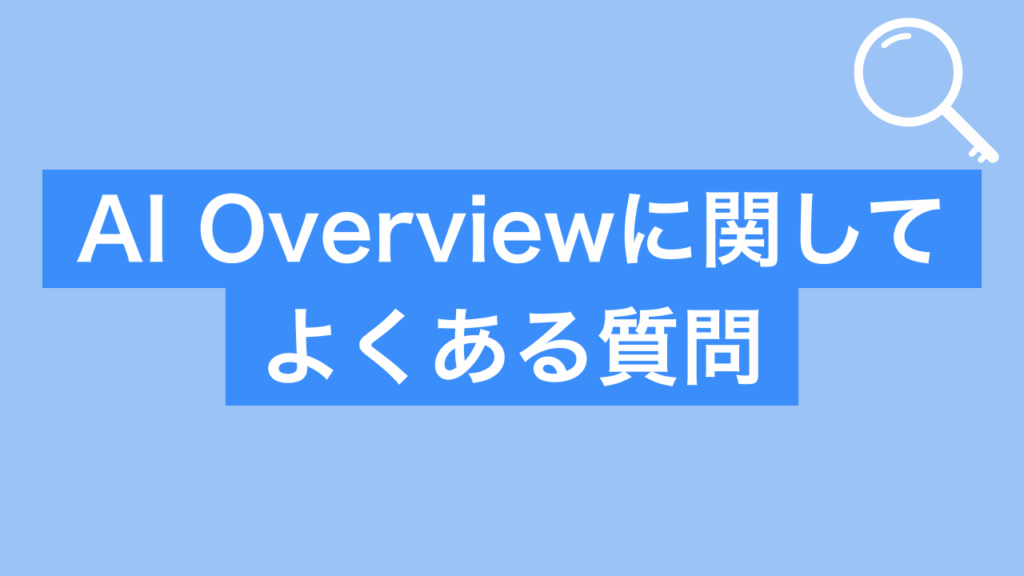
ここでは、AI Overviewに関してよくある質問に対して、実装と運用の観点から回答を紹介します。
多くの方が間違えたり気になったりするポイントなため、チェックしてみてください。
AI Overviewが表示されないときの主因と対処方法は?
AI Overviewが表示されない主な原因は、地域・言語設定の不一致やGoogleアカウントの設定、検索クエリの特性などだと考えられます。
まずGoogleアカウントでサインインした状態を維持し、Search Labsで設定を確認してみてください。
検索言語と地域設定を明確にし、端末の位置情報設定も合わせることが重要です。
検索キーワードは質問形式(「〇〇とは何ですか?」)や手順を求める形式(「〇〇のやり方」)に変更し、検索意図を明確に示すようにしましょう。
また、特定のクエリに関してはAI Overviewの表示が控えめになる傾向があるため、表示されない場合は、異なる分野のキーワードで検証してみてください。
無料で使える範囲とデータの扱いは?
Google検索でのAI Overview要約表示と出典リンクの参照は無料で利用できます。
要約の閲覧や関連質問の選択も、通常の検索利用に含まれています。
検索履歴やアカウント活動は、Googleのサービス品質向上のために活用される場合があります。
そのため企業での利用時は、社内規定に応じて業務端末での検索方針を明確にしておくことが重要です。
もし検索履歴の共有が問題となる部署では、専用のアカウントを別途作成して利用することをおすすめします。
画面キャプチャを保存する際は、個人情報や機密情報が含まれないよう適切にマスキング処理を行ってください。
誤回答への向き合い方とリスク低減方法を教えてほしい
AI Overviewの誤回答は、出典情報の偏りや曖昧な前提条件によって発生しやすくなります。
これらのリスクは適切な運用方法で大幅に抑制可能です。
コンテンツでは一次データや実際の利用写真などを積極的に取り入れ、情報の再現条件を明確に記載してください。
要点をコンテンツの冒頭に配置すれば、AIによる引用時の誤解を減らすことができます。
FAQでは例外的なケースを先に説明し、断定的すぎない表現を心がけましょう。
「一般的には」「多くの場合」といった表現を使うことで、誤った断定を避けられます。
情報の検証時には必ず複数名でクロスチェックし、誤りを発見した際の報告窓口を明確にしておきます。
特に健康や金融などの重要分野では、公開前に専門監修者による確認プロセスを必須としておきましょう。
まとめ
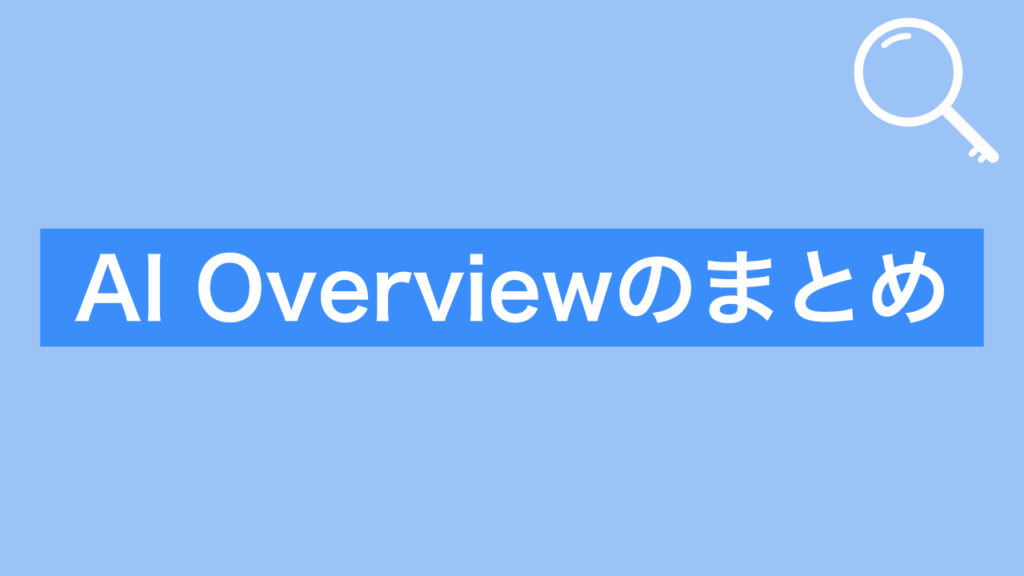
AI OverviewはAIを使用した検索機能であり、検索クエリに対する要約を自動生成し、検索結果の上部に表示します。
質問形式や手順型のクエリで表示されやすく、複数の信頼できる情報源から収集した情報をもとに文章を作成し、出典リンクも併記されます。
2026年現在、日本でもデフォルト設定となっており、従来のSEO施策だけでなく、AI Overviewに採用されるための対策が重要になっています。
要点を冒頭に配置し、構造化データの設定や比較表の活用など積極的に行い、AI Overviewからの引用を獲得しましょう。AI Overviewの略称である「AIO」の概要や、生成AI時代の検索対策全般については「LLMOとは?」の記事もあわせてご覧ください。
「LLMOに取り組みたいが、何から始めればいいかわからない」
「自社サイトがAI検索でどう扱われているか知りたい」
TRILIA株式会社では、SEO・LLMO領域の専門知見と独自のAI分析基盤を活かし、完全成果報酬型のマーケティング支援を提供しています。初期費用0円で、まずは現状の課題整理からお手伝いいたします。