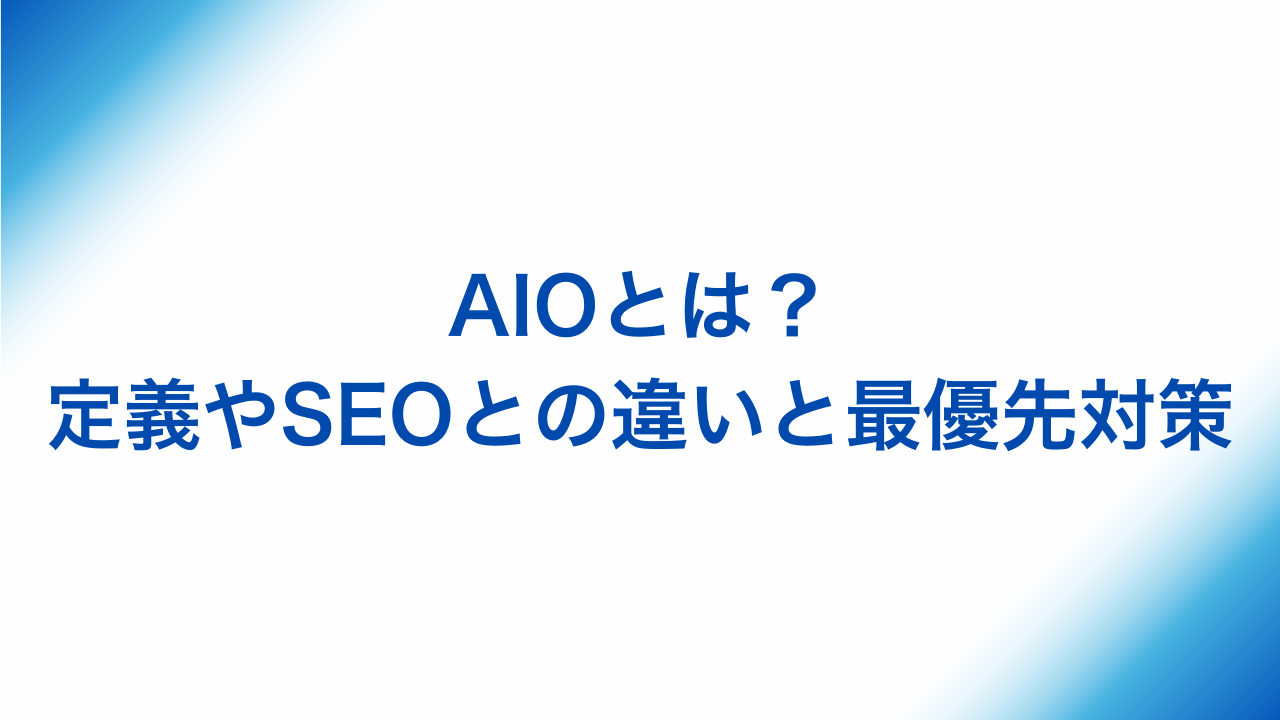- 「AIOとは何か、SEOとの違いを知りたい」
- 「AIOを実施するうえでのポイントを知りたい」
- 「AIO対策をとるメリットやデメリットを把握したい」
AIが発達してきて、今までSEO対策をしてきた担当者はこのように考えているでしょう。
この記事では、「AIOの概要や実施するうえでのポイント、AIO導入の成功パターン」などについて解説します。
AIOとは

- AI回答によって自社サイトが「引用・参照・要約源」になる
- AIOではコンテンツの質がより大切になっていく
- 技術に焦点が当たった「LLMO」もAIOとほぼ同義
AIOは、AI検索エンジンに選ばれ引用されるためにコンテンツを最適化させる施策です。
近年では検索エンジンが進化し、検索結果をAIが要約・生成する機能が誕生しました。
AIは、検索結果に出てきたコンテンツの文脈を読み取って情報を要約します。
そのため、従来のSEOにおける順位対策と比較してAIOではコンテンツの質が重要になるといえるでしょう。
また、FAQや根拠、図表などを積極的に取り入れて、AIが読み取りやすいコンテンツにすることも大切です。
AI回答によって自社サイトが「引用・参照・要約源」になる
AIOは、生成AIが情報提供のために引用する記事として、自社コンテンツを選ばせるための手法です。
生成AIは、検索結果の中から信頼性や権威性が高いと考えられるコンテンツを見つけ出して引用します。
ユーザーはAIの回答のみから情報収集を行い、従来の検索結果をチェックしない可能性もあるでしょう。
そのため、AIOを意識してAIに選ばれるコンテンツを作成することが重要です。
AIOではコンテンツの質がより大切になっていく
AIは、検索結果に出てきた多数のページから重要と思われる情報を抽出・要約してユーザーへ提供します。
ユーザーにとって重要性が低いコンテンツはAIより引用されず、ユーザーの目に触れる機会を失ってしまうでしょう。
AIに選ばれてユーザーの目に触れるコンテンツを生み出すためには、記事の品質を高めていく意識が重要です。
技術に焦点が当たった「LLMO」もAIOとほぼ同義
AIOは、「LLMO(Large Language Model Optimization)」と呼ばれるケースもあります。
LLMOは、「大規模言語モデル」と呼ばれる技術に焦点を当てた名称です。
名称に違いはありますが、LLMOはAIOとほとんど同じ意味でつかわれるケースが多いといえるでしょう。
AIOをするべき理由
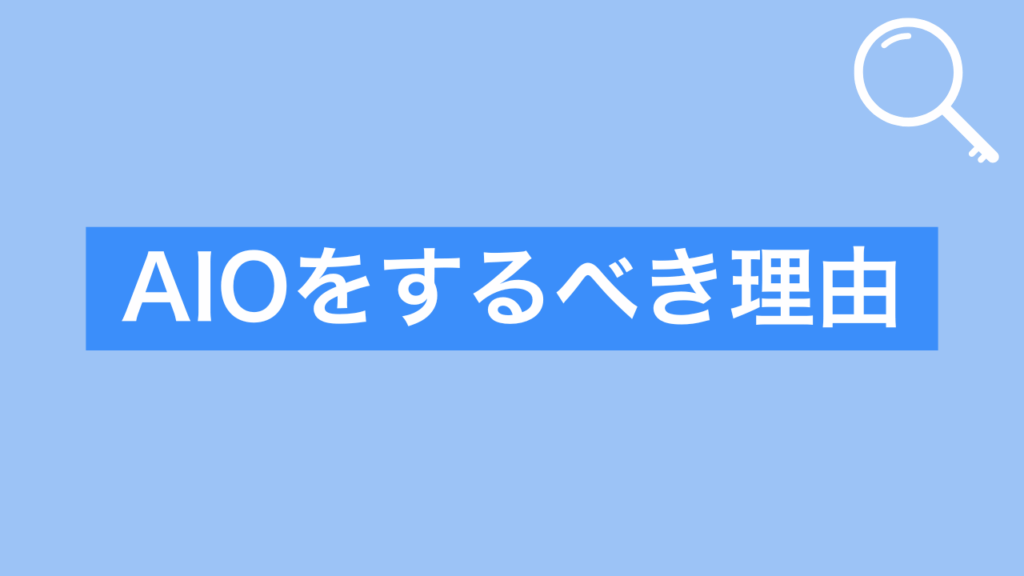
- 検索結果を見ずにAIの要約で情報収集する人が増えた
- AI概要の露出増によってクリック分配を再設計する必要性が高まった
- BtoBサイトは特にAIO施策の影響が出やすい
ユーザーの検索体験は、検索結果から気になる記事のタイトルをクリックするものから、AIの要約をチェックするものへと変化してきています。
Webサイトに掲載するコンテンツを作成する際には、いかにユーザーの注目を集められるのかを考える意識が大切です。
従来型のSEOではAIに選ばれる可能性は高まらないため、戦略を大きく見直す必要があるといえるでしょう。
検索結果を見ずにAIの要約で情報収集する人が増えた
AIによる情報提供が開始されてから、検索結果を細かく開かず、主にAIの要約から情報収集を行うユーザーが増えました。
検索結果の最初の画面でAIの要約をチェックして疑問が解ければ、各コンテンツへのリンクがクリックされる可能性は低いでしょう。
自社コンテンツの露出を高めていくには、AIの要約に採用されるようにしなくてはいけません。
AI概要の露出増によってクリック分配を再設計する必要性が高まった
AIによる要約が検索結果の目立つ位置に出るようになると、ユーザーのクリックの流れが変化します。
検索結果に上位表示させるだけでは、サイトへの流入の確保は難しくなるでしょう。
そのため、生成AIの引用からサイト流入を増やしていく必要があります。
具体的には、クリックは「AI要約 → 検索結果 → ページ内誘導」の3段で設計するのがおすすめです。
調べ物系はAI要約に拾われる作りを厚く、比較/選び方系は冒頭に比較表や診断を置いてページ内クリックを厚くします。
配分目安は【調べ物 5:3:2/比較 4:3:3】で、毎月データを見て微調整するといいでしょう。
BtoBサイトは特にAIO施策の影響が出やすい
AIO施策の影響は、特にBtoBサイトに出やすいとの見方もあります。
BtoBサイトでは、専門性の高いテーマを扱うケースが多いためです。
専門家インタビューや独自調査の結果をコンテンツに盛り込むことで、AIに評価されやすくなるでしょう。
参考文献や出典を明記し、権威性や信頼性が高いとAIに判断してもらうことが大切です。
AIOとSEOの違い

- SEOは流入最大化が目的・AIOは被引用最大化が目的
- KPI比較:順位/セッション vs 露出/被引用/指名
- 実装比較:キーワード/被リンク vs 構造化/一次データ
SEOとは、検索結果からのサイト流入を増やすための手法です。
一方でAIOは、AIの要約や回答で引用されるための手法を指します。
両者は目的が異なるため、具体的な施策や指標も変わります。
SEOは流入最大化が目的・AIOは被引用最大化が目的
SEOの主目的は検索結果からのサイト流入を増やすことです。
タイトルや見出し、本文にキーワードを積極的に盛り込んで検索エンジンの評価を高め、コンテンツへの流入を増やす施策が求められます。
一方、AIOの主な目的はAIが提供する要約に参考文献として挙げられることです。
AIが提供する情報の根拠として示されることで、コンテンツへの流入増加を図ります。
KPI比較:順位/セッション vs 露出/被引用/指名
SEOのKPIの中心は、検索順位やセッション、直帰率などです。
検索結果においてどれだけ上位に表示されるか、クリックの増減はどうか、などを観測します。
一方のAIOでは、AIの要約への被引用数や指名検索がKPIの軸です。
また、コンテンツの保存率や共有数も、ブランディングの成否を映す補助指標になるでしょう。
実装作業における違い:キーワード/被リンクvs構造化/一次データ
SEOを意識したコンテンツの実装では、キーワードの盛り込みや内部最適化、被リンクをできるだけ受けられるような設計が重要です。
ユーザーの検索意図に合う見出しと本文を作成し、検索エンジンからの評価を積み上げます。
一方のAIOでは、構造化データの設定や一次情報の積極的な掲載などが重要です。
AIに評価されるコンテンツを作るため、権威性・信頼性の高さやAIにとっての読み取りやすさなどを大切にする必要があります。
AIOとSEOの組み合わせが大切
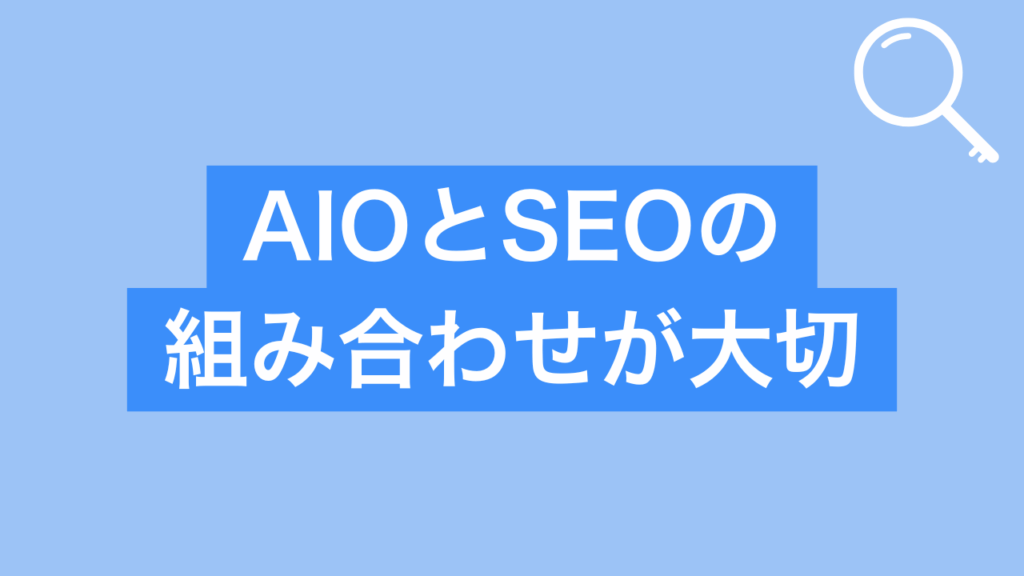
AIOはAIからの引用を増やす手段であり、SEOはクリックや被リンクから流入を増やす手法です。
現状ではいずれか一方を追求すればよいものではなく、両輪で設計するとことでWebからの集客を増やせると考えられます。
SEOによってクリックや被リンクを増やしていく施策とAIOによってAIに紹介してもらう施策の両方を、バランスよく取り入れるようにしましょう。
AIが理解しやすいコンテンツ作成のポイント
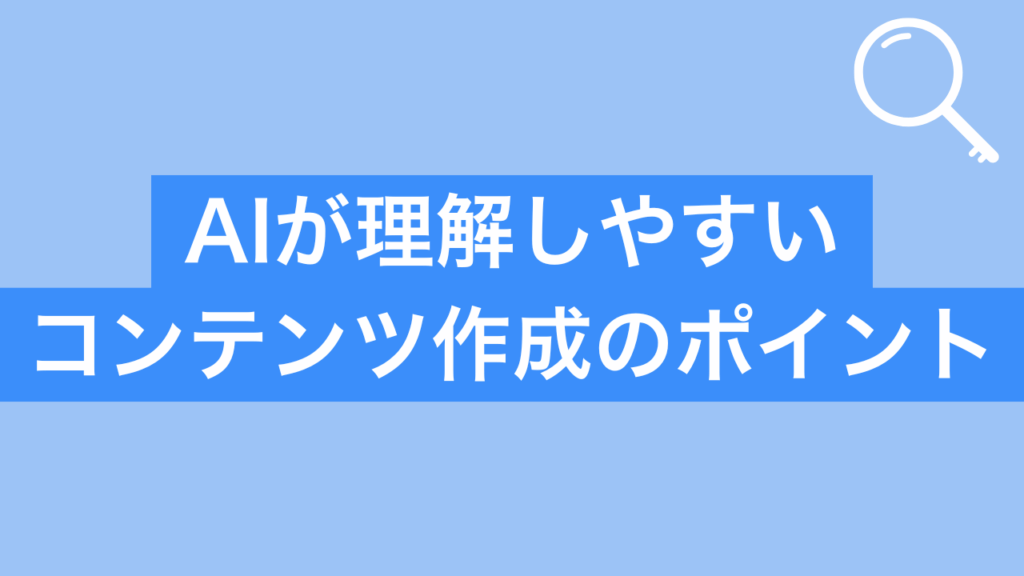
- 構造化データを設定する
- 論理的でわかりやすいコンテンツにする
- FAQ見出しを入れる
- 信頼性を強化する
- 箇条書きや表を活用する
- 出典リンクは近接配置して構造を明確にする
- 一次情報・独自情報を入れる
- 具体例やデータをできるだけ取り入れる
AIOを成功させるには、AIが読み取りやすいようにコンテンツの設計を工夫する必要があります。
ここでは、AIが理解しやすいコンテンツの作成ポイントを紹介するので、参考にしてみてください。
構造化データを設定する
AIOの具体的な施策としてまず挙げられるのが、構造化データの設定です。
構造化データとは、機械が理解・認識しやすいように定義された構造に従い、整理されたデータを指します。
構造化データを設定しておけばAIでの分析が容易になるため、引用される可能性が高まるでしょう。
論理的でわかりやすいコンテンツにする
論理的でわかりやすいコンテンツにすることも、AIOにおいては欠かせないポイントです。
コンテンツ全体の結論と要約文を冒頭に配置し、ユーザーがすぐに内容を理解できるようにしましょう。
文章は結論を先に出し、根拠、事例、結論の順を基本とします。
一文が長くなり過ぎないようにし、できる限り複雑な構造にしないことも大切です。
また、専門語は控え、難しい言葉を使う際には注釈を入れることも大切でしょう。
段落ごとに要点を一つに絞って内容の重複を減らす、図や画像で文章を補い理解しやすくする、などの工夫も重要です。
FAQ見出しを入れる
FAQ形式の見出しを入れると、AIが回答を生成しやすくなります。
読者の疑問を見出しにし、簡潔な回答を置きましょう。
質問は一意にし、余計な条件を混ぜないようにします。
回答もできるだけ簡潔に記述し、理解しやすいようにする工夫も大切です。
類義の質問も別立てにし、取りこぼしを防ぎます。
信頼性を強化する
コンテンツの著者の名前や経歴、専門分野を明示することで、信頼性を高める工夫も大切です。
コンテンツの制作者の情報を掲載することで、AIに「信頼できる情報を提供している」と判断してもらいましょう。
文章の執筆を担当したものだけでなく、監修者がいれば明示することも大切です。
専門家や有資格者がコンテンツの制作にかかわっていれば、権威性を高めるために積極的に明示するようにしてください。
箇条書きや表を活用する
できる限り箇条書きや表を使用することも、AIOにおいては重要です。
箇条書きや表を活用することで、AIがコンテンツを読み取りやすくなります。
構成が簡潔で分かりやすくなれば、AIの読み取りやすさだけでなく要約の精度も高まります。
出典リンクは近接配置して構造を明確にする
外部情報を引用したり参考にしたりした場合は、出典リンクを近くに配置します。
数値や引用のすぐ近くに出典を置き、関係を明確にすることが大切です。
一次情報・独自情報を入れる
コンテンツには一次情報や独自情報を取り入れるようにしましょう。
AIは、出典や根拠の信頼性を重視するためです。
基本的に公共機関や業界団体などの公式データを引用するようにし、出典も明記するようにしてください。
また、自社で行った調査や実測データを公開すれば、独自性が高まります。
具体例やデータをできるだけ取り入れる
コンテンツには、具体例やデータをできる限り取り入れるようにしましょう。
具体例やデータを入れることで、AIからの信頼性が高まります。
データを引用した場合は、必ず出典を明記することも忘れないようにしてください。
信頼性強化のポイント
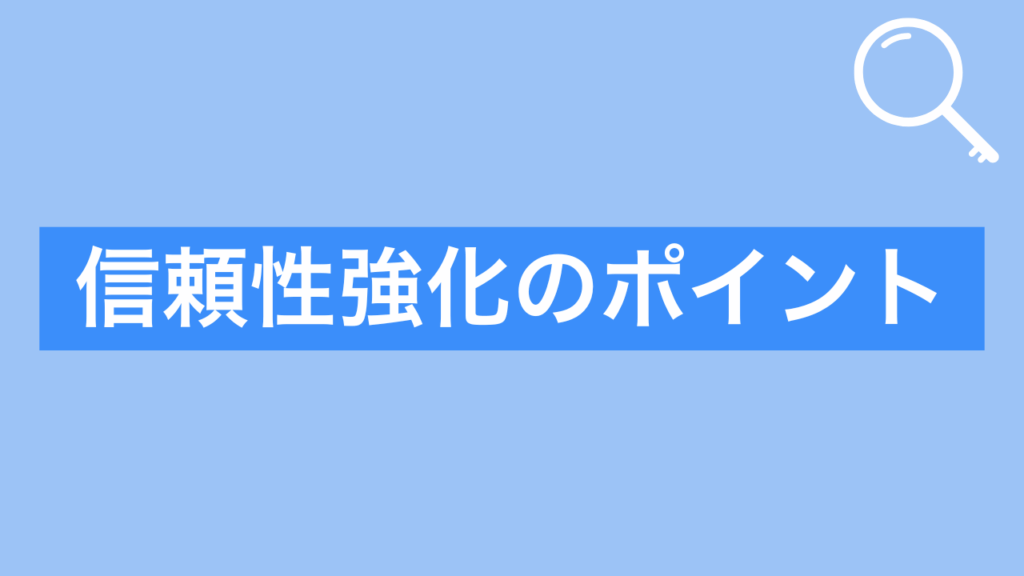
- 著者実名・経歴・専門分野を明示する
- 監修体制・実験条件・更新履歴を透明化する
- 編集方針・データ取得ポリシーを公開する
AIから信頼されるためには、信頼性を高める工夫が必要です。
著者実名・経歴・専門分野を明示する
記事の信頼性確保は、誰が作成に関わったのかを明かすことから始まります。
著者の名前や経歴、専門分野をコンテンツ内に明示するようにしましょう。
顔写真や保有資格、受賞歴があれば、積極的に盛り込むことをおすすめします。
監修体制・実験条件・更新履歴を透明化する
記事の信頼性や権威性を高めるためには、専門家による監修もおすすめします。
監修者の氏名と専門、確認した範囲を明確に示しましょう。
また、記事を更新した際には、日付と変更点を簡潔に残すことも信頼性確保においては重要です。
編集方針・データ取得ポリシーを公開する
記事の編集方針を公開すると、信頼性が高まりやすくなります。
取材基準や情報収集の基準、編集ポリシーなどを説明するようにしましょう。
たとえば、「公正中立な視点から記事を作成しています」と添えることで、コンテンツの姿勢を明確にできます。
AIO施策のポイント
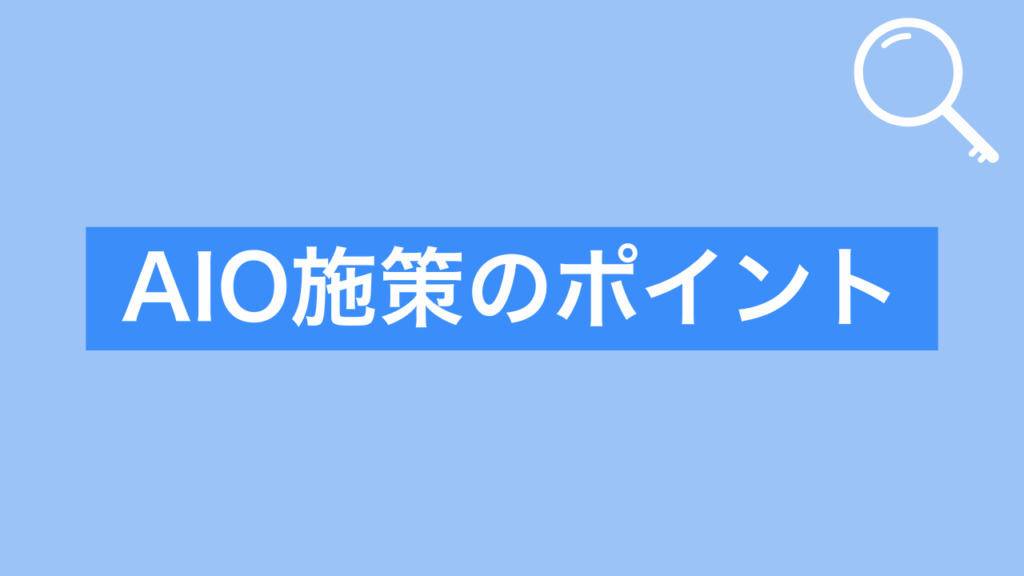
- FAQや要約などを取り入れてAIが理解しやすいコンテンツを作る
- 独自調査1本+ナレッジベース公開
- 検索トレンドを分析して定期的に情報を更新する
AIOは、継続的に運用することで成果を生みます。
AIO施策の実施におけるポイントを紹介するので、コンテンツ作成の参考にしてください。
FAQや要約などを取り入れてAIが理解しやすいコンテンツを作る
AIOを成功させるためには、できる限りAIが理解しやすいコンテンツを作る工夫が大切です。
たとえば、記事冒頭に記事全体の要約を置き、記事の結論を記すことでAIが概要を把握しやすくなります。
また、FAQ方式の見出しも、AIが要約を生成しやすくなるためおすすめです。
FAQでは似た疑問を整理・統合し、重複を避けて抽出精度を高めましょう。
独自調査1本+ナレッジベース公開
独自調査やナレッジベースを公開するのも、AIOにおいては重要なポイントです。
独自調査を公開することで、AIが「独自性があるコンテンツである」と判断してくれる可能性があります。
ナレッジベースとは、業務に関する知見をまとめたデータベースのことです。
企業が持つノウハウの公開も、独自性を高めるうえで役立つといえます。
検索トレンドを分析して定期的に情報を更新する
AIOでは、定期的にコンテンツを更新して最新情報を反映させていくことも重要です。
最新情報を掲載することで、信頼性が高いコンテンツとみなされる可能性が高まります。
また、ユーザーが知りたい情報が時間の経過とともに変化する可能性もあるため、SEOの観点からも定期的な更新は重要でしょう。
AIO対策をするメリット
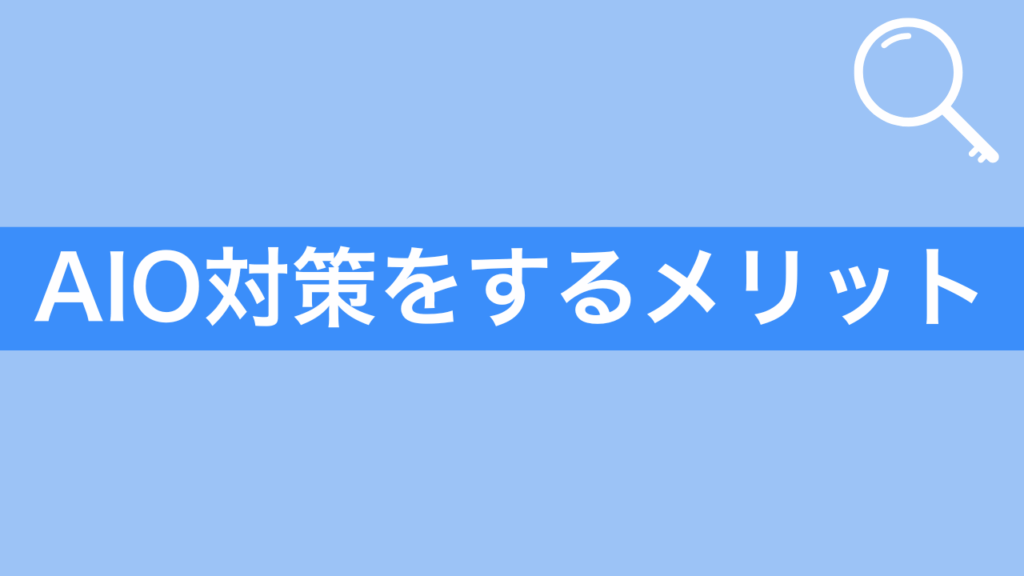
- 自社サイトの集客効果の向上
- コンバージョン率の向上
- 長期的な信頼蓄積によるエンティティの強化
AIO対策を徹底することで、AIから引用される可能性が高まりさまざまなメリットが生まれます。
自社サイトの集客効果の向上
AIの要約に引用されると、ユーザーとの接点が増えます。
また、AIO対策を進める中でコンテンツの質が高まれば、検索順位に対しても好影響を期待できるでしょう。
AIOはAIに最適化する手法ですが、検索流入の増加にもつながる可能性があるのです。
コンバージョン率の向上
AIOはコンバージョン率の向上にも貢献する可能性があります。
AIに最適化したコンテンツを作成すれば、ユーザーが欲している情報を的確に提供できるようになります。
ユーザーの検索意図に合ったコンテンツを提供できれば、サイト滞在時間が伸びてコンバージョン率の向上につながります。
長期的な信頼蓄積によるエンティティの強化
AIOを通じてユーザーからの信頼を長期的に獲得していけば、エンティティの強化にもつながります。
エンティティとは、企業やブランドが持つインターネット上での存在感です。
ユーザーが繰り返し参照するような質の高いコンテンツを作り出せば、ユーザーへ継続的にアプローチできます。
ユーザーへ繰り返しアプローチすることで、「〇〇の分野ではこの企業・ブランド」と認識されれば、エンティティの強化につながるでしょう。
AIO対策をするデメリット・リスク
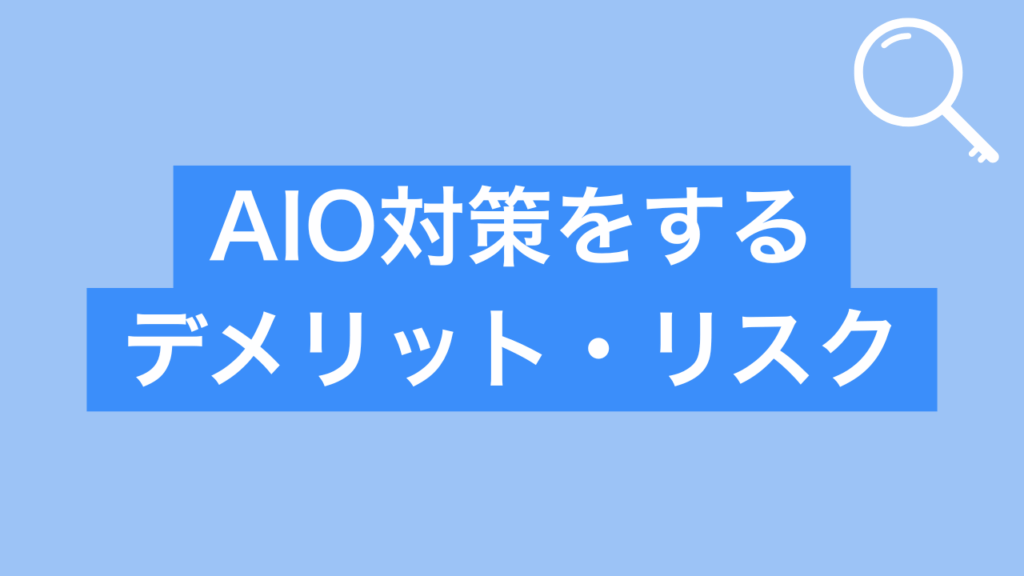
- 予想外の市場変化に対応できない
- コンテンツ作成・管理にかかるコストが増える
- AIの変化・進化を常に追っていく必要がある
AIOは効果が大きい一方で、運用には難しいポイントも一定程度存在します。
ここでは、AIOのデメリットやリスクを紹介します。
予想外の市場変化に対応できない
AIOは「過去の傾向」をもとに答えるため、法改正・価格改定・大型セールなどの“急な変化”に弱いです。
その結果、「①AI要約に古い情報が出続ける」「②伸び始めの新キーワードを拾えない」「③対応の優先順位がズレる」といった問題が起きやすく、特に価格・在庫・日程のように動きが速い分野で影響が大きくなります。
変わりやすい情報はAI任せにせず、人が定期チェックしてすぐ直す方がいいでしょう。
また、検索ニーズの変化を見て内容や見出しを柔軟に更新し、急な変更にも即対応できる体制を用意しておくことも大切です。
コンテンツ作成・管理にかかるコストが増える
AIOを続けていくには、一定のコスト増を覚悟しなくてはいけません。
AIに最適化したコンテンツを作成し更新し続けるには、手間も時間もかかります。
限られた予算の中では、AIOの実施・継続が大きな負担となる可能性があるでしょう。
AIの変化・進化を常に追っていく必要がある
AIOは「一度実施すれば完了」ではありません。
AIの仕様や評価基準が、定期的に更新されるためです。
一度AIO対策をとっても、そのままにしておけばAIからの引用が減り、効果がなくなってしまうでしょう。
AIOを成功させるには、継続的に取り組める仕組みづくりが求められます。
活用したいAIO対策ツールの例
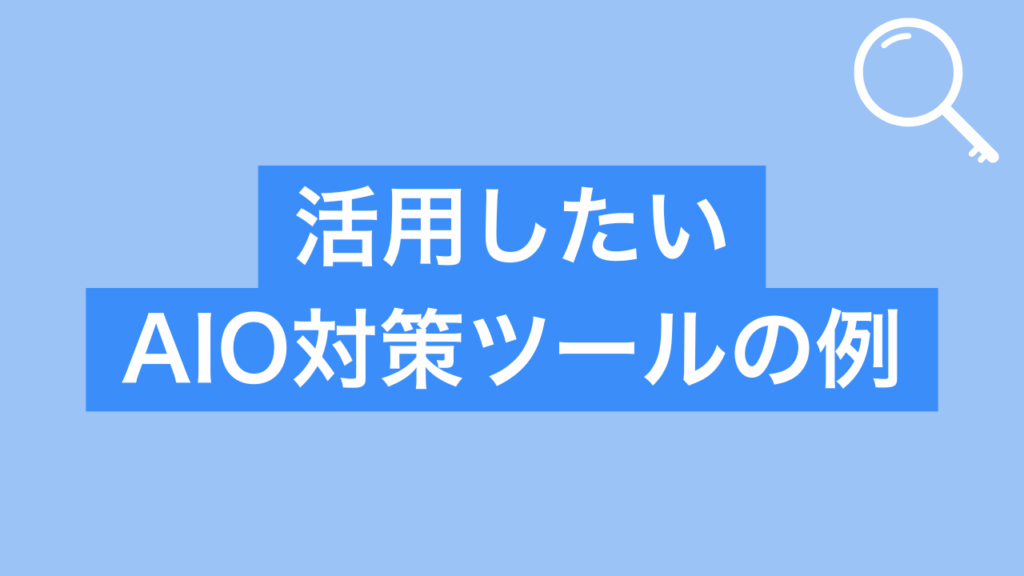
- 構造化データ生成・テストツール
- AI検索の露出チェックツール
- SEOコンテンツ最適化ツール
- リファラ・順位計測などのSEOチェックツール
- 自然言語処理(NLP)ツール
AIOを成功させるには、無理なく運用できる仕組みづくりが大切です。
ここではAIO施策の効率化に活用できるツールを紹介するので、自社の体制や予算に合わせて段階的に組み込んでみてください。
構造化データ生成・テストツール
AIOに活用できるツールとしてまず挙げられるのが、構造化データ生成・テストツールです。
構造化データはAIと検索に意味を伝えるための設計図です。
生成ツールを活用すれば、一定の定義に従った構造化データを比較的容易に作成できます。
また、テストを活用すれば、構造化のマークアップが誤りなくされているか確認可能です。
AI検索の露出チェックツール
AI検索の露出チェックツールを活用すれば、AI検索における自社コンテンツの露出状況を可視化できます。
AIの要約で自社コンテンツが引用される頻度を把握することで、改善につなげられるでしょう。
SEOコンテンツ最適化ツール
SEOコンテンツ最適化ツールを活用すれば、検索結果の上位を目指すための作業を比較的容易に実施できます。
たとえば、文章の読みやすさの向上や関連する内部・外部リンクの挿入、関連キーワードの網羅などを簡単に実施可能です。
コンテンツ最適化ツールによって、トラフィックの増加やコンバージョン率の向上などが期待できるでしょう。
リファラ・順位計測などのSEOチェックツール
SEO施策の結果を確認・分析するためのツールも、積極的な活用をおすすめします。
自然検索による流入の確保は、AIOの重要性が増している現在でも依然として重要です。
日次で順位とクリック率を追っていけば、異常値や異変を早期に検知できます。
また、リファラ分析によって引用元からの遷移や共有の流入を可視化できます。
要約露出と順位の関係を見て、リライトすべきコンテンツを決定しましょう。
SEOとAIOの指標を定期的に確認・改善していけば、コンテンツの競争力を飛躍的に高めることも可能です。
自然言語処理(NLP)ツール
自然言語処理ツールとは、文章をAIが解析し、修正や要約などを行ってくれるシステムのことです。
文章の要約や校正、類語検索などさまざまな機能を持ったツールが存在します。
たとえば、要約生成を下書きに活用することで、冒頭に設置する要約の作成を素早く行えるでしょう。
表現や言い回しの提案を行ってくれるツールもあるため、文法的に正しく読みやすい文章の作成に役立ちます。
AIO導入の成功パターン
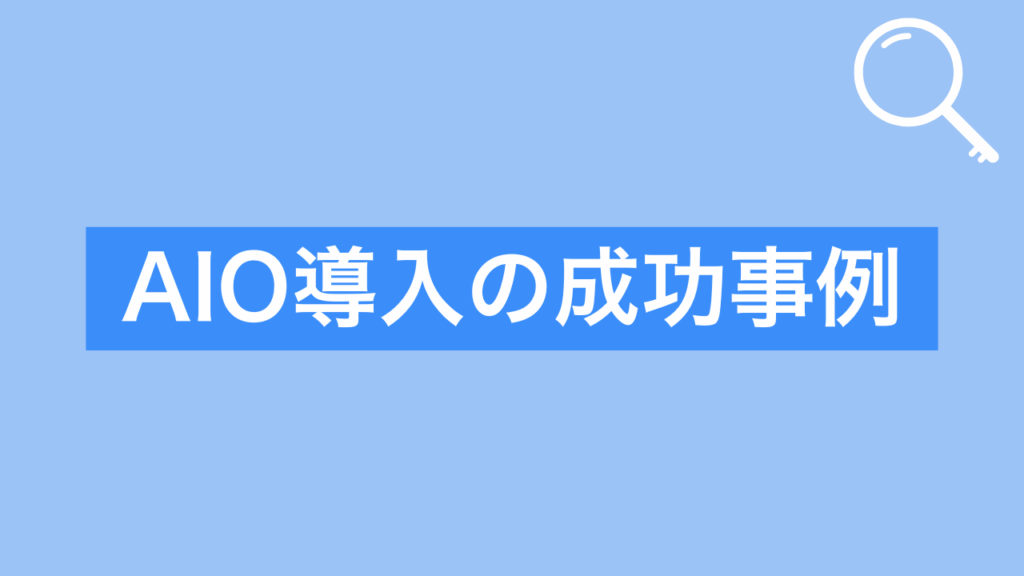
- 不動産業界
- 金融業界
- ECサイト
すでにさまざまな業界で、AIO対策の成功パターンが見られます。
各業界で想定されるAIO対策の成功パターンを紹介するので、自社の施策を検討する際の参考にしてみてください。
不動産業界
不動産業界では、AIO対策を実施することで問い合わせ件数を増やした例があります。
物件情報の基本データを構造化してAIに読みやすいようにし、FAQ形式のコンテンツを作成することでAIの読みやすさを向上させることが可能です。
また、自社の独自性や専門性を積極的に発信することで、AIに権威性や信頼性を示せます。
金融業界
金融業界においても、AIOによって成果を上げた実例は存在します。
金融商品の情報をFAQ形式のコンテンツで紹介することで、AIによる引用を増やすことに成功しました。
また、顧客の行動パターンを分析してニーズに合わせた商品を提示することで、コンバージョンや顧客満足度の向上につなげた事例もあります。
手数料や利回りなどの説明を表にまとめて明示することも、AIO上は大切です。
専門語には注釈を添えて誤解の余地を小さくすることも、コンテンツの質を高めるためには重要でしょう。
ECサイト
大手ECサイトでは、AIOによって各ユーザーにパーソナライズされた検索結果を提供することで、コンバージョン率を向上させました。
ユーザーの検索クエリから関連性の強い商品を提示できるように仕組みづくりを行い、顧客満足度の向上につなげました。
まとめ
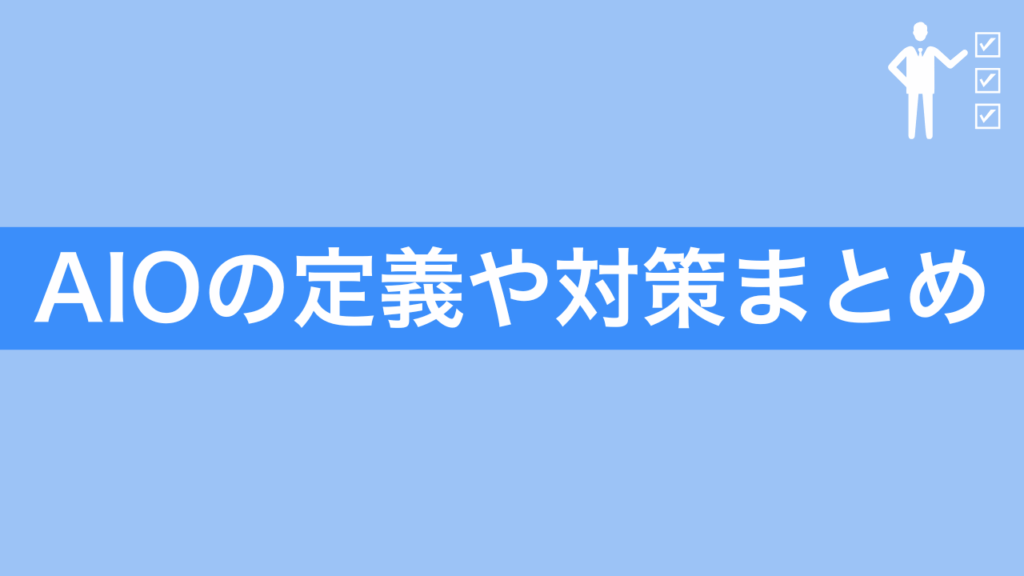
AIOはAI要約で自社コンテンツが引用されるようにするための最適化手法です。
クリックや被リンクの獲得を目的とするSEOとは大きく異なり、AIOでは被引用とエンティティの強化が大きな目的です。
AIOでは、論理的でわかりやすいコンテンツを作成し、構造化データを設置することでAIが理解しやすいようにする必要があります。
また、一次データや独自情報を公開し、信頼性や権威性を高める工夫も重要です。
SEOとAIOを並行して実施し、自社コンテンツの集客力アップを目指しましょう。なお、AI検索の具体的な仕組みについては「AI Overviewとは?」、Google検索のAI機能については「AIモードとは?」の記事もあわせてご覧ください。
「LLMOに取り組みたいが、何から始めればいいかわからない」
「自社サイトがAI検索でどう扱われているか知りたい」
TRILIA株式会社では、SEO・LLMO領域の専門知見と独自のAI分析基盤を活かし、完全成果報酬型のマーケティング支援を提供しています。初期費用0円で、まずは現状の課題整理からお手伝いいたします。