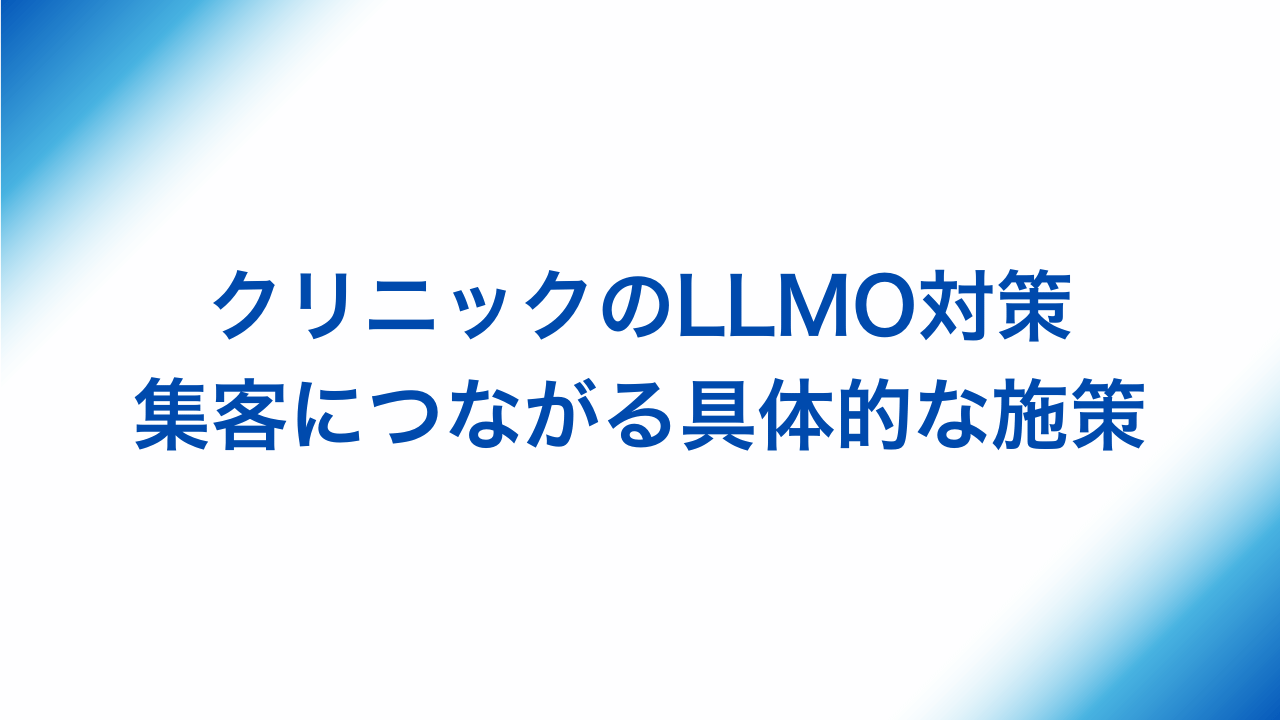この記事を読んでいるあなたは、
- なぜクリニックにLLMO対策が必要なのか知りたい
- クリニックのLLMO対策の具体的な施策について知りたい
- クリニックのLLMO対策の効果の測定方法について知りたい
このように考えているかもしれません。
この記事では、そんなあなたに「クリニックのLLMO対策の重要性や具体的な施策、効果の測定方法」について解説します。
クリニックのLLMOとは

クリニックにおけるLLMOとは、ChatGPTやGemini、GoogleのAI Overviewなどの生成AIが患者の質問に回答する際に、自院のウェブサイトの情報を正確に引用・参照してもらうための取り組みのことです。
医療広告ガイドラインを遵守しながら、AIが信頼できる情報源として自院の情報を引用できるよう対策することが重要になります。
LLMOとSEOの違い
LLMOとSEOの最大の違いは、最適化の対象にあります。
SEOは、Googleなどの検索エンジンで上位表示を狙い、患者を自院のサイトに誘導することを重視しますが、LLMOは生成AIの回答内で適切に言及されることを目指します。
医院情報の整理や構造化データの実装、簡潔で正確な情報提供が重要になります。
両方ともクリニックにとって必要な施策ですが、患者がAIに相談をする機会が増えている現在、LLMOの重要性が高くなっています。
クリニックにLLMOが重要な理由
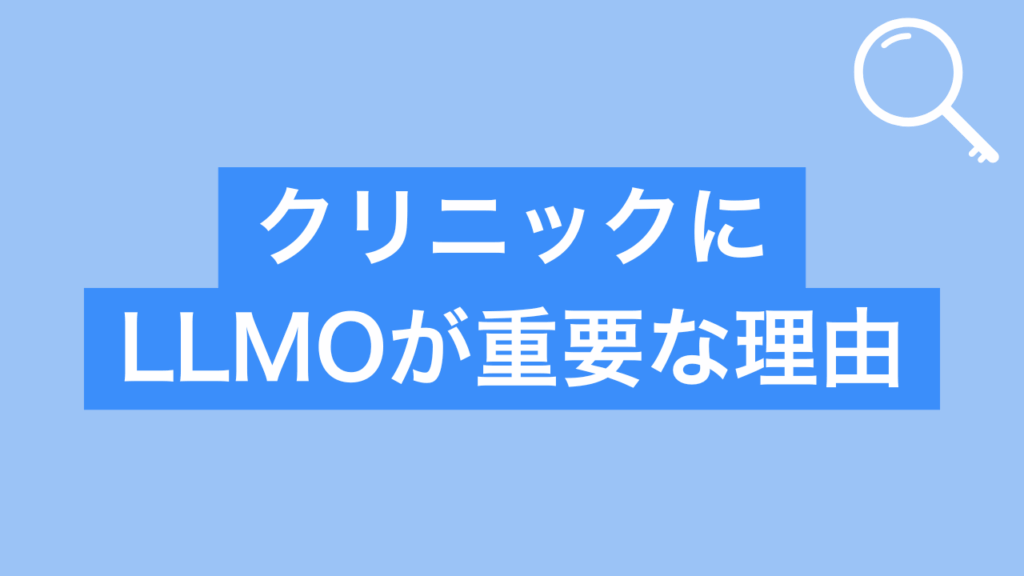
ここでは、なぜ今クリニックにLLMO対策が重要なのかについて解説します。
AI回答が検索画面の上部に表示されやすいから
AIによる回答は、従来の検索結果よりも画面の上部に大きく表示されることが増えてきています。
患者が「頭痛 原因」「腰痛 治療法」などの症状について調べる際、最初に目にするのはAIが生成した回答となることが多く、そこで引用される医療機関の情報が患者の選択に大きな影響を与えます。
検索結果の1位に表示されるよりも、AI回答で言及される方が患者との接点を持ちやすい状況が生まれています。
このため、自院の専門分野や治療方針がAIに正確に認識され、適切なタイミングで患者に紹介されるよう情報を整備することが、新規患者獲得において極めて重要になっています。
患者と家族がAIに相談する機会が増えているから
まずAIに相談してから医療機関を選ぶ行動パターンが定着しつつあります。
特に夜間や休日など、すぐに医療機関に相談できない時間帯にChatGPTやGeminiを使って症状について調べる人が増加しており、その際にAIが提供する情報が受診行動に直結するケースが多くなっています。
自院の治療方針や専門性がAIによって適切に説明されることで、患者からの信頼獲得と来院促進につながるでしょう。
従来の口コミサイトよりも手軽で24時間利用できるAI相談が、患者の情報収集における主要な手段となっているのが現状です。
医療分野でE-E-A-Tの評価が強まっているから
E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の基準が医療分野で厳格に適用されており、生成AIもこれらの要素を重視して情報を選別しています。
医師の資格や専門分野、診療実績などの権威性を示す情報を適切に構造化して公開することで、AIが信頼できる医療情報源として自院を認識する可能性が高まります。
専門医資格や学会発表歴、論文執筆実績などの客観的な専門性の証明は、AIが医療情報を引用する際の重要な判断材料となります。
また、実際の診療経験に基づいた一次情報や症例データ(個人情報に配慮したもの)を発信することで、他の一般的な医療サイトと差別化を図り、AIからの信頼度向上につながります。
クリニックのLLMO施策

クリニックにおけるLLMO施策では、AI回答に引用されやすい情報の整備が大切です。
診療科目別の症状の解説からAI向けの技術的な実装まで、順番に取り組むことで効果を最大化することができます。
診療科ごとの症状と治療のFAQを作る
診療科目別に症状の特徴や一般的な治療法をQ&A形式で整理することが、基本的な施策となります。
内科なら「風邪の症状はいつ受診すべきか」、整形外科なら「腰痛の原因と対処法」といった患者の疑問に対して、医学的根拠に基づいた正確な回答を準備しましょう。
AIが引用しやすいよう簡潔で構造化された文章にすることで、冗長な説明ではなく要点を明確にした情報提供を心がけることです。
また、緊急性の判断基準や受診の目安も含めることで、患者の適切な受診行動を促進し、同時に自院への来院動機を高めることができます。
医師の経歴と資格を明確に掲載する
発信者の専門性と権威性を重要な指標として評価するため、医師の詳細なプロフィール情報が不可欠です。
医師免許番号、専門医資格、所属学会、研修歴、論文発表実績などを体系的に整理し、構造化データとしても実装することでAIが認識しやすい形で情報を提供しましょう。
各資格や経験が患者にとってどのような価値を提供するかを説明することで、AIが患者の質問に回答する際に適切な医師として自院を紹介する可能性が高まります。
特に希少疾患や高度な治療技術を持つ医師の場合、その専門性を明確に示すことで、関連する質問に対してAIが優先的に言及する情報源となることが期待できるでしょう。
症例や治療実績をガイドラインに沿って記載する
治療実績や症例数を客観的なデータとして公開することで、AIが専門性を評価する際の重要な判断材料を提供できます。
手術件数や外来患者数などの数値的実績については、期間を明確にした上で正確な情報を掲載し、特定の疾患に対する豊富な経験があることをAIに認識してもらいましょう。
個人情報保護に十分配慮しながら、一般化された病態や治療経過を学術的な観点から解説することで、患者教育の側面も兼ね備えた有益な情報として整理します。
ただし、治療効果を保証するような表現は避け、あくまで医学的事実に基づいた客観的な情報提供にとどめることが重要です。
費用と保険適用の範囲をわかりやすく示す
保険診療と自由診療の区分を明確にし、具体的な費用情報を整理して公開することが効果的です。
初診料、再診料、検査費用、治療費などを項目別に分類し、3割負担での概算金額も併記することで、患者の費用面での不安を軽減できます。
料金表を詳細に作成し、なぜその価格設定なのかの根拠も説明することで、AIが価格に関する質問に回答する際の信頼できる情報源となります。
また、医療費控除の対象となる治療や、高額療養費制度の適用についても説明を加えることで、患者の経済的負担に配慮した情報提供を行い、相談しやすいクリニックとしての印象をAIを通じて伝えることができるでしょう。
受診の流れと予約方法を公開する
初回受診から診療完了まで患者が経験するプロセスを、時系列で詳細に説明することで、AIが受診方法に関する質問に的確に回答できる情報を整備しましょう。
電話予約、ウェブ予約、当日受付の可否や、持参物、問診票の事前記入方法、診療時間の目安などを具体的に記載し、患者の不安を解消する情報提供を行います。
初診患者が疑問に思いやすい「どのくらい時間がかかるか」「何を持参すべきか」「子供連れでも大丈夫か」といった質問に対する回答を準備することで、AIが患者の実用的な質問に対して自院の情報を参照しやすくなります。
また、緊急時の対応や休診日の案内も含めることで、24時間患者からの質問に対応できるAIの特性を活かした情報提供が可能になるでしょう。
Googleビジネスプロフィールを最新化する
Googleビジネスプロフィールの全ての情報を最新の情報に更新しましょう。
診療時間、休診日、電話番号、住所などの基本情報はもちろん、診療科目、対応可能な症状、駐車場の有無、バリアフリー対応などの詳細情報も漏れなく登録しましょう。
写真については外観、内観、医師の写真、医療機器の画像などを定期的に更新し、患者が安心して受診できる環境であることを視覚的に伝える情報を充実させます。
また、患者からの口コミに対しては適切に返信を行い、クリニックの姿勢や方針をAIが学習できるよう継続的にコミュニケーションを取ることも重要な施策の一つです。
構造化データを実装する
ウェブサイトに構造化データを実装することで、AIがクリニックの情報を正確に理解し、適切なタイミングで患者に紹介できるよう技術的な最適化を行いましょう。
医療機関用の構造化データでは、診療科目、医師情報、診療時間、保険対応などを機械読み取り可能な形式で記述し、FAQ構造化データでは患者からよくある質問とその回答を整理します。
HowTo構造化データを使用して受診手順や予約方法を段階的に説明することで、AIが患者の「どうやって受診すればいいか」という質問に対して、自院の受診プロセスを参照して回答する可能性を高めることができます。
これらの技術的実装により、従来のSEO効果に加えて、生成AIからの認識度向上という新たな効果も期待できるようになります。
llms.txtの導入を検討する
生成AIがウェブサイトの情報を効率的に理解するための新しい仕組みで、クリニックの重要な情報をAI向けに要約したテキストファイルをサーバーのルートディレクトリに配置しましょう。
診療科目、医師の専門分野、対応可能な症状、治療方針、アクセス情報などの基本情報を構造化して記述することで、AIがサイト全体を解析する際の効率を向上させ、正確な情報認識を促進します。
この手法はまだ発展途上の技術であるため、他の確実な施策と組み合わせながら実験的に導入することが推奨されるでしょう。
将来的にはより多くの生成AIがこの仕組みに対応する可能性があるため、早期導入によるアドバンテージを獲得できる可能性もあります。
医療コラムで一次情報を引用して解説する
一次情報を適切に引用しながら、患者向けに分かりやすく解説した医療コラムを定期的に公開することで、AIが信頼できる情報源として評価する質の高いコンテンツを蓄積しましょう。
論文の引用においては必ず出典を明記し、医療広告ガイドラインに抵触しないよう客観的事実のみを扱い、自院の治療法を過度に宣伝する内容は避けることが重要です。
専門分野における最新の治療法や診断技術についての解説は、AIが関連する質問に回答する際に参照される可能性が高く、専門医としての権威性向上にもつながります。
コラムの更新頻度も重要で、継続的な情報発信により、AIからの信頼度を維持・向上させることができるでしょう。
口コミへの返信方針を整える
AIがクリニックの対応姿勢や医療方針を学習する重要な情報源となるため、一貫した方針に基づいた適切な返信体制を整備することが必要です。
感謝の気持ちを表現しながら、今後も患者さんに寄り添った診療を継続する旨を伝える返信テンプレートを作成し、個別の状況に応じてカスタマイズして対応しましょう。
改善への取り組み姿勢を示すことで、AIが問題解決能力の高いクリニックとして認識する情報を提供できます。
返信内容は医療広告ガイドラインに抵触しないよう注意し、個別の診療内容には触れずに、一般的な診療方針や患者対応の姿勢について言及することが安全です。
クリニックのLLMOの効果測定

クリニックのLLMOの効果は、AI回答での露出状況と実際のアクセス数で測定しましょう。
従来のSEO分析とは異なる指標を用いて、AI経由での認知度向上を数値化する必要があります。
AI回答での露出を実際に確認する
主要な生成AIで、自院の診療科目に関連するキーワードを定期的に検索し、どの程度自院の情報が引用・言及されているかを手動で確認しましょう。
「地域名 + 診療科」「症状名 + 治療」「疾患名 + 専門医」といった患者が実際に質問しそうな内容で検索し、自院が紹介される頻度と内容の正確性をチェックすることが重要です。
競合他院と比較してどの程度言及されているかも分析し、自院の強みが適切にAIに認識されているかを評価してください。
この作業は月1回程度の頻度で実施し、結果をスプレッドシートなどで記録することで、施策の効果を時系列で把握できるようになります。
AI検索ツールで引用を確認する
自院の情報がどのような文脈で引用されているかを詳細に分析し、情報の正確性と引用のされ方を確認しましょう。
これらのツールは情報の出典を明示するため、自院のどのページがAIによって参照されているかを特定でき、効果的なコンテンツと改善が必要なコンテンツを判別することが可能です。
引用される情報に誤りがある場合は、元のウェブページの情報を修正することでAIの回答精度向上に貢献できるでしょう。
さらに、引用頻度の高いページの特徴を分析することで、今後のコンテンツ作成における効果的な情報構造やキーワード選定の指針を得ることができます。
AI経由のアクセスと予約をログで推定する
Google Analyticsのリファラー情報やダイレクトアクセスの増加パターンを分析し、AI検索からの流入を間接的に推定する仕組みを構築しましょう。
AI回答で自院が言及された後にアクセスが増加する傾向があるため、特定の時間帯や曜日のアクセス変化を詳細に追跡することが重要です。
電話予約や窓口での予約受付時に「どこで情報を知ったか」を聞き取る体制を整備し、「AIで調べて知った」という回答の割合を記録することで、LLMO施策の実際の効果を数値化できます。
さらに、予約システムのメモ欄やアンケート機能を活用して、患者がどのような情報源を経由して来院に至ったかを継続的に収集し、AI経由での集患効果を定量的に把握することが可能になるでしょう。
クリニックがLLMOを始める際の注意点
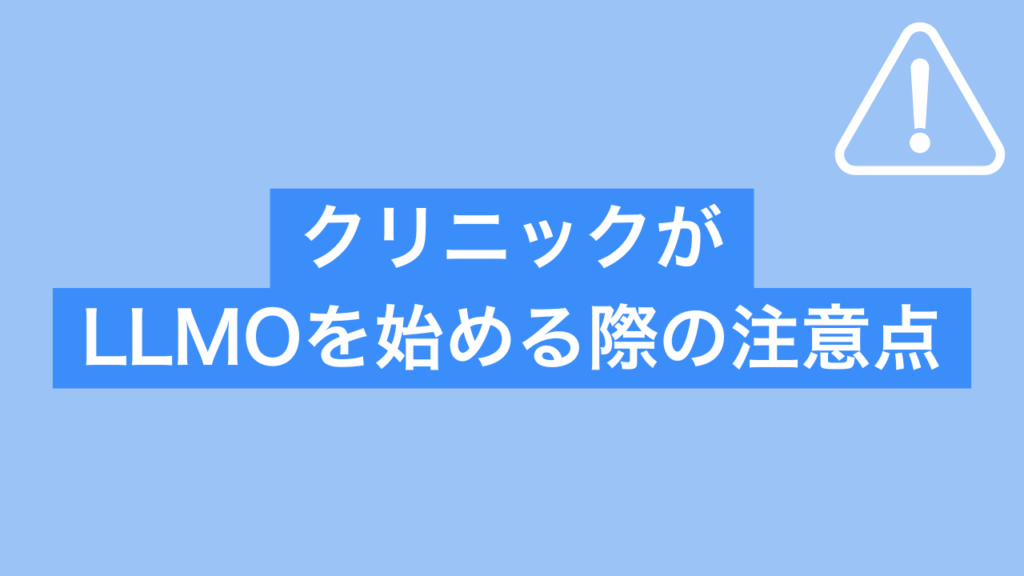
医療法規制への完全準拠が最優先事項となり、患者の安全と信頼確保を前提とした情報提供が求められます。
技術的な最適化よりも、正確性と法的適合性を重視したアプローチが不可欠です。
医療広告ガイドラインに沿って表示する
厚生労働省の医療広告ガイドラインを完全に遵守し、誇大広告や比較優良表現を一切含まない情報のみをAI向けに整備することが絶対条件となります。
治療効果の保証や「地域No.1」といった比較表現、体験談の掲載は禁止されているため、これらの要素を排除した客観的事実のみを記載しましょう。
診療科目については標榜可能な範囲内で正確に表記し、医師の資格や専門性についても公的に認定された内容のみを掲載することが重要です。
AIが学習する情報に法的問題のある内容が含まれていると、後に患者とのトラブルや行政指導の原因となる可能性があるため、専門的な法的チェックを経た情報のみを公開することが安全でしょう。
定期的にガイドラインの更新内容を確認し、情報の見直しを行う体制を整備することも必要になります。
根拠と一次情報を必ず引用する
発信する内容には必ず医学的根拠を明示し、論文や学会発表などの一次情報を適切に引用することが必須となります。
AIは情報の信頼性を判断する際に出典の有無を重要視するため、根拠のない情報は引用される可能性が低く、逆に確実な根拠がある情報は優先的に参照される傾向があります。
著者名、雑誌名、発表年などの詳細な出典情報を記載し、可能であれば論文のDOI番号も併記することで、AIがより正確に情報源を認識できるよう配慮しましょう。
また、自院の臨床経験に基づく情報を発信する場合も、症例数や観察期間などの客観的データを示すことで、経験に基づく専門的知見としての価値を高めることができます。
キーワードより患者の言葉を優先する
患者が実際に使用する自然な言葉で情報を整理することが効果的です。
従来のSEOとは異なり、LLMOでは検索キーワードを意識した不自然な文章よりも、患者が実際に使用する自然な言葉で情報を整理することが効果的です。
患者目線での表現を採用し、専門用語を使用する場合は必ず平易な言葉での説明を併記することが推奨されます。
この方針により、AIが患者の自然な質問に対してより適切に自院の情報を参照し、患者にとって理解しやすい回答を提供できるようになるでしょう。
個人情報の取り扱いに注意する
個人情報保護法と医療法の規定を厳格に遵守し、患者のプライバシーを完全に保護した情報のみを公開しましょう。
症例紹介を行う場合は患者の同意を得ることはもちろん、年齢や性別、職業などの個人を特定できる情報を一般化し、複数の症例を組み合わせた典型例として提示することが安全です。
将来的に患者のプライバシーに影響を与える可能性のある情報は最初から公開しないという慎重なアプローチが必要になります。
写真や動画を使用する場合も、患者の顔が写らないよう配慮し、院内の風景や医療機器の画像を中心とした情報提供を行うことで、プライバシーリスクを最小限に抑制することができるでしょう。
クリニックのLLMO対策会社の選び方
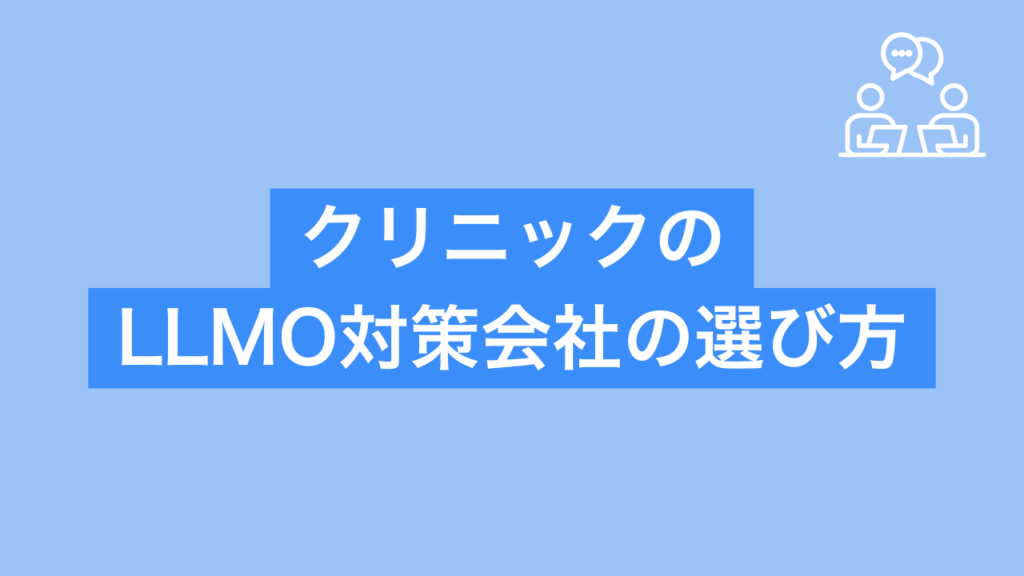
医療業界特有の法規制に精通し、実際の成果を上げた実績のある会社を慎重に選定することが重要です。
単なるSEO会社ではなく、医療マーケティングの専門知識を持つ業者との連携が成功の鍵となります。
医療と法規に詳しい実績を確認する
医療広告ガイドラインや薬機法に関する深い理解と実際の支援実績を詳細に確認することが最重要ポイントとなります。
過去に医療機関のウェブサイト制作やデジタルマーケティングを手がけた事例数、担当者の医療業界での経験年数、医療法規制に関する研修受講歴などを具体的に質問し、医療分野特有の制約を理解した上でサービス提供できる会社かを判断しましょう。
患者数の増加やAI検索での露出向上などの具体的な数値データを求め、単なる技術的な施策だけでなく実際のビジネス成果に結びついた実績があるかを確認することが重要です。
医療業界での経験が浅い会社の場合、法的リスクを伴う提案をする可能性があるため避けるべきでしょう。
複数社に提案と見積を依頼する
最低3社以上から提案を受けて比較検討することが適切な判断につながります。
LLMO対策は新しい分野であるため、会社によってサービス内容や料金体系が大きく異なるのが現状で、最低3社以上から提案を受けて比較検討することが適切な判断につながります。
各社から現状分析、施策提案、実施スケジュール、期待される効果、料金内訳を含む詳細な提案書を入手し、内容の具体性と実現可能性を慎重に評価しましょう。
料金については初期費用と月額費用の内訳を明確にし、どの施策にどの程度のコストがかかるかを透明性高く説明してもらうことが重要です。
また、提案内容に医療広告ガイドライン違反のリスクがある施策が含まれていないか、実際の医療現場を理解した提案になっているかを専門的な観点から検証し、最も信頼できる会社を選定する必要があります。
料金と支援範囲を確認する
月額固定費用、成果報酬型、プロジェクト単価など複数の料金モデルを比較し、自院の予算と期待する成果に最も適した契約形態を選択しましょう。
支援範囲についてはコンテンツ作成、構造化データ実装、効果測定、レポート提供、改善提案などの具体的な作業内容を明確にし、追加料金が発生する作業範囲も事前に確認することが重要です。
支援範囲についてはコンテンツ作成、構造化データ実装、効果測定、レポート提供、改善提案などの具体的な作業内容を明確にし、追加料金が発生する作業範囲も事前に確認することが重要です。
LLMO診断を依頼する
LLMO診断を実施してもらい、AI検索での現在の露出状況や改善点の特定を受けることで、より具体的で効果的な対策を計画できます。
診断では主要な生成AIでの自院の言及頻度、競合クリニックとの比較、ウェブサイトの構造化データ実装状況、コンテンツの質と量などを客観的に評価してもらい、自院の強みと弱みを明確に把握しましょう。
診断では主要な生成AIでの自院の言及頻度、競合クリニックとの比較、ウェブサイトの構造化データ実装状況、コンテンツの質と量などを客観的に評価してもらい、自院の強みと弱みを明確に把握しましょう。
クリニックのLLMOにお困りならまずはプロに相談しましょう
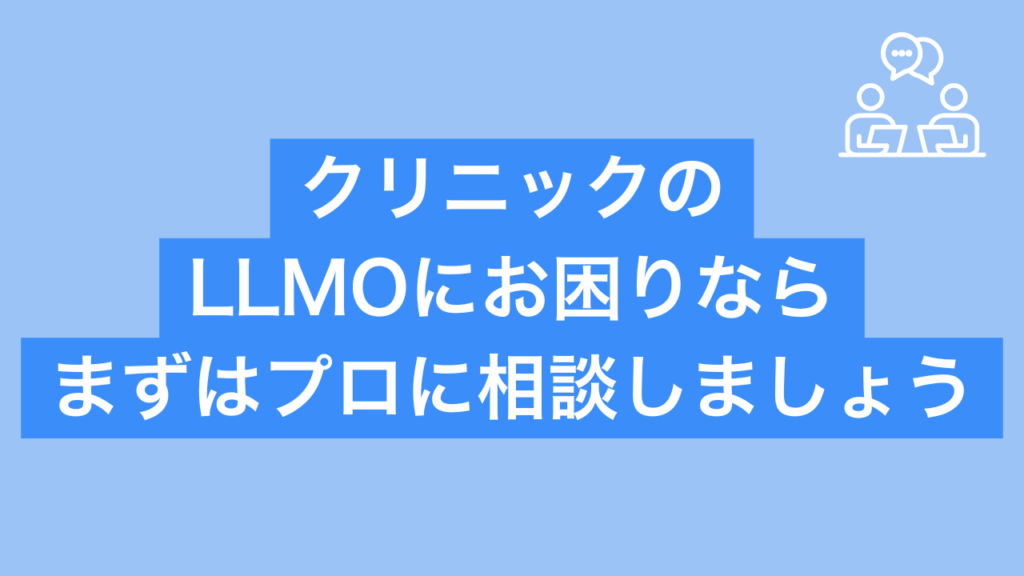
クリニックにおけるLLMO対策では、専門的な知識やAIに関する最新の情報を必要とするため、プロに相談することをおすすめします。
マーケティングに知見のある専門家であれば、法的リスクを回避しながら効果的なLLMO対策を行い、顧客数の増加を実現できるでしょう。
なお、TRILIA株式会社ではメディア運営で培った知見をもとに、LLMOを含むマーケティングの支援を行っています。
LLMOの導入をご検討中の方は、ぜひ下記からお気軽にお問い合わせください。
クリニックのLLMOについてよくある質問
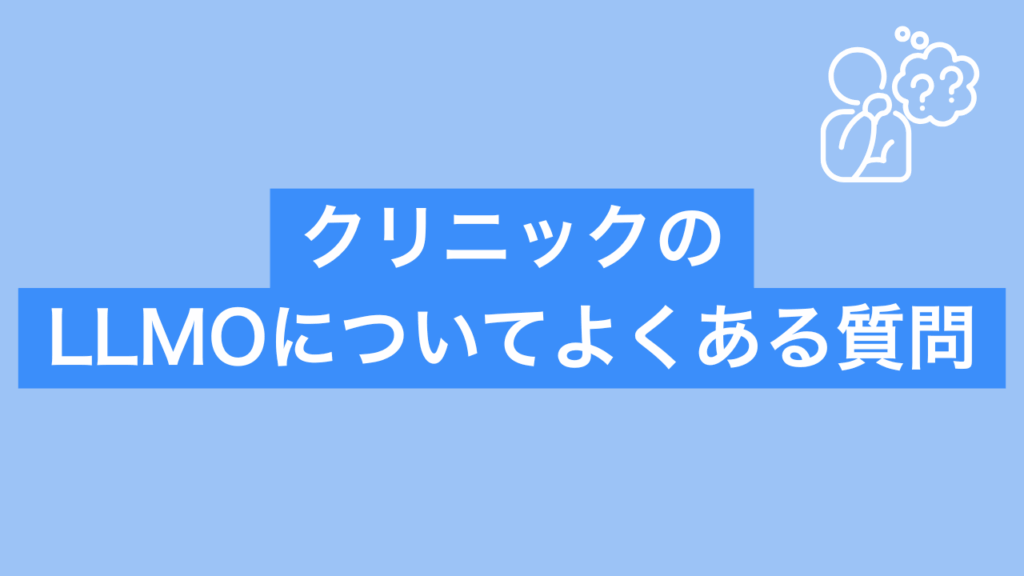
クリニックのLLMOに関するよくある質問と回答をまとめました。
LLMO対策に興味はあるものの、何から始めて良いかわからないという方はぜひ確認してみてください。
クリニックはLLMOを何から始めればいいですか?
まずGoogleビジネスプロフィールの情報を最新化し、診療科目、診療時間、医師情報、アクセス方法を登録しましょう。
Googleビジネスプロフィールの基本情報は、地域や診療科目等、特定の質問に対するAIの回答に引用されやすいです。
患者からのよくある質問を診療科目別に整理し、医療広告ガイドラインに準拠したFAQページを作成しましょう。
どのくらいの頻度で情報を更新すればいいですか?
月に1度、最新の医療技術に関するコンテンツを更新しましょう。
特に、季節性のある疾患(インフルエンザ、花粉症、熱中症など)については、該当時期の2-3ヶ月前から関連情報を更新し、AIが患者質問に対して、自院の情報を引用することを目指しましょう。
どんな情報がAIに引用されやすいですか?
客観的で具体的な数値データと、医学的根拠が明確に示されていることが共通の特徴です。
診療実績を具体的な数値で表現し、医師の専門資格や論文執筆実績などの権威性を示す情報が充実している内容は、AIが信頼できる情報源として優先的に参照する傾向があります。
LLMOやAI検索対策についてさらに詳しく知りたい方は、以下の関連記事もあわせてご覧ください。
クリニックのLLMOの重要性と具体的な実践手順まとめ
本記事では、クリニック向けのLLMO対策の重要性や具体的な施策について解説しました。
従来の検索からAIで検索または質問へと移行する傾向が強まっているため、クリニックにおいてもSEOだけではなくLLMOの対策がより一層重要になってくるでしょう。
「LLMOに取り組みたいが、何から始めればいいかわからない」
「自社サイトがAI検索でどう扱われているか知りたい」
TRILIA株式会社では、SEO・LLMO領域の専門知見と独自のAI分析基盤を活かし、完全成果報酬型のマーケティング支援を提供しています。初期費用0円で、まずは現状の課題整理からお手伝いいたします。