この記事を読んでいるあなたは、
- なぜ今建築業界にLLMO対策が必要なのか知りたい
- 建築業界のLLMO対策の具体的な施策について知りたい
- 建築業界のLLMO対策の注意点について知りたい
このように考えているかもしれません。
この記事では、そんなあなたに「建築業界のLLMO対策の重要性や具体的な施策、注意点」について解説します。
LLMOとは

LLMOは「Large Language Model Optimization(大規模言語モデル最適化)」の略称で、ChatGPTやGemini、Google検索のAI Overviewなどの生成AI検索で、自社の情報を引用や参照してもらいやすくする最適化施策です。
建築業界でも、AI技術を使った情報発信の効率化や競合他社との差別化を図るため、重要な手法になっています。
別名でGEO(Generative Engine Optimization)、AIO(AI Optimization)とも呼ばれますが、現在のところLLMOという名称が広く使われています。
LLMOとSEOの違い
LLMOとSEOの最も大きな違いは最適化の対象にあり、SEOは検索エンジン(GoogleやBing)が対象であるのに対し、LLMOは大規模言語モデル(AI)が対象となっています。
目的についてもSEOがサイトへの直接的なアクセス増加を狙うのに対して、LLMOはAIによる情報提供の中での引用や言及を通じて間接的に認知度や信頼性を高めることを目指します。
成果指標においてもSEOは検索順位や流入数で測定されるのに対し、LLMOは「引用されるかどうか」が重要な成果指標となります。
ただし、AI時代においてはSEOの延長線上にLLMOがあり、両者には重なる部分も多く存在しています。
建築業界にLLMOが重要な理由
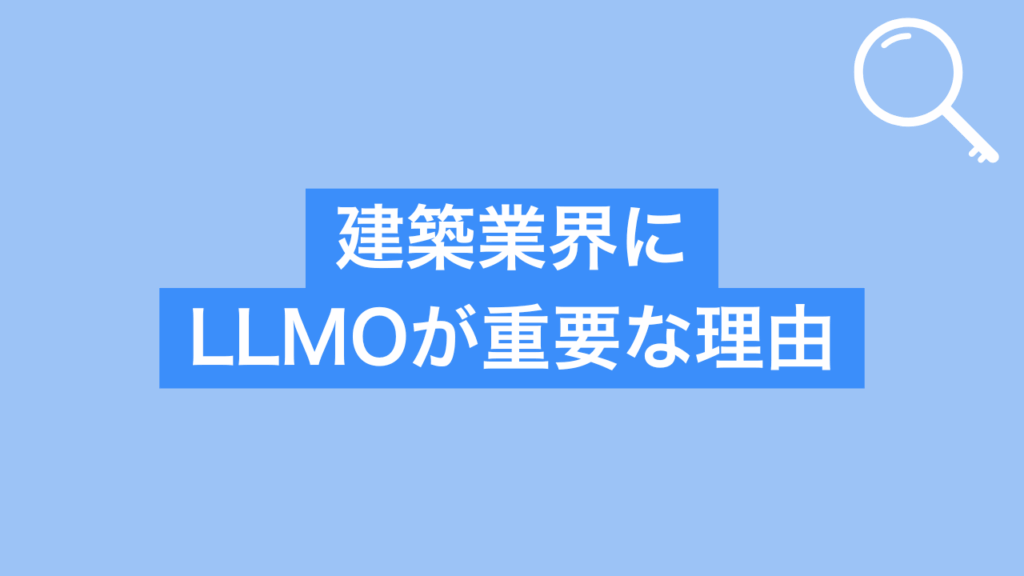
建築業界でLLMOが重要視される背景には、AI検索を利用する施主や発注担当者の増加、AIの回答が検索結果に表示されやすくなった環境変化、そして建築業界でのLLMO導入企業がまだ少ないこと等があります。
建築会社にとって、LLMO対策は競合他社との差別化を図るための重要な戦略と言えるでしょう。
AI検索を利用する施主や発注担当者が増えているから
2022年にChatGPTがリリースされて以降、建設業界でも生成AIの活用が検討されており、一部企業では既に導入が始まっています。
建築業界でもChatGPTをはじめとした生成AIに対する関心を持つ人が多く、情報収集の手段として利用する施主や発注担当者が増えています。
従来のキーワード検索から自然言語で質問し、会話を通じて情報を得るスタイルへの移行が始まっており、建築業界においてもLLMOは必須の対策と言えるでしょう。
AIの回答が検索結果やAIアプリに表示されやすくなっているから
GoogleのAI Overviews機能により、AIが生成した回答が検索結果に表示されるようになり、建築業界の情報もAI検索結果に表示される機会が大幅に増えています。
AI Overviewsは2024年の発表以来、利用者からの満足度が高く、特に米国やインドなどでは広く使われています。
そのため、AIの回答文に自社サイトの情報が引用されれば、新たな流入のきっかけになる可能性が高まっており、建築会社にとって新しい集客チャネルとして注目されています。
建築業界でLLMOを導入している企業がまだ少ないから
建築業界でLLMOを導入している企業はまだ多くないため、早期参入による先行者利益を得られる状況にあります。
建築業界のDXは他の業界より遅れている現状であり、LLMOのような比較的新しい最適化戦略を取り入れることで、競合他社との明確な差別化が図れます。
さらに、人材不足や労働力不足が深刻化する建設業界において、AI技術を活用した情報発信の効率化は、限られたリソースで最大の効果を得るための有効な手段となっています。
建築業界のLLMO施策8選
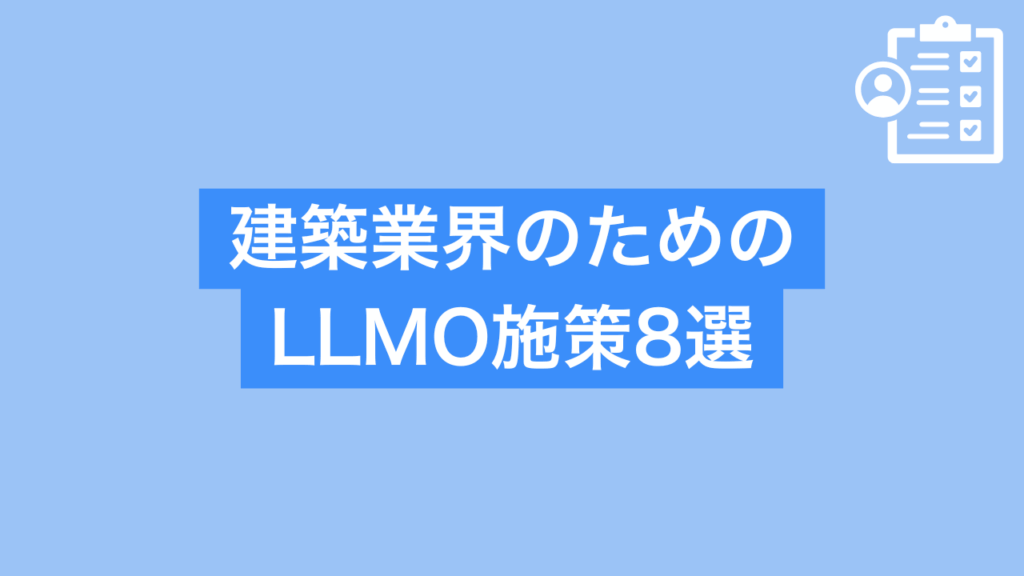
建築業界でLLMOを効果的に実施するためには、工法や用途ごとの事例充実から構造化データ設定まで、8つの具体的な施策があります。
これらの施策を組み合わせることで、AIが建築関連の質問に回答する際に自社の情報が引用される可能性が高くなり、潜在的な施主や発注担当者に対する認知度向上を図ることができます。
工法や用途ごとの事例を充実させる
住宅建築、商業施設、工場建設など用途別の施工事例を詳細に掲載し、木造、鉄骨造、RC造といった工法ごとの特徴や適用場面を具体的に説明することで、AIが建築工法に関する質問に回答する際の情報源として活用されやすくなります。
各事例には建築面積、工期、予算規模、使用建材といった具体的な数値データを含めることで、AIが正確で有用な情報として認識し、引用する可能性が高くなるでしょう。
また、施工プロセスの写真や完成写真を豊富に掲載し、視覚的な情報も充実させることで、AIの画像解析機能にも対応した総合的な情報提供が可能になります。
施工例の図面やBIMの要点について解説する
建築図面の読み方や重要なポイントを分かりやすく解説し、BIM(Building Information Modeling)の活用方法や効果を具体的な事例とともに紹介することで、AIの回答に引用されやすくなります。
特に以下の内容について詳しく解説しましょう。
- 平面図・立面図・断面図の見方や注意点
- 3Dモデリングの詳細
- 設計変更の効率化方法
建材や制度の解説ページを整える
建築基準法や省エネ基準、各種認定制度についての最新情報を整理して提供することで、AIが建材選定や法規制に関する質問に回答する際の信頼できる情報源となります。
断熱材、構造材、仕上げ材それぞれの特性や価格帯、耐用年数を比較表形式で整理し、住宅ローン減税や補助金制度の申請方法や条件を具体的に説明することで、施主が実際に必要とする情報を提供することができます。
見積や依頼の手順を公開する
建築工事の見積依頼から契約、着工までの流れを、段階ごとに分かりやすく説明しましょう。
それぞれの段階で必要となる書類や準備事項を具体的に示すことで、AIが建築依頼の方法について回答を出力する際に引用されやすくなります。
最新の法改正や審査情報を発信する
建築基準法の改正内容や施行日程、確認申請の審査基準変更について、その影響や対応方法を具体的に解説しましょう。
省エネ基準の強化や耐震基準の見直しといった重要な制度変更について、施主や建築業者への影響を分かりやすく説明することで、AIに信用できる情報として認識されます。
施主の声や完成後のレビューを掲載する
実際に建築を依頼した施主からの生の声や評価を詳細に掲載しましょう。
工事中の対応や完成後の満足度、アフターサービスの内容について具体的な体験談を紹介することで、AIが建築会社の評判や実績について回答する際に引用されやすくなります。
なお、問題が発生した場合の対応事例や解決プロセスも偽りなく公開し、誠実な企業姿勢を示すことで、AIが生成する回答の信頼性向上に寄与します。
地域や用途に特化した情報を発信する
地域の気候条件や地盤特性に適した建築手法や建材選定について、詳細に解説しましょう。
地域の建築文化や伝統工法の活用方法、地元の職人技術の継承といった地域密着型の情報も含めることで、他社では提供できない独自性の高い情報源として差別化することができます。
AIに読み取られやすい構造化データを設定する
建築会社の基本情報、サービス内容、施工実績をJSON-LD形式の構造化データとして設定し、AIが企業情報を正確に理解し、引用できるようにしましょう。
以下の内容を設定すると、AI回答に引用されやすくなります。
- 工事の種類
- 対応地域
- 料金体系
- 資格・認定情報
なお、定期的にデータの更新と検証も行い、常に正確で最新の情報を維持することで、AIからの信頼性を高めることができます。
建築業界がLLMOを始める際の注意点
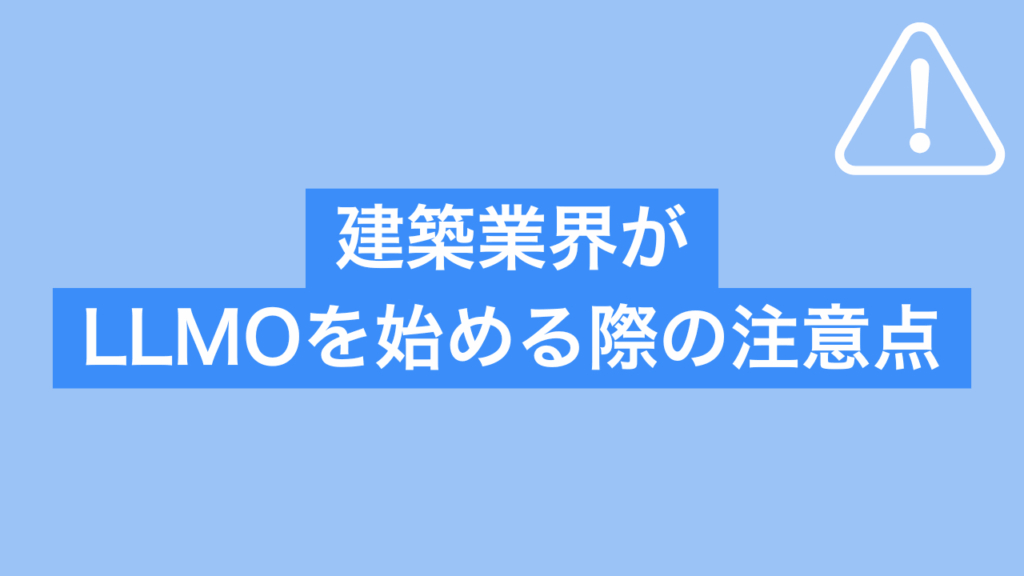
建築業界でLLMOを実施する際には、過度なキーワード最適化を避けて専門性を保持し、法令や根拠に基づいた正確な情報提供を最優先とし、施主目線での分かりやすい表現を心がけることが重要です。
これらの注意点を守ることで、AIからの信頼を獲得しながら、実際の顧客にとって価値のある情報発信が可能になります。
過度なキーワード最適化を避けて専門性を守る
AIは、不自然なキーワードの詰め込みや繰り返しを検出する能力が高いため、建築の専門用語を自然な文脈の中で適切に使い、読み手にとって価値のある情報提供を心がけましょう。
また、AIは文章の品質や有用性を総合的に判断するため、キーワードの量よりも情報の正確性に重点を置いた内容にすることで、長期的な評価向上につなげることができます。
法令や根拠に基づいた正確性を優先する
建築分野では人命や財産に関わる情報を扱うため、建築基準法や建築士法といった関連法令に基づいた正確な情報提供を最優先し、曖昧な表現や推測による記述は避けましょう。
施工方法や建材の性能について記載する際は、公的機関の基準や認定試験の結果、業界団体のガイドラインなど信頼できる根拠を明示し、情報の出典や更新日を明確にすることでAIからの信頼性を高めることができます。
依頼者が分かりやすい表現を心がける
建築の専門知識を持たない施主や発注担当者が理解できるように、専門用語には必要に応じて注釈や解説を加え、複雑な工程や仕組みは図解や事例を用いて視覚的に説明することが重要です。
工事費用や工期の目安、メンテナンス方法など、施主が実際に知りたい情報を重点的に取り上げ、建築業界の慣習や専門的な判断基準についても一般の人が理解しやすい理由とともに説明しましょう。
また、AIが生成する回答を通じて施主の疑問や不安が解消されるよう、よくある質問や心配事に対する丁寧で具体的な回答を準備し、信頼関係の構築につながる情報発信を行うと良いです。
建築業界のLLMOに困ったらまずはプロに相談しましょう
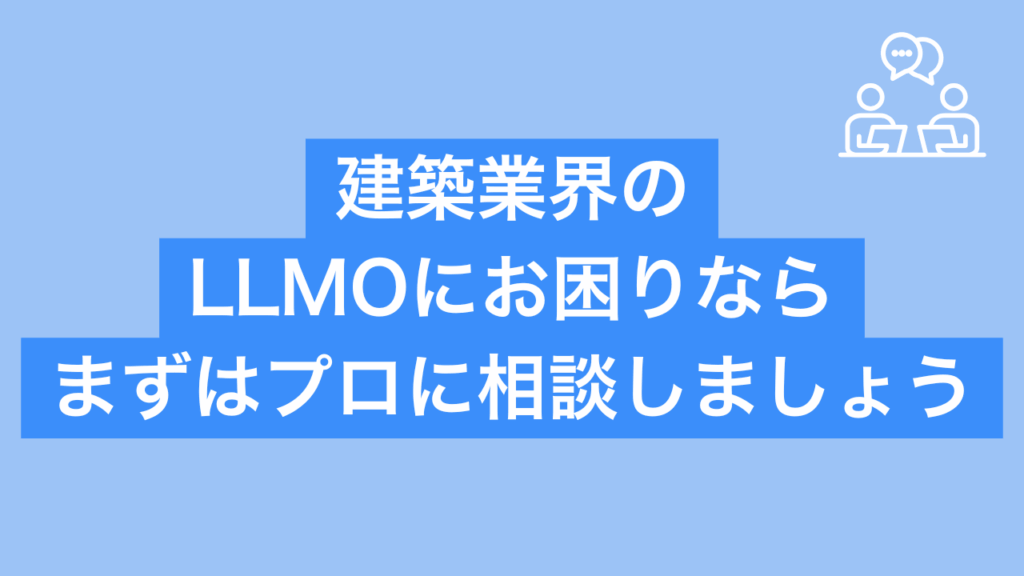
建築業界でのLLMO対策は専門的な知識と継続的な取り組みが必要なため、専門業者に相談することをおすすめします。
専門家は、建築業界特有の法規制や技術的な内容を理解した上で、効果的な最適化戦略を提案し、継続的な運用サポートを提供できるため、限られた時間とリソースで最大の効果を得ることが可能です。
また、専門業者との連携により、自社の強みを活かしながら競合他社との差別化を図り、AI時代の新しい集客チャネルを効果的に活用することができます。
なお、本記事を執筆しているTRILIA株式会社ではメディア運営で培った知見をもとに、LLMOを含むマーケティング支援を行っています。
LLMO対策を進めたいご担当者様は下記からお気軽にお問い合わせください。
建築業界のLLMOについてよくある質問
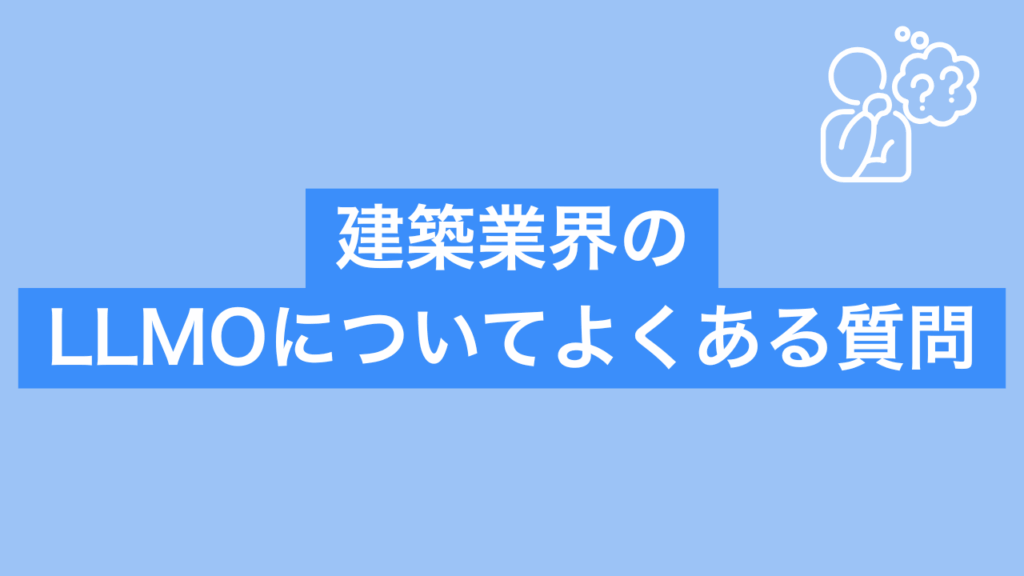
建築業界でLLMOを検討する際によく寄せられる質問として、取り組み開始の方法、コンテンツ更新頻度、SEOとの同時実施の必要性などがあります。
LLMOの導入を検討している場合は、ぜひ確認してみてください。
LLMOは何から取り組めばいいですか?
建築業界でLLMO対策をする場合は、自社の強みや専門分野を明確にし、それに関連するコンテンツの作成から始めることをおすすめします。
工法別の施工事例や建材の特性解説、地域特有の建築課題と解決方法など、AIが建築関連の質問に回答する際に引用したくなる専門性の高い情報を優先的に整備することが効果的です。
どのくらいの頻度でコンテンツを更新すればいいですか?
建築業界のLLMOにおいては、法改正や基準変更など重要な制度変更があった場合はすぐに更新し、施工事例や技術情報については月1回程度の定期的な更新が理想です。
建築基準法の改正や省エネ基準の変更といった法制度に関わる情報は、施主や業界関係者への影響が大きいため、変更内容の詳細と対応方法を速やかに掲載する必要があります。
SEOとLLMOを同時に進める必要はありますか?
SEOとLLMOは最適化の対象が異なりますが、質の高いコンテンツ作成や正確な情報提供といった基本的な要素は共通しているため、同時に進めることで相乗効果を期待できます。
従来のSEO対策で作成した建築関連の詳細なコンテンツは、AIの学習データや引用元としても活用される可能性が高く、既存のコンテンツ資産を有効活用しながらLLMO対策を進めることが効率的です。
ただし、LLMOでは検索順位よりもAIによる引用を重視するため、キーワードの数よりも情報の正確性や網羅性に重点を置いた最適化が必要になり、一部SEOとは異なる視点での対策が必要です。
LLMOやAI検索対策についてさらに詳しく知りたい方は、以下の関連記事もあわせてご覧ください。
建築業界のLLMOの重要性と具体的な実践手順まとめ
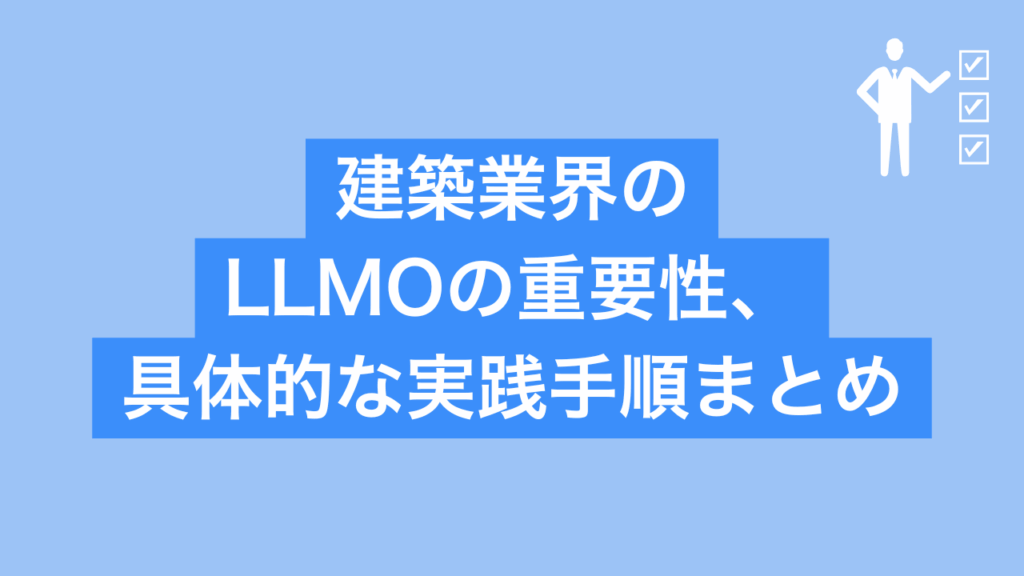
建築業界におけるLLMOは、AI検索を活用する施主や発注担当者の増加に伴い、従来のSEOでは対応しきれない新しいチャネルとして重要性を増しています。
工法や用途別の事例充実、図面やBIMの解説、建材や制度の詳細説明、見積手順の公開など、具体的施策を通じて、AIが建築関連の質問に回答する際の信頼できる情報源となることが可能です。
実施の際は過度なキーワード最適化を避けて専門性を保持し、法令に基づいた正確性を優先し、施主目線での分かりやすい表現を心がけることで、AI時代の新しい集客チャネルを効果的に活用できます。
「LLMOに取り組みたいが、何から始めればいいかわからない」
「自社サイトがAI検索でどう扱われているか知りたい」
TRILIA株式会社では、SEO・LLMO領域の専門知見と独自のAI分析基盤を活かし、完全成果報酬型のマーケティング支援を提供しています。初期費用0円で、まずは現状の課題整理からお手伝いいたします。

