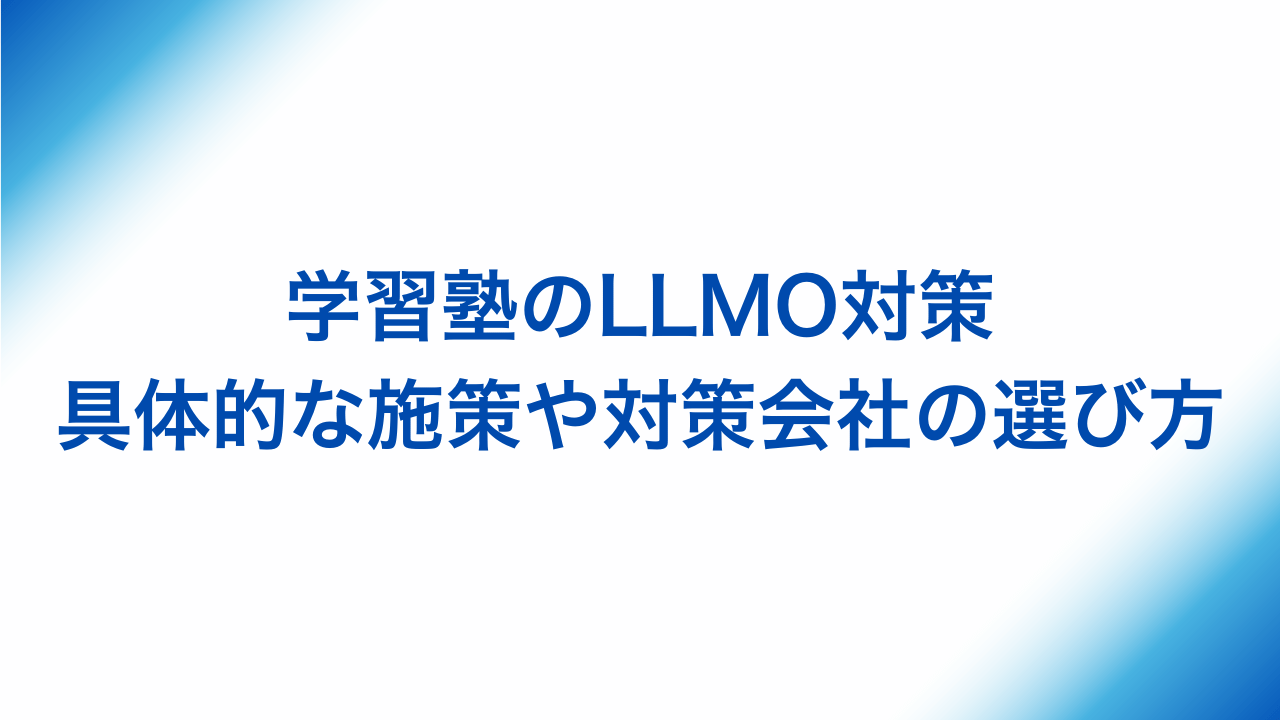この記事を読んでいるあなたは、
- なぜ学習塾にLLMO対策が必要なのか知りたい
- 学習塾のLLMO対策の具体的な施策について知りたい
- 学習塾のLLMO対策の注意点について知りたい
このように考えているかもしれません。
この記事では、そんなあなたに「学習塾のLLMO対策の重要性や具体的な施策、注意点」について解説します。
学習塾のLLMOとは

学習塾のLLMOは、ChatGPTやGeminiといった大規模言語モデルを対象に、AI検索で自塾の情報を優先的に引用してもらう取り組みのことです。
従来の検索エンジン最適化とは異なり、AIが生徒や保護者の質問に答える際、自塾の名称やサイトを引用してくれることを目指します。
生成AIの利用者が急激に増える現在、塾選びの情報収集でもAI検索が一般化しており、この変化に対応した新しいデジタルマーケティング手法として大きな注目を集めています。
LLMOとSEOの違い
LLMOとSEOの根本的な違いは、最適化する対象と目標設定にあります。
SEOは検索エンジンでの上位表示を狙うのに対し、LLMOは生成AIに自塾の情報を引用させることを最重要視します。
具体的に見ると、SEOではキーワード最適化や被リンク獲得が主な施策になりますが、LLMOでは構造化データの整備やE-E-A-T(専門性・権威性・信頼性・経験)の向上が特に重要です。
さらに、SEOはWebサイトへのクリック数増加を狙いますが、LLMOはAIの回答で塾の情報が適切に伝わることを目指しており、利用者の情報収集スタイルの変革に対応した戦略と言えるでしょう。
学習塾にLLMOが重要な理由

学習塾にとってLLMO対策が不可欠な理由は、情報の収集方法の変化が起きているからです。
従来の、検索結果を一つずつ確認する方法から、AIに質問してまとまった回答を求める方法に変わりつつあります。
特に、2024年8月にGoogleのAI Overviewが日本で正式にスタートし、検索結果の最上部にAI生成の要約が表示されるようになりました。
これにより、AI検索で引用されない塾は保護者の選択肢に入らない可能性があり、集客に深刻な影響を与えるかもしれません。
AI検索を利用する生徒や保護者が増えているから
現在、ChatGPTの月間利用者は37億から52億人、Geminiも約2億5000万人に到達しており、教育分野でも情報収集ツールとして定着しています。
保護者が塾を選ぶ際に、「中学受験に強い塾を教えて」「数学が苦手な子におすすめの指導方法は?」といった具体的な質問をAIに投げかけるようになりました。
この流れにより、AIの回答に引用されない塾は、保護者の検討対象から外れる可能性があります。
AI回答が検索結果に表示されやすくなっているから
AI生成の要約表示による、クリック率低下が顕著になっています。
GoogleのAI Overviewが表示される検索では、従来の検索順位1位のクリック率が平均15.5%下落し、非ブランド系検索では19.9%も減少しています。
検索結果の最上部にAI生成の要約が表示されることで、利用者はWebサイトを訪問せずに必要な情報を入手できるようになりました。
特にAI Overviewとリッチスニペットが同時に表示される場合、最大37.4%もクリック率が低下するデータも出ています。
この変化により、検索行動が「検索する」から「AIに聞く」スタイルへ移行し、塾のWebサイトへの直接アクセスが減る傾向にあります。
学習塾業界でLLMOを導入している事例がまだ少ないから
現在、LLMO対策を本格導入している学習塾は極めて少なく、SEO対策と比較すると圧倒的に対応が遅れています。
この状況は先行者利益を獲得する絶好のタイミングと言えるでしょう。
競合が少ない現段階で対策をスタートすれば、自塾のコンテンツがAIに優先的に引用される可能性が高まります。
AIにとって引用先の選択肢が限られている現状では、質の高いコンテンツを提供することで特定分野の標準として認識されやすく、比較的少ない労力でも大きなリターンを狙えます。
学習塾のLLMO施策

学習塾が効果的なLLMO対策を実行するには、AIが理解しやすい情報提供が必要です。
学習塾が効果的なLLMO対策を実行するためには、AIが理解しやすい形で情報を提供し、保護者や生徒の具体的な質問に対応できるコンテンツ作りが欠かせません。
以下に紹介する8つの施策は、AIに正確に情報を伝え、塾選びの際に自塾が推薦されやすくなる具体的な手法です。
これらの施策を組み合わせることで、AI検索での露出度を高め、新規生徒の獲得につなげることができます。
各施策は段階的に実行でき、塾の規模や特色に合わせたカスタマイズも可能です。
学年や科目ごとの事例を充実させる
具体的な指導事例を学年・科目別に整理して公開することが有効です。
AIが塾を推薦する際の重要な判断材料となるのが、具体的な指導事例です。
「小学6年生の算数で図形問題が苦手だった生徒が、どのような指導で改善したか」といった詳細な事例を学年・科目別に整理して公開しましょう。
単に「成績向上」と抽象的に述べるのではなく、「3か月で偏差値が42から58に上がった」「定期テストで30点台だった英語が80点台まで向上した」など数値を含めた具体例が効果的です。
AIは具体性の高い情報を好む傾向があるため、実際の指導プロセスや使用教材、期間なども併せて記載することで引用されやすくなります。
合格実績をデータで示す
合格実績は、データで整理して提示することが重要です。
合格実績は保護者が最も関心を寄せる情報の一つですが、単に学校名を並べるだけでは不十分です。
「過去3年間で○○中学に15名合格、合格率65%」「偏差値50以下から都立上位校への合格者数」など、データに基づいた実績を整理して提示しましょう。
さらに、入塾時の成績レベル別の合格実績や、通塾期間による成果の違いなども併記することで、AIがより具体的な推薦を行えるようになります。
ただし、個人情報に配慮し、生徒を特定できない形でのデータ公開を心がけることが重要です。
学習相談の事例を記事化する
保護者の相談とその回答を匿名化して記事にまとめることが有用です。
保護者から寄せられる学習相談とその回答を記事として公開することで、AIが類似の質問に対して塾を紹介しやすくなります。
「中学生の子どもが勉強に集中できない」「高校受験の志望校選びで迷っている」など、実際に受けた相談内容を匿名化して記事にまとめましょう。
相談内容に対する塾長や講師の具体的なアドバイス、実際に提案した学習プランなどを詳しく記載することで、AIが保護者の悩みに応える際の有益な情報源として認識されます。
定期的な更新により、幅広い学習相談に対応できる塾として位置づけられるでしょう。
学習用語や入試制度をわかりやすく解説する
専門用語や入試制度を初心者向けに説明する記事を充実させることが効果的です。
教育用語や入試制度の解説記事を充実させることで、保護者の疑問に答えるコンテンツとしてAIに活用されやすくなります。
「内申点とは何か」「推薦入試の種類と特徴」「偏差値の計算方法」など、保護者が理解しにくい専門用語を初心者向けに説明しましょう。
また、地域の入試制度や最新の教育改革についても、塾の専門知識を活かした解説を提供することが重要です。
これらのコンテンツは検索頻度が高く、AIが教育情報を提供する際の引用元として選ばれやすいため、塾の認知度向上に大きく貢献します。
入塾手続きの手順を公開する
入塾に関する具体的な手順を、段階別に整理して公開すると利便性が高まります。
入塾を検討している保護者が知りたがる手続きの流れを詳細に公開することで、AIが塾の紹介をする際の補足情報として活用されます。
「体験授業の申し込み方法」「入塾テストの内容と対策」「授業料の支払い方法」など、入塾に関する具体的な手順を段階別に整理しましょう。
特に、他塾との違いや塾独自の特色ある手続きがある場合は、詳しく説明することでAIが差別化要因として認識しやすくなります。
透明性の高い情報提供は保護者の信頼獲得にもつながり、最終的な入塾決定を後押しする効果も期待できます。
最新の入試情報や教育制度の更新を継続して発信する
教育制度の変更や入試情報をタイムリーに発信し続けることが重要です。
教育制度の変更や入試情報の更新を継続的に発信することで、AIが最新情報を求める質問に対して塾を引用する機会が増えます。
「2024年度高校入試の変更点」「新学習指導要領の影響」「大学入学共通テストの最新動向」など、タイムリーな教育情報を専門的な観点から解説しましょう。
情報の更新頻度が高く、正確性が保たれているコンテンツは、AIにとって信頼できる情報源として評価されます。
また、地域特有の入試情報や説明会の日程なども併せて提供することで、地域密着型の塾として認識されやすくなります。
保護者の声や成功事例を掲載する
保護者の声や成功事例を匿名で掲載して信頼を示すことが有効です。
実際に通塾した生徒の保護者からの声や成功事例を掲載することで、塾の教育効果をAIに具体的に伝えることができます。
「子どもの学習習慣が身についた」「苦手科目を克服できた」といった保護者のコメントに加えて、具体的な成果や変化の過程も記載しましょう。
ただし、プライバシーに配慮し、保護者の同意を得た上で匿名または仮名での掲載を行うことが重要です。
これらの生の声は、AIが塾の実績や特色を判断する際の重要な材料となり、類似の状況で悩む保護者への推薦理由として活用されます。
AIに読み取られやすい構造化データを設定する
塾の基本情報を構造化データで整理して埋め込むことが推奨されます。
塾の基本情報や授業内容を構造化データとして設定することで、AIが情報を正確に理解し、適切な場面で引用できるようになります。
塾名、所在地、開講科目、対象学年、授業形式、料金体系などを標準的な形式で整理し、Webサイトに埋め込みましょう。
また、FAQ形式での情報提供や、見出しタグの適切な使用により、AIが内容を理解しやすい構造を作ることも重要です。
これにより、「地域名+個別指導塾」「科目名+苦手克服」といった具体的な検索に対して、塾が適切に紹介される可能性が高まります。
学習塾のLLMOの効果測定

LLMO施策の効果を正確に測定するためにはAI検索特有の指標が必要です。
LLMO施策の効果を正確に測定することは、継続的な改善と投資対効果の判断に不可欠です。
従来のSEO効果測定とは異なる指標や手法が必要となるため、AI検索での露出度や利用者の行動変化を多角的に分析する必要があります。
効果測定により、どの施策が最も効果的かを判断し、限られたリソースを最適に配分することができます。
また、定期的な測定結果を基に戦略を調整することで、競合他塾との差別化を維持し続けることが可能になります。
AI回答での確認
主要な生成AIに対して定期的に質問を投げて引用を確認することが基本です。
ChatGPTやGemini、Copilotなどの主要な生成AIに対して、塾に関連する質問を投げかけ、自塾が引用されているかを定期的に確認しましょう。
「○○地域でおすすめの学習塾は」「中学受験に強い塾を教えて」といった具体的な質問を行い、回答内容を記録することが重要です。
月1回程度の頻度で同じ質問を繰り返し、引用される頻度や内容の変化を追跡します。
また、異なる表現で同様の質問をすることで、より幅広い検索パターンでの露出度を測定できます。
引用されていない場合は、どの競合塾が紹介されているかも併せて分析し、自塾のコンテンツ改善に活用しましょう。
ChatGPT検索での確認
ChatGPTの検索機能を使ってリアルタイム情報での言及を確認することが有効です。
ChatGPTの検索機能を活用して、リアルタイムのWeb情報を基にした回答での塾の言及を確認します。
通常のChatGPTでの回答と検索機能を使った回答では、引用される情報源が異なる場合があるため、両方での確認が必要です。
「最新の○○塾の合格実績」「2024年度の塾の授業料比較」など、時事性のある質問を中心に調査を行いましょう。
検索機能付きのAI回答では、具体的な情報源も表示されるため、自塾のどのページが引用されているかも把握できます。
この情報を基に、よく引用されるページの特徴を分析し、他のページの改善に活用することが効果的です。
AI経由のアクセス数の分析
AI経由の流入をアクセス解析で識別して変化を追跡することが重要です。
Webサイトのアクセス解析において、AI経由の流入を識別し、その変化を追跡することでLLMO効果を定量的に測定します。
Google AnalyticsやSearch Consoleで「ai overview」「chatgpt」「perplexity」などの参照元を確認し、AI検索からの流入数を把握しましょう。
また、AIが引用しやすいページと実際にアクセスが増加したページの相関関係を分析することで、効果的なコンテンツの特徴を見出すことができます。
流入数の変化と併せて、AI経由の利用者の行動パターン(滞在時間、ページビュー数、問い合わせ率など)も分析し、質の高いアクセスが増加しているかを確認することが重要です。
学習塾がLLMOを始める際の注意点
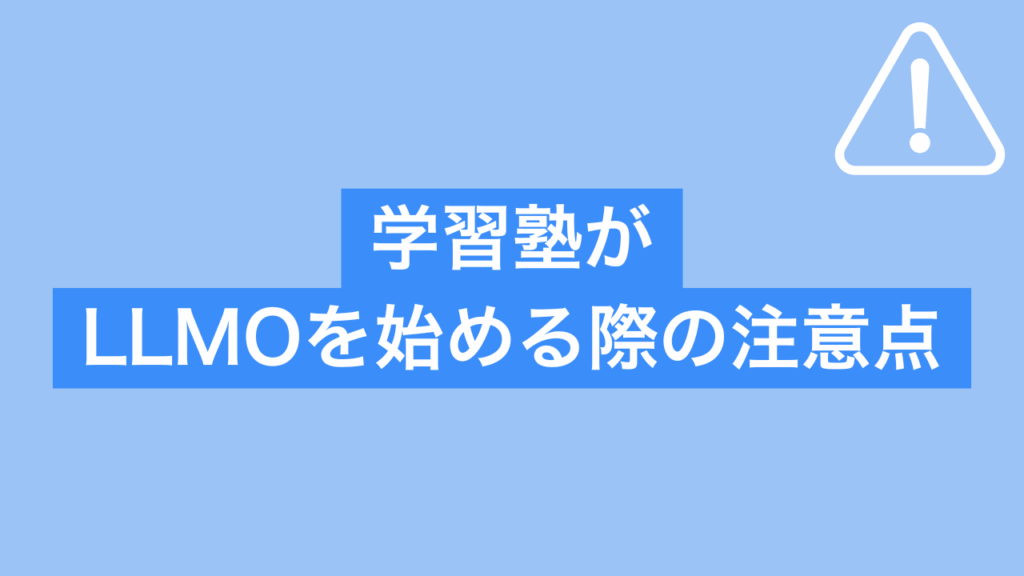
LLMO対策を行う際は教育者としての責任を持ちつつ実施することが求められます。
学習塾がLLMO対策を実行する際には、教育業界特有の注意点を理解して取り組むことが重要です。
単にAIに引用されることを目指すだけでなく、塾としての専門性と信頼性を維持しながら最適化を行う必要があります。
間違った手法を用いると、かえって塾の評判を損なったり、保護者からの信頼を失ったりするリスクがあります。
以下の注意点を守ることで、効果的かつ持続可能なLLMO戦略を実行できるでしょう。
教育者としての責任を持ちながら、デジタルマーケティングの効果も追求するバランスが求められます。
専門性を損なう過度なキーワード最適化を避ける
教育内容の専門性を犠牲にする過度な最適化は避けるべきです。
LLMO対策においてキーワードの使用は重要ですが、教育内容の専門性を犠牲にしてまで最適化を行うことは避けなければなりません。
「受験対策」「成績向上」といったキーワードを過度に詰め込むと、文章が不自然になり、かえってAIからの評価が下がる可能性があります。
塾の指導方針や教育理念を正確に伝えることを最優先とし、自然な文脈でキーワードを使用することが重要です。
また、競合他塾との差別化を図るために、独自の指導法や教材について具体的に説明することで、専門性の高いコンテンツとしてAIに認識させることができます。
教育法規や根拠に基づいた正確性を優先する
教育法規や公式発表に基づいた正確な情報提供を行う必要があります。
学習塾が提供する情報は、生徒の進路や学習に直接影響を与えるため、教育法規や客観的な根拠に基づいた正確な内容でなければなりません。
入試制度や学習指導要領に関する情報は、文部科学省や各都道府県教育委員会の公式発表を基に作成し、推測や憶測に基づく記述は避けましょう。
また、合格実績や指導効果についても、事実に基づいた範囲での記載にとどめ、誇張した表現は使用しないことが重要です。
正確性の高い情報を継続的に提供することで、AIからも信頼できる情報源として評価され、長期的なLLMO効果を期待できます。
保護者の立場から見て分かりやすい表現を心がける
保護者が理解しやすい表現と構造化された情報提供を心がけることが大切です。
LLMO対策では、AIが理解しやすい構造化された情報提供が重要ですが、最終的な読み手は保護者であることを忘れてはいけません。
教育専門用語や業界特有の表現は、必要に応じて補足説明を加え、保護者が理解しやすい言葉に置き換えて使用しましょう。
「内申点の向上により推薦入試での合格可能性が高まる」といった専門的な内容も、具体例や数値を交えて分かりやすく説明することが重要です。
保護者の視点に立ったコンテンツ作りにより、AIが適切に情報を要約して提供できるようになり、最終的に塾への問い合わせや体験授業の申し込みにつながりやすくなります。
学習塾向けのLLMO対策会社の選び方
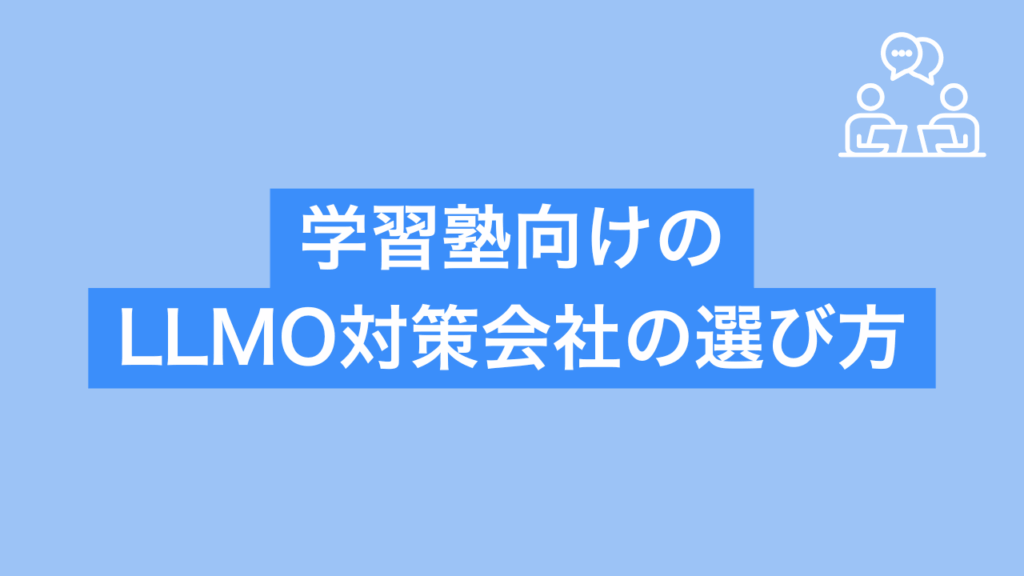
教育業界の特殊性を理解できる対策会社を選定することが重要です。
学習塾のLLMO対策を外部に依頼する場合、教育業界の特殊性を理解し、適切なサポートを提供できる会社を選ぶことが重要です。
LLMO自体が新しい分野のため、実績や専門性を慎重に見極める必要があります。
また、塾の規模や特色に合わせたカスタマイズされたサービスを提供できるかも重要な判断基準となります。
以下の選び方のポイントを参考に、塾の成長に真に貢献できるパートナーを見つけましょう。
適切な対策会社との協力により、効率的かつ効果的なLLMO施策を実現できます。
複数社に問い合わせる
最低でも複数社に問い合わせて提案内容を比較することを推奨します。
LLMO対策会社を選ぶ際は、必ず複数の会社に問い合わせを行い、提案内容やサービス内容を比較検討しましょう。
各社のLLMOに対する理解度や教育業界での経験、具体的な施策提案を聞くことで、塾に最適なパートナーを見つけることができます。
特に、学習塾特有の課題(季節性のある集客、地域密着性、教育法規への対応など)を理解しているかを確認することが重要です。
また、担当者の対応の質や提案の具体性、質問への回答の的確さなども、今後の協力関係を築く上で重要な判断材料となります。
最低でも3社程度は比較し、塾の方針に最も合致する会社を選択しましょう。
費用やサポート体制を確認する
費用体系と含まれるサポート範囲を詳細に確認することが必要です。
LLMO対策の費用体系とサポート体制について詳細に確認し、塾の予算と必要なサポートレベルに合致するかを判断しましょう。
月額固定制、成果報酬制、初期設定費用など、各社で異なる料金体系があるため、自塾の状況に最適なプランを選択することが重要です。
また、コンテンツ作成、効果測定、定期報告、戦略見直しなど、どこまでのサポートが含まれているかも確認が必要です。
緊急時の対応体制や担当者の変更時の引き継ぎ方法、契約期間や解約条件なども事前に確認し、長期的な協力関係を前提とした契約を結びましょう。
LLMO診断を依頼する
本格契約前に診断を依頼して提案力を確認することが賢明です。
本格的な契約前に、現在の塾のWebサイトやコンテンツに対するLLMO診断を依頼し、対策会社の分析力と提案力を確認しましょう。
診断では、AI検索での現在の露出状況、コンテンツの構造化データ対応状況、競合他塾との比較分析などが含まれるべきです。
診断結果を基にした具体的な改善提案や優先順位の設定、期待できる効果の予測などが示されることで、その会社の専門性と実行力を判断できます。
無料診断を提供している会社も多いため、複数社の診断を受けることで、自塾の現状をより客観的に把握し、最も効果的な改善案を提示する会社を選択することが可能になります。
学習塾のLLMOにお困りならまずはプロに相談しましょう
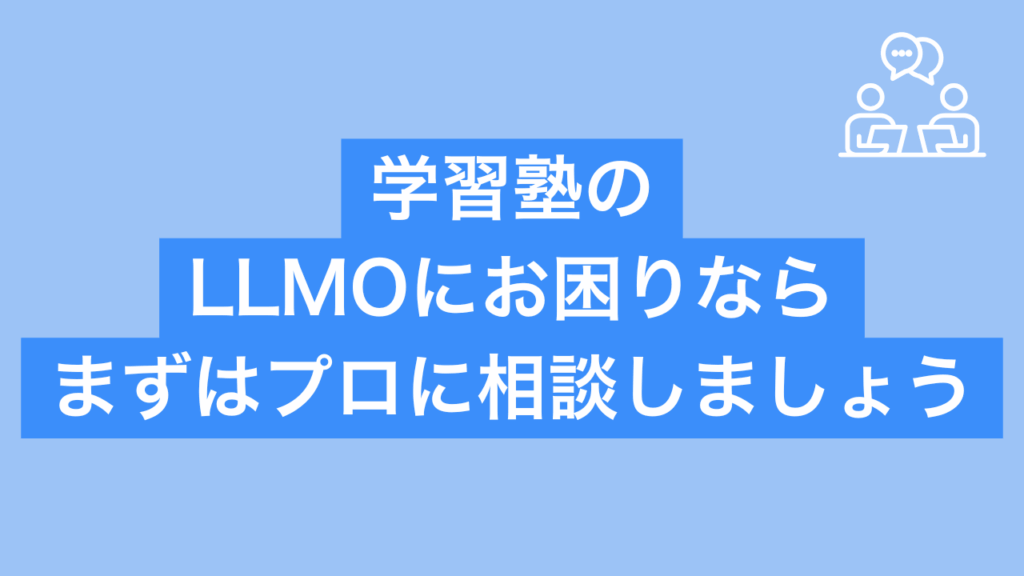
LLMO対策では、専門的な知識と継続的な取り組みが必要なため、プロに相談することをおすすめします。
AIの技術革新が急速に進む中で、効果的な対策を独学で行うには多大な時間と労力を要します。
プロのサポートを受けることで、限られたリソースを最大限に活用し、競合他塾に先駆けてLLMO対策を成功させることができます。
まずは現状の分析から始め、塾の特色を活かした最適な戦略を立てることが重要です。
なお、TRILIA株式会社ではメディア運営で培った知見をもとに、LLMOを含むマーケティング支援を行っています。
LLMOの導入を検討中の方は、ぜひ下記からお気軽にご相談してください。
学習塾のLLMOについてよくある質問
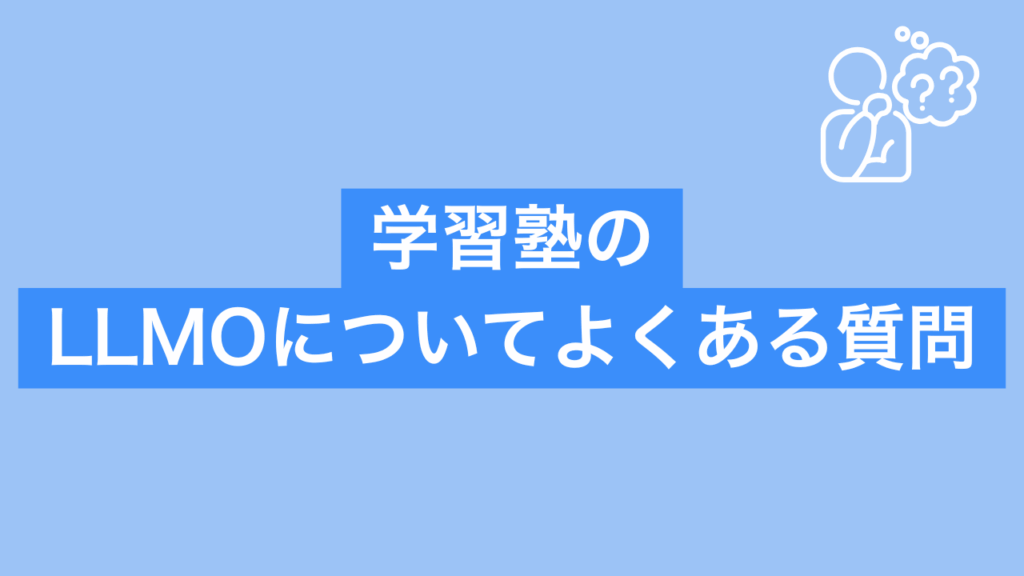
経営者や担当者の疑問に答えるQ&Aを用意しておくことが役立ちます。
学習塾の経営者や担当者からLLMOに関して寄せられる質問をまとめました。
これらの質問と回答を通じて、LLMO対策の具体的な実行方法や効果について理解を深めていただけます。
実際の取り組みを始める前の不安や疑問の解消に役立てください。
また、これらの情報をもとに、塾の現状に合わせたLLMO戦略を検討する際の参考としてもお役立ていただけます。
学習塾がLLMOを始めるには何から取り組めばいいですか?
まずは現状のAI検索での表示状況を確認することから始めると良いです。
学習塾がLLMOをスタートする際は、まず現在の塾の情報がAI検索でどのように表示されているかを確認することから始めましょう。
ChatGPTやGeminiに「○○地域の学習塾でおすすめは」と質問し、自塾が言及されているかをチェックします。
次に、塾の基本情報(所在地、開講科目、指導方針、合格実績など)を構造化データとして整理し、Webサイト上で分かりやすく表示することが重要です。
同時に、保護者からよく受ける質問とその回答をFAQ形式でまとめ、具体的な指導事例や成功体験を記事として公開することで、AIに引用されやすいコンテンツを積み上げていきます。
どのくらいの頻度でコンテンツを更新すればいいですか?
月に2~4回程度の定期更新が維持に有効です。
LLMO効果を維持するためには、月に2~4回程度の定期的なコンテンツ更新が推奨されます。
特に入試制度の変更や最新の教育動向に関する情報は、タイムリーな更新が重要です。
合格実績は年度ごと、定期テスト対策情報は各学期前、季節講習の案内は該当時期に合わせて更新しましょう。
また、保護者からの新しい相談事例や指導の成功事例があれば、個人情報に配慮した形で随時追加することで、コンテンツの鮮度と量を維持できます。
AIは更新頻度の高いサイトを信頼できる情報源として評価する傾向があるため、計画的な更新スケジュールを立てて継続することが重要です。
AIに引用されやすい学習塾の情報にはどんな特徴がありますか?
具体性と数値的根拠を含む情報が引用されやすいです。
AIに引用されやすい学習塾の情報には、具体性と数値的根拠があることが最も重要な特徴です。
「成績向上」という抽象的な表現ではなく、「偏差値45から60への向上」「3か月で英語の点数が30点アップ」といった具体的な数値を含む情報が好まれます。
また、「中学3年生の数学で図形問題を苦手とする生徒に対し、視覚的教材を用いて指導した結果、模試での正答率が30%から80%に改善」のように、対象・問題・手法・結果が明確に示された事例も引用されやすくなります。
さらに、FAQ形式での情報提供や、見出しタグを適切に使用した構造化されたコンテンツも、AIが理解しやすい情報として評価されます。
SEOとLLMOを同時に進める必要はありますか?
両方を並行して進めるのが理想だが、優先順位の付け方が重要です。
SEOとLLMOは目的と手法が異なるため、理想的には両方を同時に進めることが望ましいです。
SEOは検索エンジンでの上位表示を目指し、LLMOはAIに引用されることを目的としますが、質の高いコンテンツ作成という点では共通しています。
リソースが限られている場合は、LLMOを優先することをおすすめします。
なぜなら、現在のAI検索の急速な普及により、従来の検索結果からのクリック率が大幅に減少しているためです。
LLMO対策で作成したコンテンツは、SEO効果も併せ持つことが多いため、まずはLLMOに集中し、その後段階的にSEO特有の施策(被リンク獲得など)を追加していく戦略が効率的といえます。
LLMOの効果はどのくらいで表れますか?
LLMO対策の効果が表れる期間は、対策内容と競合状況により大きく異なりますが、一般的には3~6か月程度で初期効果が出ることが多いです。
構造化データの設定や基本的なコンテンツの充実は比較的早く効果が表れ、1~2か月でAI検索での言及が始まることもあります。
ただし、安定した引用を得るためには継続的なコンテンツ更新と改善が必要であり、本格的な効果を実感するまでには半年から1年程度かかる場合もあります。
競合が少ない地域や特定の分野では、より早期に効果を実感できる可能性が高く、逆に競合が多い地域では時間がかかる傾向にあります。
月1回程度の効果測定により進捗を確認し、必要に応じて戦略を調整することが重要です。
LLMOやAI検索対策についてさらに詳しく知りたい方は、以下の関連記事もあわせてご覧ください。
学習塾のLLMOの重要性と具体的な実践手順まとめ
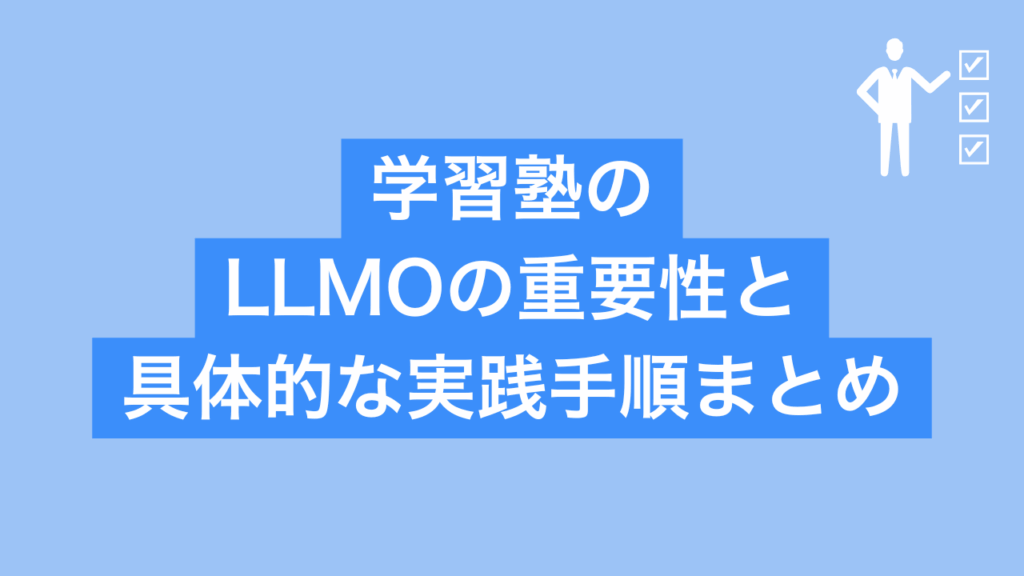
LLMO対策は、専門性と信頼性を維持しつつ継続的に取り組むことが大切です。
学習塾におけるLLMO対策は、保護者や生徒の情報収集方法の変化に対応するために必要不可欠と言えるでしょう。
AI検索の普及により、従来の検索結果に依存した集客方法では限界があり、AI回答で引用される塾とそうでない塾の間で大きな差が生まれています。
効果的なLLMO施策により、競合他塾より早期に対策を講じることで、地域での認知度向上と新規生徒獲得につながります。
重要なのは、単にAIに引用されることを目指すのではなく、教育者としての専門性と信頼性を維持しながら、保護者のニーズに応える質の高い情報提供を継続することです。
今後もAI技術の進化に合わせて戦略を調整し、持続可能なデジタルマーケティング戦略としてLLMOを活用していくことが、学習塾の長期的な成功につながるでしょう。
「LLMOに取り組みたいが、何から始めればいいかわからない」
「自社サイトがAI検索でどう扱われているか知りたい」
TRILIA株式会社では、SEO・LLMO領域の専門知見と独自のAI分析基盤を活かし、完全成果報酬型のマーケティング支援を提供しています。初期費用0円で、まずは現状の課題整理からお手伝いいたします。