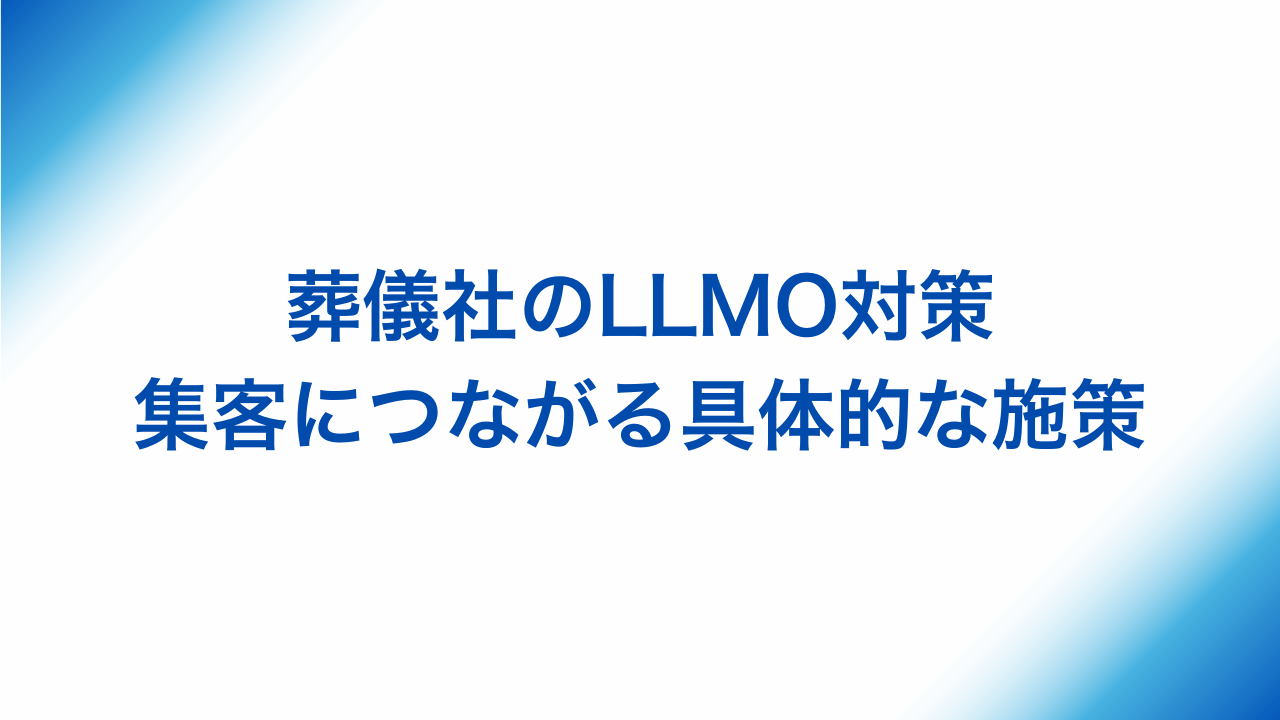この記事を読んでいるあなたは、
- なぜ葬儀社にLLMO対策が必要なのか知りたい
- 葬儀社のLLMO対策の具体的な施策について知りたい
- 葬儀社のLLMO対策の注意点について知りたい
このように考えているかもしれません。
この記事では、そんなあなたに「葬儀社のLLMO対策の重要性や具体的な施策、注意点」について解説します。
葬儀社のLLMOとは

葬儀社におけるLLMOとは、ChatGPTやGemini、Google検索のAI Overviewなどの生成AIが回答を作る際に、自社の葬儀サービスや情報が引用されやすくなる取り組みのことです。
LLMOはGenerative Engine Optimization(GEO)やAI Optimization(AIO)とも呼ばれ、喪主や遺族が生成AIで葬儀について質問した時に、適切で信頼できる葬儀社として紹介されることを目指します。
従来のように自社サイトへの誘導を重視するのではなく、AI回答内で正確に言及され、相談者に選ばれる葬儀社として認知されることが主な目的となります。
LLMOとSEOの違い
LLMOの目的は、自社の葬儀サービス情報を正しく引用させることですが、SEOはGoogle検索で上位表示を狙うことが目的です。
SEO対策では、検索キーワードを意識した文章作成や内部リンク設計、被リンク獲得が主要施策となりますが、LLMO対策では葬儀社の基本情報整理や構造化データ実装、明確で簡潔な情報の整理がメインになります。
また、SEOではユーザーを自社サイトに誘導することを重視しますが、LLMOはAIの回答内で適切に言及されることを重視し、喪主が葬儀社選びで迷った際にAIから推薦される状況を作り出すことも大きな違いです。
葬儀社にLLMOが重要な理由
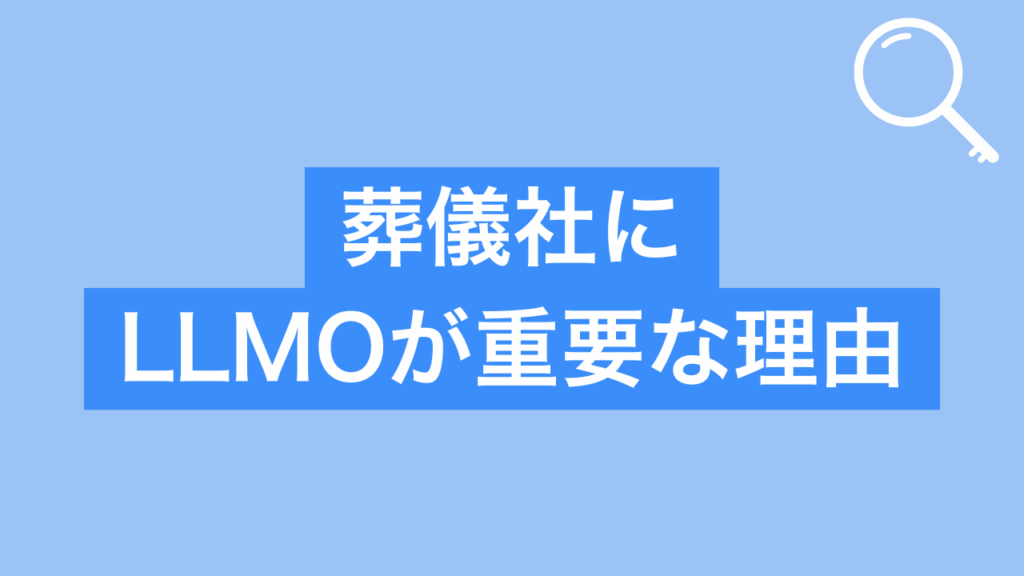
葬儀社にLLMO対策が必要な理由は、喪主や遺族が葬儀についての調べ方が従来と比べて変わってきているからです。
Gartner社の2024年2月の予測によると、2026年までに従来の検索ボリュームが最大25%減少すると見込まれており、ユーザーは複数サイトを回遊するのではなく、生成AIに直接質問して回答を得る傾向が強まるとのことです。
葬儀という人生の重要な局面において、AI回答で適切に紹介される葬儀社とそうでない葬儀社では、今後の問い合わせ件数に大きな差が生まれる可能性があります。
AI回答が検索画面の上部に表示されやすくなっているから
AI Overviewとは、検索結果の上部にAIによる回答を表示する機能で、ユーザーが最も見やすい位置に掲載されます。
Ahrefsの調査によると、AI Overviewの表示により上位表示サイトのクリック率が34.5%も減少しており、従来のSEO対策だけでは集客効果が薄れていることが明らかになっています。
葬儀社の場合、「葬儀費用 相場」「家族葬 流れ」といった検索でAI回答に自社情報が引用されれば、喪主が最初に目にする情報として強いインパクトを与えられます。
そのため、相談につながる可能性が大幅に向上するでしょう。
相談者と家族がAIに質問する機会が増えているから
調べものをする際に生成AIを利用すると回答したユーザーは28.7%に達しており、葬儀という緊急性の高い場面でも同様の傾向が見られます。
また、73%の企業がChatGPTやClaudeを情報収集に使用しており、葬儀社への相談前にAIで基礎知識を得る喪主や遺族が増加しています。
突然の訃報で混乱している状況では、複数の葬儀社サイトを比較検討する時間的余裕がないため、AIから「信頼できる葬儀社」として紹介されることが、相談機会獲得の重要な要因となっています。
YMYL分野でE-E-A-Tの評価が強まっているから
葬儀はYour Money or Your Life(YMYL)分野に該当するため、GoogleはE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の評価を特に厳格に行っています。
生成AIも同様の基準で情報を評価するため、葬儀ディレクターの資格や経験、施行実績、正確な料金の記載など、信頼性の高い葬儀社ほどAI回答で引用されやすくなります。
逆に曖昧な表現や根拠不明な情報を掲載している葬儀社は、AIから信頼性が低いと判断され、回答として引用されにくくなる恐れがあります。
葬儀社のLLMO施策

葬儀社向けのLLMO施策では、生成AIが自社情報を正確に理解し引用できるよう、AIが理解しやすい形式で情報をまとめましょう。
喪主が葬儀について質問した際にAIが自社の情報を引用するように、料金体系や施行の流れ、スタッフの資格など、重要な情報をまとめましょう。
プラン内容と追加費用のFAQを作る
喪主が最も不安に感じる「追加費用の発生」について、明確なFAQを作成することで、AIが正確な情報を引用できるようになります。
基本プランに含まれる内容と別途費用が発生するオプション、想定される総費用の範囲を具体的に記載し、「○○の場合は追加で△万円」といった具体例を含めることが重要です。
また、見積もり後の変更可能範囲や支払いタイミングなど、契約に関わる詳細も併せて記載することで、AIが喪主の疑問に対してまとまった回答を作れるようになります。
顧客の疑問に対して丁寧な回答を作成することで、信頼できる葬儀社として紹介される可能性が高くなります。
葬儀ディレクターの経歴と資格を掲載する
葬儀ディレクターの資格取得年、実務経験年数、担当した葬儀件数などの具体的な情報を掲載することで、専門性と信頼性をAIに伝えることができます。
特に、厚生労働省認定の葬祭ディレクター技能審査の1級・2級の取得状況、所属する葬祭関連団体、研修受講歴なども併せて記載すると良いでしょう。
スタッフ個人の経歴だけでなく、葬儀社としての創業年数や累計施行件数、地域での実績なども明示することで、AIが「経験豊富で信頼できる葬儀社」として判断し、回答として引用される可能性が高くなります。
施行事例は表示ルールに沿って記載する
遺族のプライバシーを保護しつつ、具体的で参考になる施行事例を記載することが重要です。
以下の内容を必ず匿名化して記載しましょう。
- 故人の年齢や性別
- 葬儀形式
- 参列者数
- 斎場
- 総費用
具体的に記載することにより、似たような状況の喪主への参考情報として、AIから引用される可能性が高くなります。
料金と自治体費用の目安をわかりやすく示す
葬儀費用の内訳を明確に区分し、葬儀社への支払い分と火葬場や霊園などの自治体施設利用料を分けて表示することで、喪主が予算を把握しやすくなります。
基本料金、オプション料金、自治体費用のそれぞれについて具体的な金額範囲を示し、地域の相場との比較も併せて記載することが効果的です。
支払い方法や分割払いの可否、葬祭費給付金の申請サポートなども含めることで、AIが費用に関する包括的な情報を提供できるようになります。
その結果、料金面での不安を抱える喪主に対して信頼できる情報源として紹介される可能性が高まります。
相談から施行までの流れと連絡方法を公開する
相談から施行までの詳細な流れを時系列で記載することで、AIが正確な情報を引用できるようになります。
24時間対応の有無、初回相談の方法(電話・メール・来店)、見積もり提示までの時間、契約から施行までの準備期間など、各段階での所要時間と必要な手続きを具体的に記載しましょう。
Googleビジネスプロフィールを最新化する
Googleビジネスプロフィールの情報を定期的に更新し、営業時間、連絡先、サービス内容、写真などを最新状態に保つことで、AIが正確な情報を参照できるようになります。
特に葬儀社の場合は、24時間対応の有無、対応可能な葬儀形式、料金の目安、アクセス方法などの基本情報を詳細に記載することが重要です。
また、顧客からの口コミに対する丁寧な返信や、新しいサービスの追加情報なども随時更新することで、AIに詳細に情報を伝えることができます。
構造化データを実装する
JSON-LD形式の構造化データを実装することで、葬儀社の基本情報、提供サービス、料金、営業時間などをAIが情報を理解しやすくなります。
特にLocalBusiness、Service、FAQPageなどのスキーママークアップを適用し、葬儀社としての事業内容、対応地域、連絡先情報を明確に定義することが効果的です。
しかし、構造化データの実装には専門的な知識が必要になるため、独学で進めるのは相当に難易度が高いと言えます。
llms.txtの導入を検討する
llms.txtは、生成AIに効率的に情報を伝えられるように、サイトの主要コンテンツを要約したテキストファイルです。
葬儀社の基本情報、主要サービス、料金体系、連絡先、よくある質問への回答などを簡潔にまとめ、サイトルートに配置することで、AIのクローリング効率が向上すると言われています。
ただし、llms.txtは比較的新しいテキストファイルであり、その効果に対しては確実な言及がないため、導入前に最新の情報を確認しましょう。
コラムで一次情報を引用して解説する
葬儀に関する法規制、厚生労働省のガイドライン、葬祭業界の統計データなどの一次情報を引用し、解説したコンテンツを作成することで、AIから信頼されるようになります。
例えば、葬祭費給付金の支給条件、埋葬許可証の取得手続き、宗教別の葬儀マナーなど、喪主が疑問に思いやすい内容について、公的機関の情報を基に正確で詳細な解説をしましょう。
単なる一般論ではなく、実際の業務経験に基づく具体的なアドバイスも加えることで、AIが「専門性と信頼性の高い情報源」として認識し、類似の質問に対する回答で引用される機会が増えます。
口コミに丁寧に返信する
口コミに対して、丁寧な返信を行うことで、AIが葬儀社の顧客対応を評価する際の参考情報となります。
感謝のコメントには心からの謝意を示し、改善提案については具体的な対応策を回答し、誤解が生じている場合は事実に基づいた説明を行うなど、一貫性のある対応を心がけましょう。
葬儀社のLLMOの効果測定
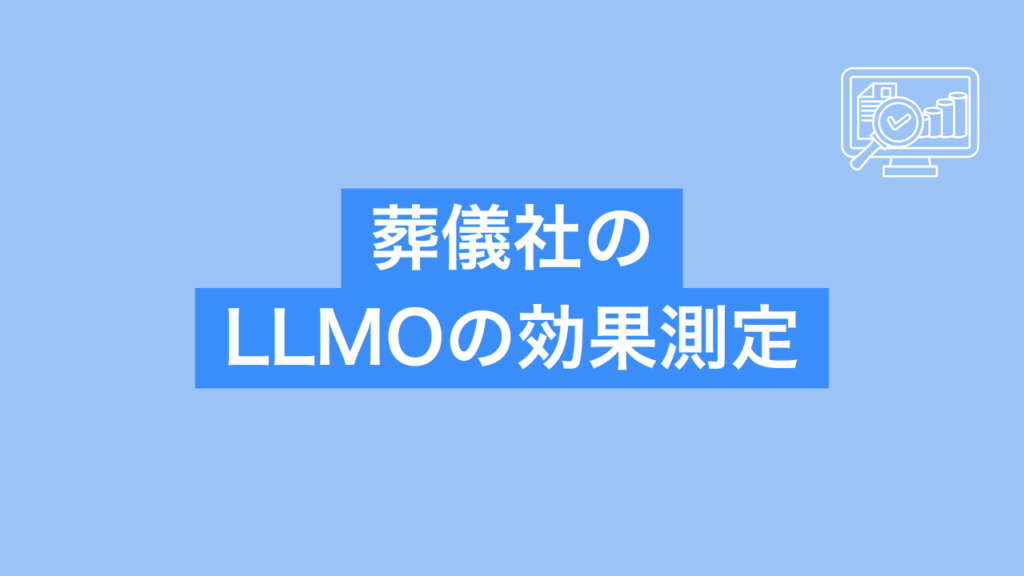
LLMOの効果測定は、AI回答での引用状況や引用実績を直接確認しましょう。
生成AIは、回答作成の際にリアルタイムで情報を取得するため、タイミングによって引用率に差があります。
また、問い合わせ内容の分析や顧客アンケートなどの間接的な方法も組み合わせる必要があります。
実際にAIで検索してみる
ChatGPTやGeminiなどの主要な生成AIサービスに対して、葬儀関連の質問を定期的に投げかけ、自社が言及されるかを確認してみましょう。
「○○市 葬儀社 おすすめ」「家族葬 費用 相場」「葬儀 流れ 注意点」など、想定される検索クエリで検証し、回答内での位置や紹介のされ方を記録することが重要です。
競合他社との比較掲載状況や、推薦理由として挙げられる要素を分析することで、改善点を見つけやすくなります。
実際にAIに質問してみる
実際にAIに葬儀関連の質問をしてみて、回答にて自社サイトがどの程度引用されているかを確認しましょう。
AI回答では、根拠として参照元URLを明示するため、自社コンテンツの引用頻度や引用される内容を把握することができます。
特に料金情報、サービス内容、スタッフの資格などの重要情報がどのページから引用されているかを分析し、引用されやすいコンテンツの傾向を把握することで、今後のコンテンツ制作戦略に活用できるでしょう。
葬儀社がLLMOを始める際の注意点
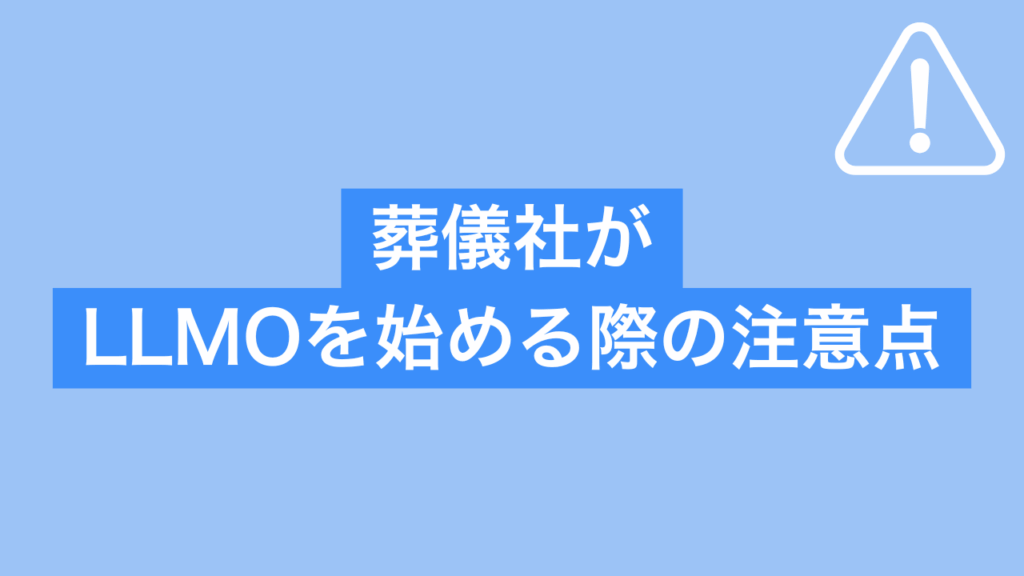
LLMOを導入する際は、葬祭業特有の法規制や倫理的配慮を慎重に確認しながら進めましょう。
生成AIが誤った情報を学習して拡散するリスクや、喪主の感情に配慮しない表現が問題となる可能性もあるため、慎重な情報発信が求められます。
葬儀という人生の重要な局面において、AIの回答が喪主の判断に大きな影響を与える可能性があるため、提供する情報の正確性と適切性には特に注意を払う必要があります。
法的リスクの回避と喪主への真摯な対応を両立させることが、持続可能なLLMO戦略の基盤となります。
景品表示法と表示ルールを遵守する
葬儀サービスの料金表示や広告表現は景品表示法の規制対象となるため、「最安値」「業界最大級」といった優良誤認を招く表現は避け、具体的な根拠を示した正確な情報を発信しましょう。
特に基本料金は、含まれるサービス内容を明確に記載し、追加費用が発生する可能性についても併記することで、AIが正確な情報を学習できるようにします。
また、他社との比較表現を行う際は客観的なデータに基づいた内容とし、誇大な表現や事実と異なる内容は掲載しないよう注意することも必要です。
これにより、AIが信頼性の高い情報として学習し、喪主に対して適切な情報を回答できます。
根拠と一次情報を必ず引用する
厚生労働省、自治体、業界団体などの公的機関や一次情報源を必ず明記し、AIが信頼性の高い情報として認識できるようにします。
例えば、葬祭費給付金については各自治体の公式サイト、火葬許可申請については戸籍法の条文、業界平均費用については日本消費者協会の調査結果など、具体的な出典を併記することが重要です。
また、単なる経験則や業界の慣習を記載する場合も、その根拠となる実績や統計データを可能な限り示すことで、AIからの評価が上がり、YMYL分野での信頼性確保につなげることができます。
個人情報の取り扱いに注意する
個人を特定できる情報は一切掲載せず、年代や性別、大まかな地域程度に留めることで、プライバシーを保護しつつ参考情報を提供します。
写真を使用する場合は故人や遺族の写真は避け、会場や装飾の様子のみを掲載し、個人情報保護方針も明確に記載することが重要です。
AIが学習する情報として、個人の詳細な情報が含まれていないことを確認し、匿名化された事例のみを提供することで、将来的なプライバシー問題を防ぐことができます。
顧客からの問い合わせ情報についても適切な管理体制を整備し、信頼できる葬儀社として認識されることを目指しましょう。
葬儀社向けのLLMO支援会社の選び方
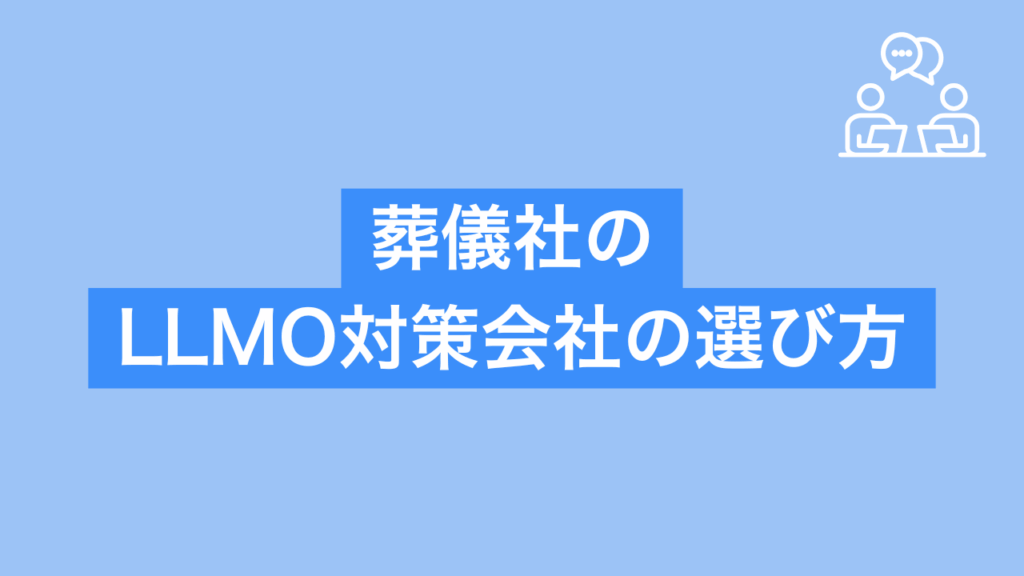
葬儀社向けのLLMO支援会社を選ぶ際は、LLMの最新の動向を熟知している業者を選ぶことで、効果が出やすくなります。
複数社からの提案を比較検討し、自社のニーズに最も適した支援内容を提供できる業者を選びましょう。
複数社に提案と見積もりを依頼する
業者によってサービス内容や料金体系が大きく異なることがあるため、最低3社以上から提案を受けて比較検討することが重要です。
提案内容では、実施期間、期待できる効果、リスク対策などを詳細に確認し、単純な料金比較だけでなく費用対効果を総合的に判断します。
月額固定制、成果報酬制、スポット契約など、異なる契約形態での見積もりも取得し、自社の予算と目標に最も合うプランを選定することが効果的です。
料金と支援範囲を確認する
初期費用、月額費用、成果報酬の有無を明確に確認し、どこまでが基本サービスでどこからが追加料金となるかを詳細に把握することが重要です。
契約期間の縛りや解約条件、途中での支援内容変更の可否なども事前に確認し、柔軟性のある契約条件を選択することで、効果が見込めない場合の方針変更にも対応できます。
長期的な視点で投資対効果を判断し、持続可能な予算範囲での支援を選択します。
LLMO診断を依頼する
現在の自社サイトがAIにどの程度認識されているか、改善すべきポイントはどこかを客観的に診断してもらうことで、具体的な課題と改善案を見つけることができます。
主要な生成AIサービスでの露出状況、構造化データの実装状況、コンテンツの品質評価、競合他社との比較分析などを含む診断を依頼し、現状の問題点を明確にしましょう。
無料診断を提供している会社も多いため、まずは複数社に診断を依頼して比較検討することが効果的です。
葬儀社のLLMOにお困りならまずはプロに相談しましょう
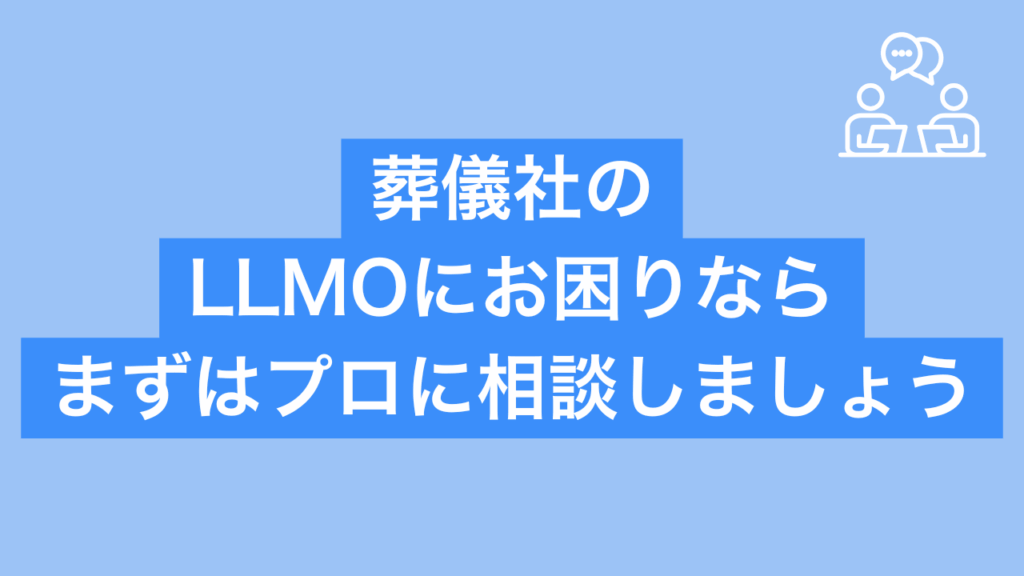
葬儀社のLLMO対策は、専門的な知識と効果の測定・改善を継続する必要があり、自社のみでの導入には限界があります。
まずは現状の診断から始めて、自社に最適な施策から取り組むことで、確実な効果を得ることができます。
LLMO対策でお悩みの葬儀社様は、業界に精通した専門業者に相談することから始めてみてください。
なお、TRILIA株式会社ではメディア運営で培った知見をもとに、LLMOを含むマーケティングの支援を行っています。
LLMOの導入をご検討中の方は、ぜひ下記からお気軽にお問い合わせください。
葬儀社のLLMOについてよくある質問
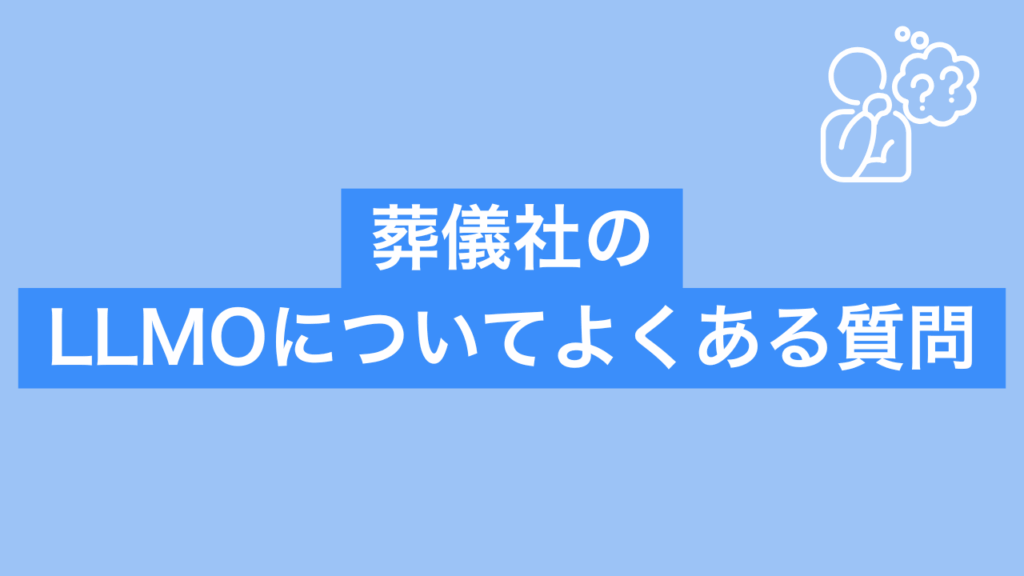
葬儀社のLLMO対策について、多くの事業者から寄せられる質問にお答えします。
新しい分野であるため、具体的な実施方法や効果、法的な問題について不安を感じる方も多いでしょう。
しかし、適切な知識を習得し、施策を着実に実行することで、成果が出やすくなります。
葬儀社はLLMOを何から始めればいいですか?
葬儀社のLLMO対策は、まず基本情報の整理から始めることをおすすめします。
会社概要、サービス内容、料金体系、スタッフの資格、連絡先などの基本情報を正確かつ詳細に整備し、構造化データの実装を行うことで、AIに正しい情報を認識してもらいましょう。
次に、よくある質問のFAQページを充実させ、喪主が疑問に思う内容について具体的で分かりやすい回答を用意すると効果的です。
これらの基礎的な対策を実施した後、AI回答での露出状況を確認し、段階的に改善を進めていくことで、着実に効果を積み上げることができます。
どのくらいの頻度で情報を更新すればいいですか?
葬儀社のLLMO対策では、基本情報は月1回程度の定期更新を行い、料金改定やサービス変更があった際は即座に更新することが重要です。
季節的な需要変動や地域の情勢変化に応じて、関連する情報の見直しも必要となります。
特にGoogleビジネスプロフィールや構造化データなどのAIが参照しやすい情報は、変更があった際の更新を優先し、常に最新の状態を維持することでAIの信頼性評価を向上させることができます。
コラムやFAQなどのコンテンツは週1回程度の更新が理想的ですが、品質を重視し、無理のない範囲で継続的に充実させていくことが大切です。
景品表示法とLLMOは両立できますか?
景品表示法の規制を遵守しながら、LLMO対策を実施することは十分に可能です。
重要なのは、優良誤認や有利誤認を招く表現を避け、事実に基づいた正確な情報提供を行うことです。
料金表示では基本サービスの内容を明確に記載し、追加費用の可能性も併記することで、透明性の高い情報を提供できます。
他社との比較を行う際は客観的なデータを根拠とし、誇大な表現は使用しないよう注意することで、法的リスクを回避しながらAIに正確な情報を学習させることができます。
むしろ、正確で詳細な情報提供は景品表示法の遵守とLLMO対策の両方に効果的であり、長期的な信頼性向上につながります。
LLMOやAI検索対策についてさらに詳しく知りたい方は、以下の関連記事もあわせてご覧ください。
葬儀社のLLMOの重要性と具体的な実践手順まとめ
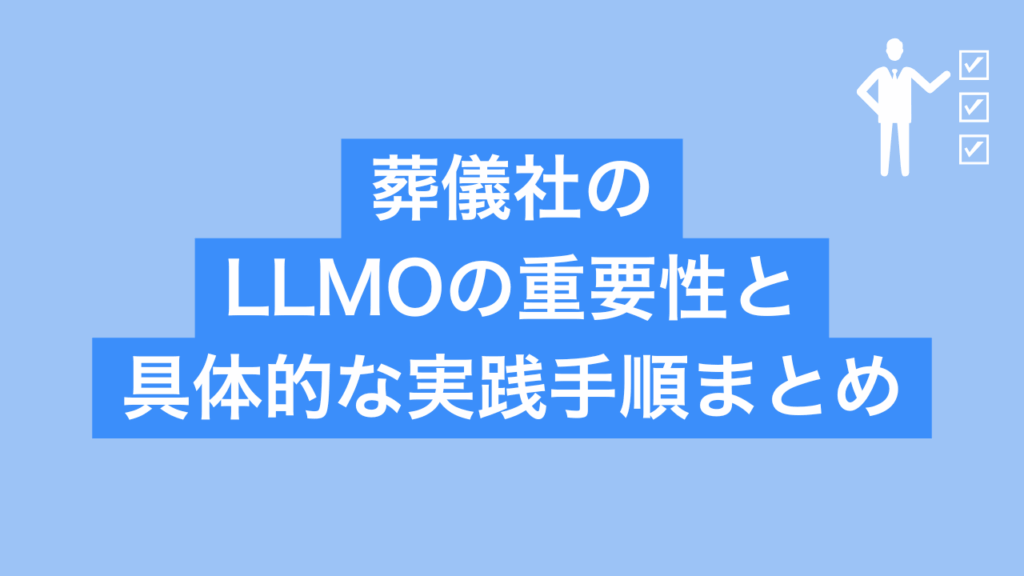
葬儀社のLLMOは、喪主や遺族の検索方法の変化に対応する重要な取り組みであり、AI回答に引用されることにより、集客UPが期待できます。
ただし、LLMO対策は専門的な知識やAIに関する最新情報が必要となるため、プロのサポートを受けながら進めることをおすすめします。
AIの回答の中で、信頼できる葬儀社としておすすめされることで、今後のAI検索の時代においても事業を拡大していくことができるでしょう。
「LLMOに取り組みたいが、何から始めればいいかわからない」
「自社サイトがAI検索でどう扱われているか知りたい」
TRILIA株式会社では、SEO・LLMO領域の専門知見と独自のAI分析基盤を活かし、完全成果報酬型のマーケティング支援を提供しています。初期費用0円で、まずは現状の課題整理からお手伝いいたします。