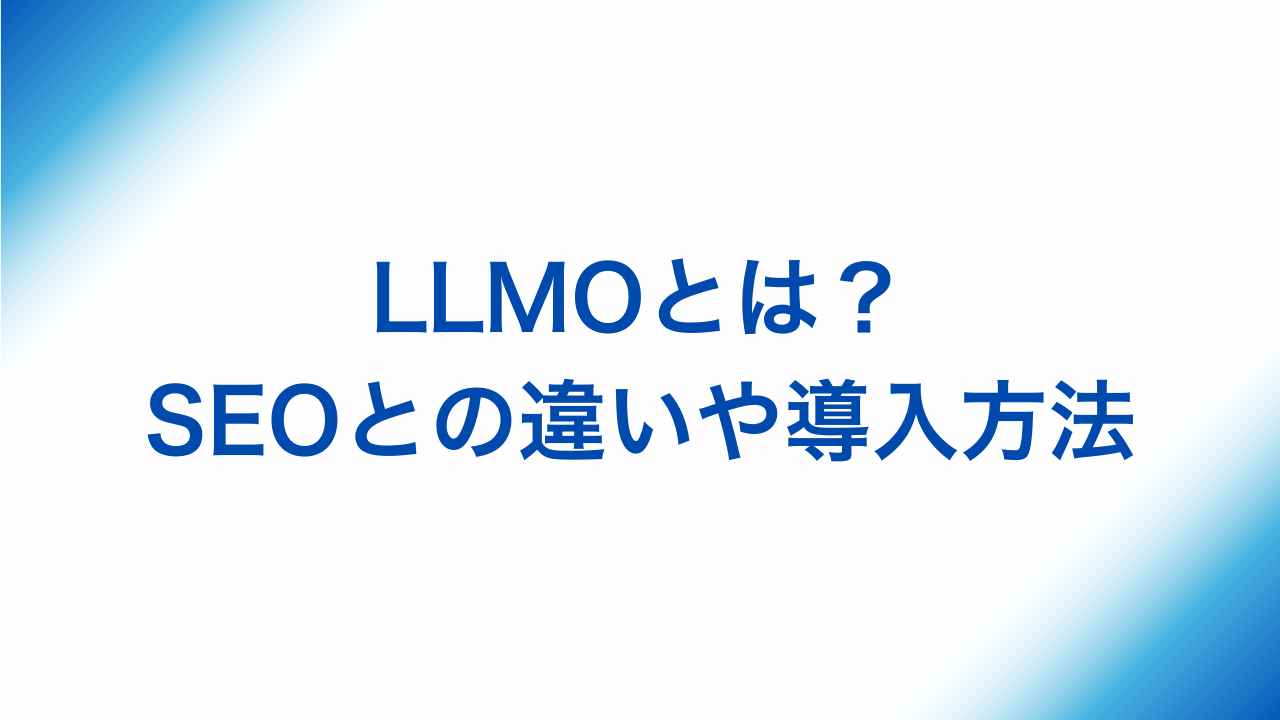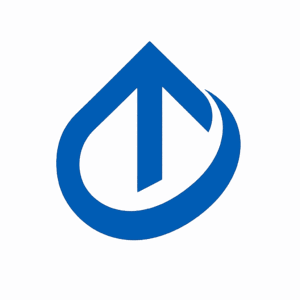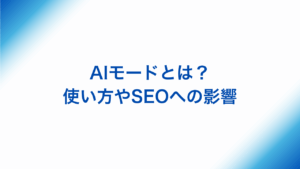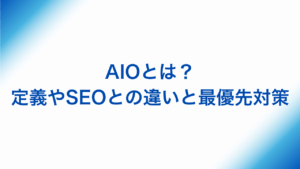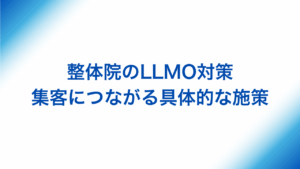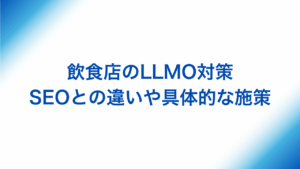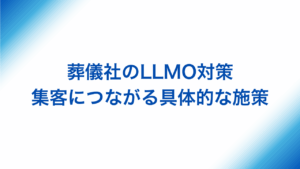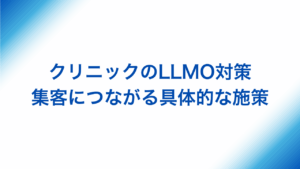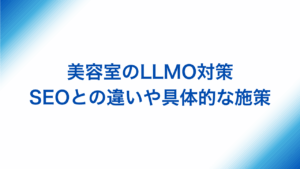この記事を読んでいるあなたは、
- LLMOとSEOの違いについて知りたい
- LLMOの具体的な導入方法について知りたい
- LLMO注意点について知りたい
このように考えているかもしれません。
この記事では、そんなあなたに「LLMOとSEOの違いや具体的な実践ステップ、注意点」について解説します。
LLMOとは

近年、その重要性が強調されているLLMOについて、以下の内容に基づき解説を行います。
- LLMOの読み方と正式名称
- LLMOの目的
- LLMOとSEOの違い
それぞれ解説します。
LLMOの読み方と正式名称
LLMOの読み方は「エルエルエムオー」で、英語の正式名称は「Large Language Model Optimization」です。
日本語では「大規模言語モデル最適化」と訳され、生成AIによる回答に自社のサービス名やサイトを引用されるための取り組みを意味します。
なお、厳密にはLLMOは和製英語であり、英語圏では必ずしも一般的な表現ではありませんが、日本市場ではAIOやGEOといった類似名称との混同を避けるため、この用語が主流となっています。
LLMOの目的
LLMOの主な目的は、生成AIが提示する回答文に自社のウェブページの情報が引用されることで、ブランドの認知向上と指名検索の増加を実現することです。
具体的には、AIの回答に自社のWebサイトのURLが引用される回数を増やして流入数を増加させ、同時に自社のブランド名や会社名・サービス名についての言及を増やすことで認知度を高めます。
また、従来の検索エンジン経由の流入が減少傾向にある中で、AIに引用されることが次世代の重要な集客チャネルになると考えられており、間接的な効果も含めた総合的なブランド価値向上を目指しています。
LLMOとSEOの違い
SEOは検索エンジンを主な対象とするのに対し、LLMOは生成AIを対象としています。
SEOは、Googleなどの検索エンジンを主な対象とし、主にWebサイトへの直接的なアクセス増加を狙うのに対し、LLMOはChatGPTやGeminiといった大規模言語モデルを対象とし、AIによる情報提供の中での引用や言及を通じて間接的に認知度や信頼性を高めることを重視します。
また、SEOが「検索されること」を前提とした設計であるのに対し、LLMOは「聞かれること」への最適化という点でも異なる点でしょう。
ただし、AIに引用されやすいページには検索順位が高いページが多いという傾向があり、両者には重なる点も多くあります。
LLMOが注目される背景
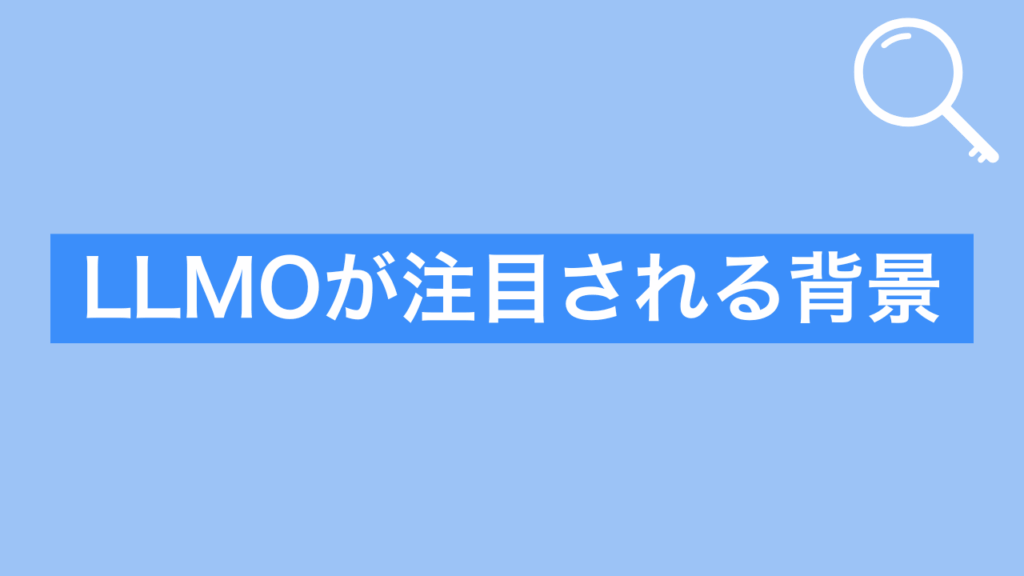
LLMOが注目される背景は、以下のとおりです。
- AI検索環境の急速な変化
- Google AI Overviewsの開始
- ゼロクリック検索による流入減少
それぞれ解説します。
AI検索環境の急速な変化
ChatGPTをはじめとする生成AIの登場により、ユーザーの情報収集行動が劇的に変化しています。
生成AIでは、質問を投げかけるだけで要約された回答を得られる点が利用者増加の要因と言えるでしょう。
従来のキーワード検索では、複数のWebサイトを訪問して情報を収集する必要がありましたが、生成AIでは質問を投げかけるだけで要約された回答を瞬時に得られる手軽さから、多くのユーザーが日常的に生成AIを活用するようになりました。
この変化により、企業は検索エンジンだけでなく生成AIからの引用も考慮したマーケティングが必要になり、AIが参照するコンテンツとして自社情報を最適化することの重要性が急速に高まっています。
Google AI Overviewsの開始
GoogleがAI Overviews(旧SGE)を正式に導入したことで、従来の検索結果の上位に生成AIによる要約回答が表示されるようになりました。
そのため、AI Overviewsに自社情報が引用されることで、検索結果の最上部に表示されることが企業にとって重要になっています。
ゼロクリック検索による流入減少
ゼロクリック検索とは、検索結果の最上部に表示されるAIの要約のみでユーザーが満足し、Webサイトをクリックしないことを指します。
Google AI Overviewsや強調スニペットの拡充により、このゼロクリック検索の割合が大幅に増加し、企業のWebサイトへの直接流入が著しく減少しています。
従来のSEO施策で上位に表示されても、AIによる要約回答でユーザーの疑問が解決されてしまうため、クリック率の低下が深刻な問題となっています。
この状況において、AIの回答に引用される形で自社情報を表示させるLLMOが、新たな集客手法として企業の注目を集めているのです。
LLMOの仕組み

LLMOの仕組みは、以下のとおりです。
- 大規模言語モデルが回答を生成する流れ
- E-E-A-Tの重要性
- ハルシネーションの抑制
それぞれ解説します。
大規模言語モデルが回答を生成する流れ
大規模言語モデルが回答を生成する流れは、まずユーザーからの質問を理解し、関連性の高い情報源を特定することから始まります。
AIは学習済みデータと合わせてリアルタイムで検索可能な最新のWebコンテンツを分析し、信頼性・正確性・関連性の観点から最適な情報を抽出します。
この際、構造化データが適切に設定されているサイトや、明確な回答形式で情報が整理されているコンテンツが優先的に選ばれる傾向があります。
さらに、権威性の高いドメインや専門性のあるコンテンツ、引用元が明確な一次情報なども重要な選択基準となり、これらの要素を満たすコンテンツほどAIの回答に引用される可能性が高くなります。
E-E-A-Tの重要性
E-E-A-T(Experience、Expertise、Authoritativeness、Trustworthiness)は、生成AIがコンテンツを評価する際にも重要です。
特に経験(Experience)に基づいた実体験の情報や、専門性(Expertise)を示す詳細な解説、業界内での権威性(Authoritativeness)を持つサイトのコンテンツは、AIによって高く評価され引用されやすくなります。
信頼性(Trustworthiness)の面では、著者情報や運営体制の記載、引用元の明確化などが重要視されており、これらの要素が揃ったコンテンツはAIが信頼できる情報源として認識されます。
したがって、LLMOにおいてもE-E-A-Tの各要素を満たすコンテンツ制作と情報発信が、引用率の向上につながるでしょう。
ハルシネーションの抑制
ハルシネーション(AI の誤った情報生成)を抑制するため、大規模言語モデルは信頼性の高い情報源を重視する傾向があります。
具体的には、一次情報の提供、データの出典明示、専門機関や公的機関からの情報、複数の信頼できるソースによる裏付けなどがあるコンテンツが優先的に参照されます。
また、曖昧な表現や推測に基づく記述よりも、具体的な数値や事実に基づいた明確な記述がAIによって選ばれやすくなっています。
LLMO対策では、これらのハルシネーション抑制機能に対応するため、正確性を重視したコンテンツ作成と、情報の根拠を明示することが重要です。
LLMOの技術的対策
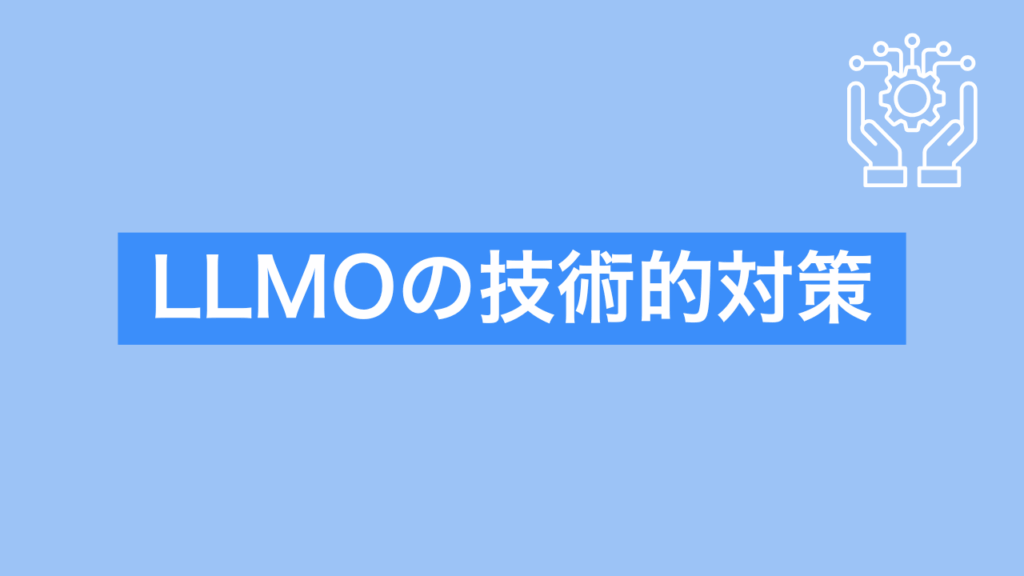
LLMOの技術的対策は、以下のとおりです。
- 構造化データの活用
- llms.txtの設置
- Core Web Vitalsの最適化
それぞれ解説します。
構造化データの活用
構造化データは、AIがWebページの内容を正確に理解し、適切に引用するための重要な技術的要素です。
JSON-LDでのFAQマークアップや著者情報の明示などを適切に実装することで、大規模言語モデルがコンテンツの意味と文脈を的確に把握できるようになります。
特に質問と回答形式のコンテンツでは、FAQスキーマを活用することでAIが回答として引用しやすい形式に情報を整理できます。
また、組織情報や専門性を示すスキーママークアップを実装することで、E-E-A-Tの評価向上にも寄与し、AIからの信頼性を高めることが可能です。
llms.txtの設置
llms.txtは、AIクローラーに対してWebサイトの構造や重要なコンテンツを伝えるためのファイルとして注目されていますが、現時点では標準化されておらず、設置したことによる効果については議論が分かれています。
一部の専門家は、AIがWebサイトを効率的にクロールし、重要な情報を優先的に参照するための有効な手段として推奨していますが、大手の生成AIサービスがllms.txtを正式に採用しているかは明確ではありません。
設置を検討する場合は、サイト全体の構造や主要コンテンツへの案内、クロール対象の優先順位などを記載することが一般的ですが、過度な期待は避け、他の確実な技術的対策と併用することがおすすめです。
Core Web Vitalsの最適化
Core Web Vitalsの最適化は、AIクローラーがWebサイトに効率的にアクセスし、コンテンツを取得するために重要な技術的対策です。
ページの読み込み速度(LCP)、操作への応答性(FID/INP)、視覚的安定性(CLS)の改善により、AIがサイトを巡回する際のアクセシビリティが向上します。
特に読み込み速度の改善は、AIが大量のWebページを効率的に処理する際の重要な要素となるため、画像の最適化、コードの軽量化、サーバーレスポンス時間の短縮などが必要です。
LLMOのコンテンツ戦略
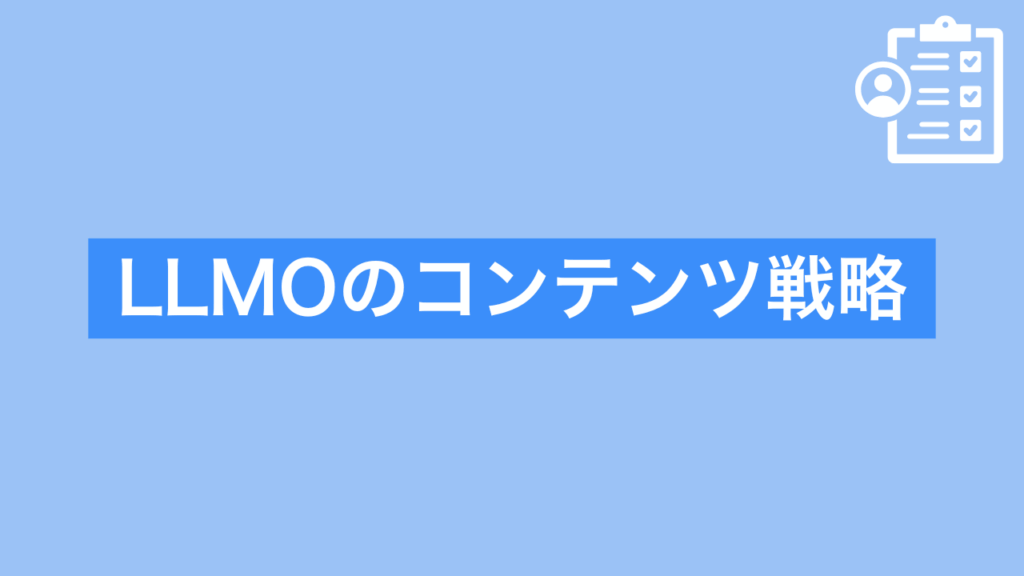
LLMOのコンテンツ戦略は、以下のとおりです。
- 質問と回答形式の採用
- 一次情報の提示
- 著者と運営体制の明示
- 外部からの言及の獲得
それぞれ解説します。
質問と回答形式の採用
質問と回答形式の採用により、生成AIがユーザーの疑問に対する回答を生成する際に、自社の情報を引用しやすくなります。
「〇〇とは何ですか?」「〇〇の方法は?」といった具体的な質問に対して、明確で簡潔な回答を提示することで、AIが回答として引用しやすくなるでしょう。
この際、回答部分は最初に結論を述べ、その後に詳細な説明を続けると効果的です。
また、FAQ形式でよくある質問をまとめたセクションを設けることで、多様なユーザーの疑問に対応でき、AIが異なる質問パターンに対して自社コンテンツを参照する機会が増加します。
一次情報の提示
一次情報を提示することによって、AIからの信頼性が高くなり、引用されやすくなります。
自社で実施した調査結果、インタビュー内容、実験データ、業界統計などのオリジナル情報を含むコンテンツは、AIが貴重な情報源として高く評価し、積極的に引用する傾向があります。
データを提示する際は、調査期間、対象者数、調査方法などの詳細を明記し、グラフや表を用いて視覚的に分かりやすく表現することが重要です。
また、定期的なデータ更新や調査実施により、常に最新で信頼できる情報源として認識されることも大切です。
著者と運営体制の明示
著者と運営体制を明示することは、AIがコンテンツの信頼性を判断する際の重要な評価基準となります。
コンテンツの執筆者の経歴、保有資格、実績を詳細に記載し、運営会社の概要、所在地、連絡先などを明確に表示することで、E-E-A-Tの権威性と信頼性を向上させることができます。
特に専門的な分野では、著者の専門性を裏付ける具体的な情報(学位、職歴、発表論文、所属団体など)を提示することが効果的です。
外部からの言及の獲得
外部からの言及を得ることは、AIが複数の情報を参照する際に大きく影響します。
業界メディアへの専門記事の寄稿、権威あるWebサイトでのインタビュー掲載、学術論文での引用獲得などを通じて、他者からの自然な言及を増やすことが効果的です。
また、SNSでの専門的な情報発信、業界イベントでの講演活動、他の専門家との対談なども、間接的に外部からの言及を増やすきっかけになります。
外部からの言及を増やすことによって、AIが「多方面から言及される信頼できる情報源」として自社コンテンツを認識し、引用頻度の向上につながります。
LLMOの効果測定と改善
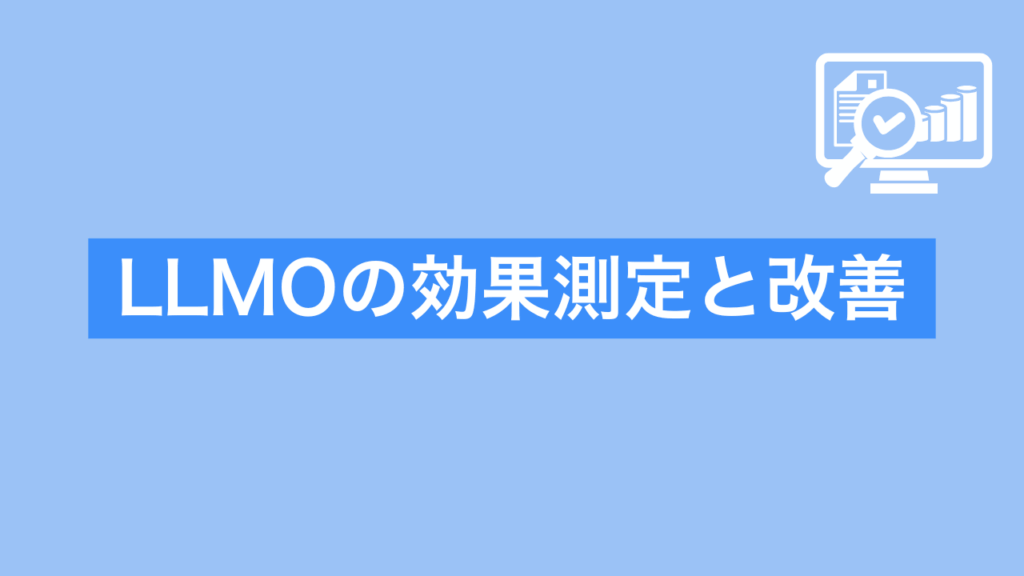
LLMOの効果測定と改善は、以下のとおりです。
- AI経由流入の確認
- 引用率とサイテーションの分析
- 改善点の洗い出し
それぞれ解説します。
AIからの流入の確認
AI経由の流入については、従来のGoogleアナリティクスだけでは完全に把握できないため、複数の方法で確認しましょう。
まず、リファラー情報から「chatgpt.com」「bard.google.com」「bing.com/search」などのAI関連ドメインからの流入があるか確認し、カスタムセグメントを設定してAI経由のトラフィックを分析しましょう。
また、特定のランディングページやFAQページへのアクセス数が増加している場合も、AIから引用されている可能性が高いです。
さらに、検索クエリデータから従来とは異なる長文の質問形式での流入増加も、ユーザーがAIに質問をした時の回答として引用されていることがあります。
引用率とサイテーションの分析
ChatGPTやGeminiで自社に関連するキーワードで質問を投げかけ、回答内での自社情報がどれくらい引用されるか定期的に確認しましょう。
また、Google AlertsやMention.comなどのツールを活用して、Web上での自社ブランドやコンテンツへの言及を分析することもできます。
改善点の洗い出し
月次でAIからの引用状況を分析し、引用されやすいコンテンツの特徴を特定して他のページにも横展開し、逆に引用されていないコンテンツについては構造や内容の見直しを行いましょう。
また、新しいAIツールやアルゴリズムの変更に対応するため、最新のLLMO手法をリサーチすることも大切です。
LLMOを導入する手順

LLMOを導入する手順は、以下のとおりです。
- 現状分析を行う
- 施策の優先度を決める
- 運用体制を整える
それぞれ解説します。
現状分析を行う
自社のWebサイトがAIに引用されやすいかどうか現状を客観的に分析しましょう。
以下の流れで分析することをおすすめします。
まず、主要なAIツール(ChatGPT、Gemini、Bing AI)で自社に関連するキーワードを検索し、現在の引用状況や言及内容を確認してください。
次に、自社のWebサイトの構造化データの実装状況、ページ速度、モバイル対応度を分析しましょう。
コンテンツ面ではFAQを設定しているか、一次情報が明記されているか、著者情報が記載されているかを確認してみてください。
競合他社のAI引用状況と比較分析を行い、自社との違いを確認することで、具体的な改善案を洗い出しましょう。
施策の優先度を決める
分析結果を踏まえ、構造化データの追加や一次情報の明記など、効果が期待できる施策から優先的に取り組みましょう。
低コストでできる施策でも引用率が10%以上伸びるケースがあるため、積極的に改善していきましょう。
運用体制を整える
最後に、継続的にLLMO対策を実施するための運営体制を整えましょう。
効果のあった施策を社内で共有し、それぞれの役割を決めることでLLMO対策を仕組み化することができます。
LLMOについてよくある質問
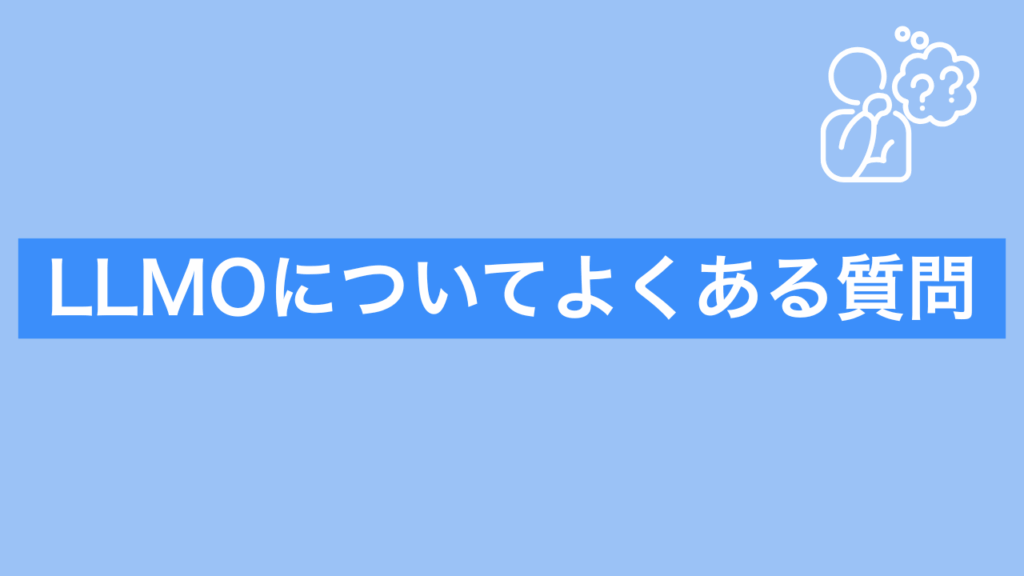
LLMOについてよくある質問は、以下のとおりです。
- SEOは不要になる?
- LLMOの効果が出るまで何日くらいかかる?
- LLMOの費用相場はどのくらい?
それぞれ解説します。
SEOは不要になる?
LLMOとSEOは相互に補完する関係にあり、SEO対策が不要になるわけではありません。
現状、SEOで上位に表示されているコンテンツが生成AIに引用されることが多くあるため、SEO対策とLLMO対策を並行して行うことで、より効果が現れやすくなるでしょう。
LLMOの効果が出るまで何日くらいかかる?
LLMOの効果が現れるまでの期間は、施策の内容と規模によって大きく異なりますが、一般的には3か月から6か月程度の取り組みが必要です。
構造化データの実装や既存コンテンツの修正などの施策では、1か月から2か月程度で効果が出る場合がありますが、一次情報の記載や新規コンテンツ制作などの施策では、インデックスとAIの学習に時間がかかるため、効果を実感できるまで3か月以上かかる可能性があります。
LLMOの費用相場はどのくらい?
LLMOの費用相場は、実施する施策の規模と外部委託の度合いによって大幅に異なりますが、自社で基本的な施策を行う場合は月額10万円から30万円程度、専門業者に包括的に委託する場合は月額30万円から100万円程度が一般的な相場となっています。
ただし、LLMO市場はまだ新しく、サービス内容や品質にばらつきがあるため、複数の業者から提案を受けて比較検討し、自社のニーズと予算に最適な選択することが重要です。
LLMOが注目される背景や仕組み、導入する手順まとめ
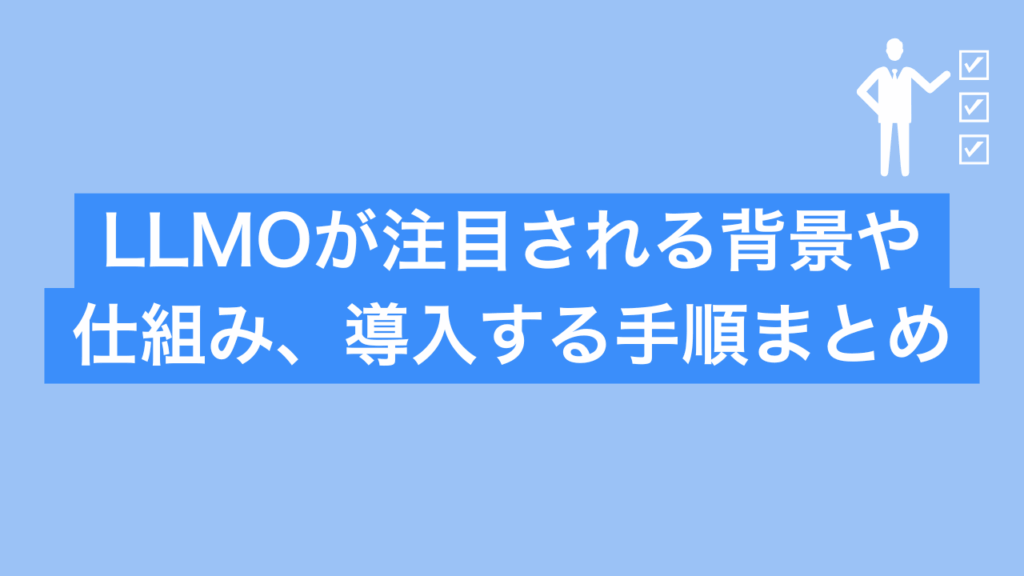
本記事では、近年注目を集めているLLMOの背景や仕組み、そして具体的な施策について解説しました。
今後、AI検索やAIによる回答表示がさらに増加するにつれ、従来のSEOだけでなく、LLMOの重要性も一層高まっていくと考えられます。
そのため、今のうちからLLMOに取り組むことをおすすめします。
なお、TRILIA株式会社ではメディア運営で培った知見をもとに、LLMOを含むマーケティング支援事業を展開しています。
LLMOにご興味をお持ちのご担当者様は、まずは下記よりお気軽にお問い合わせください。